世界経済評論IMPACT(世界経済評論インパクト)
「21世紀の不平等条約」への抵抗:ASEANは米国の相互関税にどう対峙すべきか
(国士舘大学政経学部 教授・泰日工業大学 客員教授)
2025.09.01
相互主義の理念のない「相互関税」
米国トランプ政権は2025年4月,世界各国を対象に国別に税率の異なる「相互関税」を課す方針を示した。名称自体は,第二次世界大戦後のグローバリズムを追求してきた国際協力体制を理解する上での相互主義,互恵主義を想起させるが,実態は大きく異なる。トランプ政権は高関税を一方的に突き付け,関税を引き下げる条件として,米国が相手国に与える待遇以上の譲歩を求める手法を採っている。
以降,米国は90日間の猶予期間を設け,二国間交渉に重点を移したが,東南アジアの中で46%の相互関税を課すと脅されたベトナムが先んじて米国と交渉,相互関税20%で合意した。これに当初32%を提示されたインドネシアが続き,19%で合意した。フィリピンも19%で合意している。
その一方で,これら各国は米輸出品に対し,関税ゼロでの「全市場アクセス」の提供を提供していると報じられている。これは,一見,交渉と妥協の産物のように映るが,実態は米国の市場アクセスを拡大するための手段に過ぎず,相互的な自由貿易とは程遠い。一方的な関税引き上げとそれに付随する協定の締結は,事実上,東南アジア諸国の経済主権を制限する効果を持つ。
「21世紀型不平等条約」としての相互関税
このような状況は,大航海時代以降,欧米列強による植民地支配と,不平等条約の強制的締結の歴史を想起させる。特に,シャム王国(現タイ)は,植民地化こそ免れたものの,1855年に英国との間でボーリング条約,および翌1856年には米国との間でハリス条約を締結,治外法権や関税自主権の喪失といった不平等な条件を受け入れざるを得なかった。
シャムは,これらの条約を改正するために,近代化と数十年にわたる外交努力を重ねる必要があった。最終的に1937年の改正条約によってようやく治外法権の撤廃,関税自主権の回復が実現した。米国の相互関税措置は,いわば「21世紀型の不平等条約」である。形式上は交渉による二国間協定の体裁をとっているが,強大な経済力と市場を背景に圧力をかけ,相手国に不利な条件を呑ませる構図は,過去の帝国主義的な手法と何ら変わらない。これを「相互主義」と呼ぶのは言葉のすり替えであり,実態は「選択の自由なき交渉」,すなわち経済的従属関係の強要である。こうした手法は,主に19世紀に欧米列強がアジア・アフリカ諸国に用いた「砲艦外交」と本質的に変わらず,経済力という名の圧力によって構造的に不平等な国際秩序を再構築しようとするものである。
ASEANを分断する圧力と国際的リスク
米国の政策に対し,ベトナムやインドネシアなどASEAN加盟国が,それぞれの立場から協定に応じたとしても,それはASEAN全体の利益や,ASEANの原則とは必ずしも一致しない。むしろ,米国が各国を個別に分断して交渉することで,ASEANの交渉力が削がれている現状は,過去に列強がアジア・アフリカ諸国に対して採った「分割して統治する(divide and rule)」政策を連想させる。
国家間の結束が欠如すれば,共通外交・経済政策の土台が失われ,また個々の国は圧力に屈しやすくなり,やがては地域全体が不利な条件を受け入れざるを得なくなる恐れがある。
さらに懸念すべきは,こうした関税協定がASEAN内部に「遠心力」として作用しかねない点である。加盟国間で米国との協定内容や関税水準に大きな格差が生じれば,他国が米国との交渉に追随せざるを得なくなり,またASEAN内の公平性と結束が揺らぎかねず,「ASEAN中心性」の理念が毀損しかねない。
また,これらの協定は世界貿易機関(WTO)の最恵国待遇(MFN)原則に抵触する可能性をはらんでいる。米国製品のみが無税または低関税でASEAN市場に参入できる場合,他国は差別的待遇とみなされ,WTO違反として他国から提訴されるリスクがある。これはASEAN諸国にとって法的・外交的に重大な問題であり,短期的な利益を優先すれば,長期的な信頼や経済安定を損なうことにつながる可能性がある。
ゆえに,東南アジア諸国はタイの歴史的経験に学び,ASEAN全体として協調し,米国との再交渉に臨むべきである。包括的な地域的経済連携(RCEP)協定や日ASEAN包括的経済連携協定(AJCEP)などの地域協定の枠組みを活かしつつ,7億人を超える経済圏としての集団的な力を行使することで,21世紀の不平等条約に抵抗すべきである。そうでなければ,21世紀の国際貿易は,かつての帝国主義的支配の再現となる危険すら孕んでいる。タイがかつて不平等条約の改正に数十年を要したことを想起し,ASEANも今こそ連携し,21世紀の不平等に立ち向かうべきときである。
関連記事
助川成也
-
[No.4076 2025.11.10 ]
-
[No.4041 2025.10.20 ]
-
[No.4024 2025.10.06 ]
最新のコラム
-
New! [No.4178 2026.01.19 ]
-
New! [No.4177 2026.01.19 ]
-
New! [No.4176 2026.01.19 ]
-
New! [No.4175 2026.01.19 ]
-
New! [No.4174 2026.01.19 ]
世界経済評論IMPACT 記事検索
おすすめの本〈 広告 〉
-
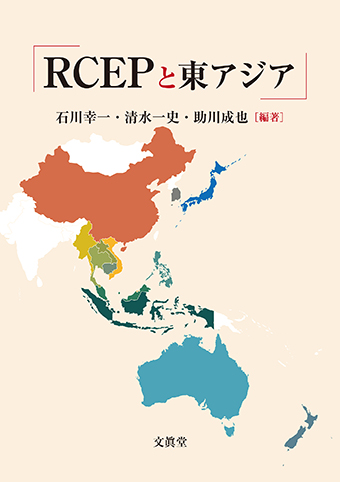 RCEPと東アジア
本体価格:3,200円+税 2022年6月
RCEPと東アジア
本体価格:3,200円+税 2022年6月
文眞堂 -
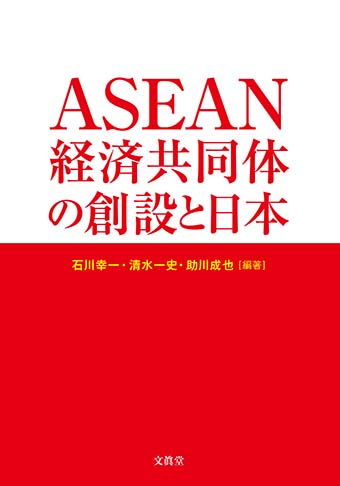 ASEAN経済共同体の創設と日本
本体価格:2,800円+税 2016年11月
ASEAN経済共同体の創設と日本
本体価格:2,800円+税 2016年11月
文眞堂 -
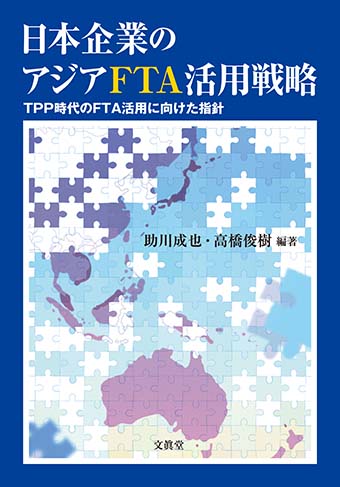 日本企業のアジアFTA活用戦略:TPP時代のFTA活用に向けた指針
本体価格:2,400円+税 2016年2月
日本企業のアジアFTA活用戦略:TPP時代のFTA活用に向けた指針
本体価格:2,400円+税 2016年2月
文眞堂 -
 グローバルサウス入門:「南」の論理で読み解く多極世界
本体価格:2,200円+税 2025年9月
グローバルサウス入門:「南」の論理で読み解く多極世界
本体価格:2,200円+税 2025年9月
文眞堂 -
 職場・学校のセクハラ・パワハラ :ハラスメントの法と判例
本体価格:1,300円+税 2026年1月
職場・学校のセクハラ・パワハラ :ハラスメントの法と判例
本体価格:1,300円+税 2026年1月
文眞堂 -
 DEIBにおける経営倫理とCSRの役割:障害者雇用と女性、LGBT、がん患者の方々に焦点を当てて
本体価格:2,700円+税 2025年10月
DEIBにおける経営倫理とCSRの役割:障害者雇用と女性、LGBT、がん患者の方々に焦点を当てて
本体価格:2,700円+税 2025年10月
文眞堂 -
 国際マーケティングの補助線
本体価格:2,700円+税 2025年9月
国際マーケティングの補助線
本体価格:2,700円+税 2025年9月
文眞堂 -
 これさえ読めばすべてわかるアセットマネジメントの教科書
本体価格:2,900円+税 2025年9月
これさえ読めばすべてわかるアセットマネジメントの教科書
本体価格:2,900円+税 2025年9月
文眞堂 -
 高収益経営とアントレプレナーシップ:東燃中原延平・伸之の軌跡
本体価格:3,900円+税 2025年11月
高収益経営とアントレプレナーシップ:東燃中原延平・伸之の軌跡
本体価格:3,900円+税 2025年11月
文眞堂 -
 ルビーはなぜ赤いのか?:川野教授の宝石学講座
本体価格:2,500円+税
ルビーはなぜ赤いのか?:川野教授の宝石学講座
本体価格:2,500円+税
文眞堂

