世界経済評論IMPACT(世界経済評論インパクト)
中国は自由貿易の「旗手」たりうるか:WTOルール運用と制度の実態からの検証
(国士舘大学政経学部 教授・泰日工業大学 客員教授)
2025.07.21
近年,米国は多国間協定や自由貿易体制から距離を置き,保護主義に傾倒していることに代わり,中国が自らを「自由貿易・多国間主義の擁護者」として国際社会に印象づけようとしてきた。たとえば,2021年のダボス会議で習近平国家主席は「経済のグローバル化を拒むべきではない」と述べ,自由貿易の重要性を訴えた(注1)。
しかし,実際の中国の通商政策や外交手法は,その発言と大きく乖離している。特に注目すべきは,補助金政策の不透明性,国有企業への過度な支援,WTO協定上の通報義務の不履行,そして経済的威圧と受け止められる輸出入制限措置の数々である。中国は2018年以降,オーストラリアによる新型コロナの起源調査要求に反発し,ワイン・牛肉・大麦などへの輸入制限を課したほか,台湾との関係強化を進めたリトアニアにも報復的措置を取った。これらは「健康保護」や「国家安全保障」などを名目としているが,WTOルールを形式的に回避する措置であり,国際社会からは詭弁と見なされている。
WTO上の義務と現実:透明性欠如がもたらす不信
中国は2001年のWTO加盟時に,通商制度の透明性確保,統一的な運用,司法的なレビュー制度の導入を約束している。GATT第10条(通商規則の公表及びその運用)やGATS第6条(内国民待遇に係る措置の運用)に基づき,すべての貿易関連措置は公開され,国内外の企業に等しく適用されなければならない。
しかし,実態はその理想からほど遠い。地方政府が発出する規則や通達が未公表のままとなることも多く,企業は制度変更に迅速に対応することが困難である。また,WTO補助金協定第25条に基づく補助金の通報義務も十分に果たしておらず,制度運用の透明性を欠いている。このような姿勢は,自由貿易の根幹である「予見可能性」や「ルールへの信頼」を損なうものである。
補助金と国有企業:構造的歪みと競争条件の不平等
中国の補助金政策と国有企業制度は,市場競争を大きく歪めている。鉄鋼,アルミニウム,半導体,造船,電気自動車(EV)などの戦略分野では,国家主導の補助金が非効率な企業を温存させ,過剰供給が常態化している。とくに近隣諸国では,中国製品の不当廉売が指摘されている。
また,中国の国有企業は商業的判断に基づかず,政府の政策誘導により動いているとされる。GATT第17条は,国有貿易企業が「商業的考慮(commercial considerations)」に従って行動し,外国企業に対して差別的な取り扱いをしてはならないと規定しているが,1947年策定のこの条文は抽象的で,抑止力や透明性に欠ける。
一方,CPTPP(環太平洋パートナーシップに関する包括的および先進的な協定)や日EU経済連携協定(EPA)では,国有企業に対して「無差別待遇義務」や「商業的考慮義務」が明確に規定されている。これにより,国有企業が自国企業を優遇し,外国企業に不利な条件で取引を行うことを禁じており,「競争条件の対等性(Level Playing Field)」を確保する仕組みが整っている。中国のこれら措置は,CPTPPでは「競争条件の対等性」が確保されているとは言い難い。
WTO紛争事例から見た中国の問題行動
中国はWTO紛争解決制度でもたびたび被申立国となっており,補助金支給,アンチ・ダンピング,輸出制限などをめぐって,日本,米国,EUなどとの間で複数の紛争を抱えている。たとえば,日本製化学品や鉄鋼製品に対する高関税措置や不当なダンピング認定は,日本から提訴され,WTO判断でも中国側の措置が問題視された。
また,中国は希少資源に輸出制限を課しており,WTO協定違反の懸念がある。これらの行動は,自由貿易の基本原則に反するだけでなく,他国の経済的選択肢を狭める結果を招いている。
日本の対応と国際社会への制度的提案
これら状況に対し,日本はEPAやCPTPPを通じて,補助金の透明性確保,国有企業の行動規範化といった分野で,実効性のあるルール整備を主導してきた。これらの協定では,WTO協定よりも具体性の高い規律が設けられており,中国が今後国際貿易秩序の一員として信頼を獲得したいのであれば,こうしたルールを受け入れる姿勢が求められる。
自由貿易は,すべての市場参加者が同じルールの下で競争できる「公正な競争条件」が前提である。中国の現在の制度・慣行は,WTOの基本理念に抵触しており,「自由貿易の旗手」を名乗るには不十分である。むしろ「ルールを都合よく解釈し,行動が伴わないプレイヤー」との懸念が国際社会に広がっている。
中国が本当に自由貿易体制や多国間枠組みの「旗手」としての地位を確立したいのであれば,まずはWTO協定上の義務の誠実な履行,補助金政策の透明化と通報,そして国有企業の商業的独立性の確保を着実に進めることが不可欠である。発言ではなく,制度と実行こそが旗手の資格を決める。
[注]
- (1)Xi Jinping warns against "new cold war" in Davos speech
関連記事
助川成也
-
[No.4076 2025.11.10 ]
-
[No.4041 2025.10.20 ]
-
[No.4024 2025.10.06 ]
最新のコラム
-
New! [No.4194 2026.02.02 ]
-
New! [No.4193 2026.02.02 ]
-
New! [No.4192 2026.02.02 ]
-
New! [No.4191 2026.02.02 ]
-
New! [No.4190 2026.02.02 ]
世界経済評論IMPACT 記事検索
おすすめの本〈 広告 〉
-
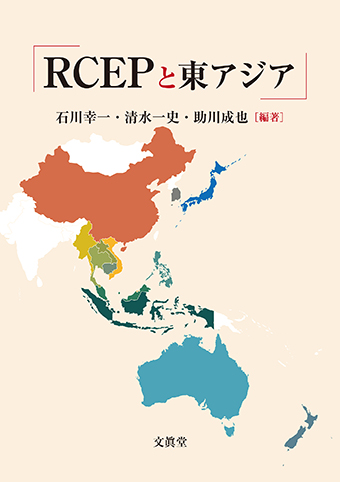 RCEPと東アジア
本体価格:3,200円+税 2022年6月
RCEPと東アジア
本体価格:3,200円+税 2022年6月
文眞堂 -
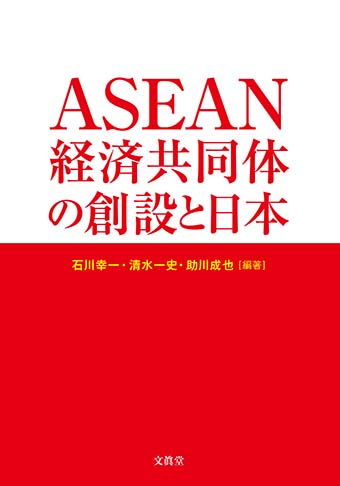 ASEAN経済共同体の創設と日本
本体価格:2,800円+税 2016年11月
ASEAN経済共同体の創設と日本
本体価格:2,800円+税 2016年11月
文眞堂 -
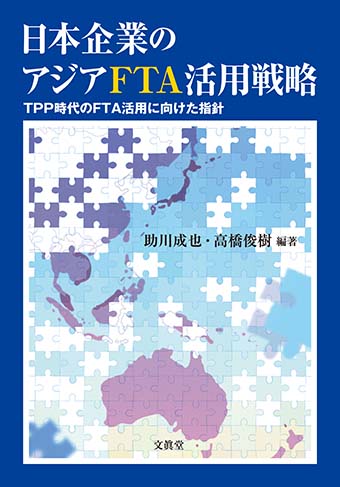 日本企業のアジアFTA活用戦略:TPP時代のFTA活用に向けた指針
本体価格:2,400円+税 2016年2月
日本企業のアジアFTA活用戦略:TPP時代のFTA活用に向けた指針
本体価格:2,400円+税 2016年2月
文眞堂 -
 職場・学校のセクハラ・パワハラ :ハラスメントの法と判例
本体価格:1,300円+税 2026年1月
職場・学校のセクハラ・パワハラ :ハラスメントの法と判例
本体価格:1,300円+税 2026年1月
文眞堂 -
 これさえ読めばすべてわかるアセットマネジメントの教科書
本体価格:2,900円+税 2025年9月
これさえ読めばすべてわかるアセットマネジメントの教科書
本体価格:2,900円+税 2025年9月
文眞堂 -
 高収益経営とアントレプレナーシップ:東燃中原延平・伸之の軌跡
本体価格:3,900円+税 2025年11月
高収益経営とアントレプレナーシップ:東燃中原延平・伸之の軌跡
本体価格:3,900円+税 2025年11月
文眞堂 -
 国際マーケティングの補助線
本体価格:2,700円+税 2025年9月
国際マーケティングの補助線
本体価格:2,700円+税 2025年9月
文眞堂 -
 ソーシャルマーケティング:行動変容で社会的価値を共創する
本体価格:3,500円+税 2025年12月
ソーシャルマーケティング:行動変容で社会的価値を共創する
本体価格:3,500円+税 2025年12月
文眞堂 -
 中国鉄鋼業:生産システム,企業,産業の三層構造と産業政策
本体価格:4,000円+税 2025年8月
中国鉄鋼業:生産システム,企業,産業の三層構造と産業政策
本体価格:4,000円+税 2025年8月
文眞堂 -
 「気づき」あれこれ―2013~2025―
本体価格:2,000円+税
「気づき」あれこれ―2013~2025―
本体価格:2,000円+税
文眞堂

