世界経済評論IMPACT(世界経済評論インパクト)
2035年温室効果ガス排出19年比60%削減:国際公約の衝撃波が政府・自治体・企業を襲う
(国際大学 学長)
2023.11.27
2023年5月に広島で開催されたG7(先進7ヵ国首脳会議)に先立って,同年4月には先進7ヵ国のエネルギー・環境担当大臣会合が札幌で開催された。この札幌会合について多くのメディアは,「石炭火力廃止の時期が明示されなかった」とか,「原子力が選択肢の一つとして認められた」とか,「天然ガスも長期的には削減対象に含まれた」とかに重点をおいて,報道を行った。しかし,これらの報道は,いずれも「的外れ」だと言わざるをえない。取り上げた論点に,目新しい内容は何も含まれていないからである。
先進7ヵ国のエネルギー・環境担当大臣による札幌会合の「肝(きも)」は,別なところにある。同会合の共同声明に,2035年の温室効果ガス(GHG)排出削減目標について,「2019年比60%減」という数値が盛り込まれたことこそが,「肝心要(かんじんかなめ)」なのである。
今のところ,経済産業省や環境省の関係者は,この「2035年GHG排出19年比60%削減」目標は「国際公約ではない」と言い張っている。しかし,この言い分は,世界で通用するだろうか。議長国である日本が共同声明に明記された内容に対して,「あれは言及しただけであって約束ではない」と言い繕うことが国際的にまかり通るとは,とうてい思えない。早晩,「2035年GHG排出19年比60%削減」目標は,日本の新しい国際公約とみなされることになるだろう。すでに海外では,そのような見方が広がり始めている。
日本のこれまでの国際公約は,「2030年度にGHGの排出を2013年度比で46%削減する」というものであった。2013年度から2019年度にかけて,わが国の年間GHG排出量は,14億800万トンから12億1000万トンへ(いずれも二酸化炭素換算値),14%減少した。14%減少した年間温室効果ガス排出量をさらに60%削減するというのであるから,これは,一大事である。「2035年GHG排出19年比60%削減」という事実上の新しい国際公約は,「2013年度比」に換算すると,「66%削減」を意味する。期限が2030年から2035年へ5年間延びるとはいえ,削減比率は46%から66%へ20ポイントも上積みされるのである。
じつはわが国は,突然の「削減目標20ポイント上積み」を,過去にも経験したことがある。2021年4月に当時の菅義偉首相が,米国のジョー・バイデン大統領が主催した気候サミットにおいて,それまでの「2030年度CHG排出2013年度比26%削減」目標を,「2030年度CHG排出2013年度比46%削減」目標に転換したときが,それである。
この46%削減という目標は,従来の目標を20ポイント上方修正したものであった。日本政府は,パリ協定を採択した2015年のCOP21(The 21st Conference of the Parties to the United Nations Framework Convention on Climate Change, 国連気候変動枠組条約第21回締約国会議)で,「2030年度における国内の温室効果ガス排出量を2013年度の水準から26%削減する」という国際公約を行い,それを,2021年4月の気候変動サミット直前まで繰り返し公言していた。
当時の26%削減目標は,COP21以前の2015年に策定し,2018年の第5次エネルギー基本計画で追認した当時の電源構成見通し・一次エネルギー構成見通しと整合していた。したがって,大幅上方修正された46%削減目標が急きょ設定されたため,電源構成・一次エネルギー見通しを作り直さなければならなくなったわけであるが,その作業は難航した。
難航した直接の原因は,①まず電源構成・一次エネルギー構成見通しを決定し,②それをふまえて温室効果ガスの削減目標を国際的に宣言する,というそれまでの手順が覆されたことにある。①→②ではなく,②→①となった。2021年の第6次エネルギー基本計画の場合には,バイデン政権の圧力という政治的要因が強く作用して,まず,46%という削減目標が決まった。それを受けて,新目標と帳尻が合うように電源構成・一次エネルギー構成見通しを「調整」しなければならなくなった。このため,日本の政策当局は混乱に陥ったのである。
今回,削減目標をさらに20ポイント引き上げる新たな国際公約が登場したことにより,わが国ではエネルギー政策をめぐる混乱が繰り返されることになるだろう。世界各国は,2025年秋に開かれるCOP30までに,2035年のGHG削減目標を明示しなければならないことになっている。これに合わせて日本政府も第7次エネルギー基本計画の策定することとなるが,その作業が難航することは,火を見るより明らかである。
「2035年GHG排出19年比60%削減」という新目標の衝撃波は,政府を襲うだけではない。その影響は,地方自治体や企業にも及ぶ。
日本の多くの自治体や企業は,政府のこれまでの「2030年度CHG排出2013年度比46%削減」目標に平仄(ひょうそく)を合わせる形で,46%という数値をそのまま援用するか,若干上積みするかして,各々のカーボンニュートラルをめざす中長期計画を策定してきた。筆者が策定にかかわった二つの事例を紹介しよう。
社外取締役をつとめる出光興産が2022年に策定した中期経営計画では,「2030年度の自社操業にともなう二酸化炭素の排出量を2013年度比で46%削減する」ことを,目標として掲げている。また,策定にあたる審議会の座長をつとめた2023年発表の富山県のカーボンニュートラル戦略では,「2030年度までに温室効果ガス排出量を2013年度比で53%削減する」ことを,中期目標として挙げている。これらが,政府のこれまでの「2030年度CHG排出2013年度比46%削減」目標を意識したものであることは,言うまでもない。
このようなケースは,なにも出光興産や富山県に限られているわけではない。わが国の多くの企業や自治体が,政府の従来の「2030年度CHG排出2013年度比46%削減」目標に平仄を合わせて,各々のカーボンニュートラルをめざす中長期計画を策定している。
ところが,政府が「2035年GHG排出19年比60%削減」目標を新たに国際公約したことによって,状況は一変する。多くの企業や自治体は,カーボンニュートラルにかかわる中長期計画の目標値を大幅に引き上げざるをえなくなる。新しい国際公約の衝撃波の影響は,きわめて大きいのである。
関連記事
橘川武郎
-
[No.4221 2026.02.23 ]
-
[No.4210 2026.02.16 ]
-
[No.4179 2026.01.26 ]
最新のコラム
-
New! [No.4245 2026.03.02 ]
-
New! [No.4244 2026.03.02 ]
-
New! [No.4243 2026.03.02 ]
-
New! [No.4242 2026.03.02 ]
-
New! [No.4241 2026.03.02 ]
世界経済評論IMPACT 記事検索
おすすめの本〈 広告 〉
-
 イノベーション実現の条件
本体価格:3,200円+税 2021年3月
イノベーション実現の条件
本体価格:3,200円+税 2021年3月
文眞堂 -
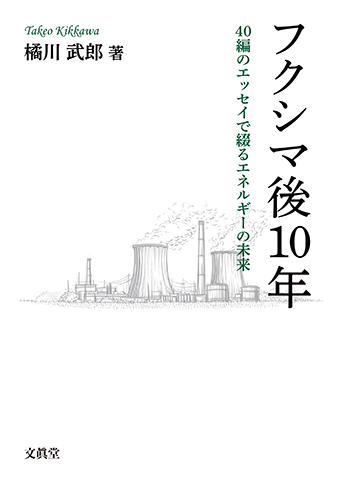 フクシマ後10年:40編のエッセイで綴るエネルギーの未来
本体価格:2,500円+税 2021年3月
フクシマ後10年:40編のエッセイで綴るエネルギーの未来
本体価格:2,500円+税 2021年3月
文眞堂 -
 応用経営史:福島第一原発事故後の電力・原子力改革への適用
本体価格:2,750円+税 2016年3月
応用経営史:福島第一原発事故後の電力・原子力改革への適用
本体価格:2,750円+税 2016年3月
文眞堂 -
 国際マーケティングの補助線
本体価格:2,700円+税 2025年9月
国際マーケティングの補助線
本体価格:2,700円+税 2025年9月
文眞堂 -
 貿易実務:新たな研究潮流
本体価格:3,500円+税 2026年1月
貿易実務:新たな研究潮流
本体価格:3,500円+税 2026年1月
文眞堂 -
 ルビーはなぜ赤いのか?:川野教授の宝石学講座
本体価格:2,500円+税
ルビーはなぜ赤いのか?:川野教授の宝石学講座
本体価格:2,500円+税
文眞堂 -
 揺らぐサムスン共和国:米中対立の狭間で苦悩する巨大財閥
本体価格:2,700円+税 2025年12月
揺らぐサムスン共和国:米中対立の狭間で苦悩する巨大財閥
本体価格:2,700円+税 2025年12月
文眞堂 -
 創造力強化経営の実践
本体価格:2,200円+税
創造力強化経営の実践
本体価格:2,200円+税
文眞堂 -
 グローバルサウス入門:「南」の論理で読み解く多極世界
本体価格:2,200円+税 2025年9月
グローバルサウス入門:「南」の論理で読み解く多極世界
本体価格:2,200円+税 2025年9月
文眞堂 -
 DEIBにおける経営倫理とCSRの役割:障害者雇用と女性、LGBT、がん患者の方々に焦点を当てて
本体価格:2,700円+税 2025年10月
DEIBにおける経営倫理とCSRの役割:障害者雇用と女性、LGBT、がん患者の方々に焦点を当てて
本体価格:2,700円+税 2025年10月
文眞堂
