世界経済評論IMPACT(世界経済評論インパクト)
日本のeメタン vs. 欧州の水素:都市ガス事業カーボンニュートラル化への二つの道
(国際大学 学長)
2025.07.21
2024年7月,オーストリアのガス関連事業所を,2ヵ所,見学する機会があった。そこで改めて確認したのは,都市ガス産業のカーボンニュートラル化を実現する方策に関する,日欧間の認識の違いである。
オーストリアのウィーンにあるウィーン・エネルジー(Wien Energie)社のドナウシュタット・プラントでは,「2040年にカーボンニュートラルを実現するという目標に向けて,積極的にエネルギー転換を進めている」旨の説明を受けた。2024年時点でウィーン・エネルジー社のCHP(熱電併給)施設は,天然ガスや石油などの化石燃料を主たる燃料としているが,2040年までに,石油だけでなく天然ガスの使用もやめる予定だと言う。代わりに活用するのは,水素,地中熱,水力,ヒートポンプ,廃棄物などだそうだ。現場での見学も,実証試験を終えたばかりの水素関連設備が中心に行われた。
ウィーン・エネルジー社が,脱天然ガスを強調するのには,特別な背景がある。それは,オーストリアを含む内陸の中欧諸国が共有する,エネルギー安全保障への強い危機感である。ウクライナ戦争の長期化により,ロシアからのパイプラインを通じた天然ガス供給の不確実性が高まるなかで,内陸国であるためLNG(液化天然ガス)という代替手段をとりにくい中欧諸国では,日本では考えられないほどエネルギー確保への危機感が高まっている。このような事情を考慮に入れれば,ウィーン・エネルジー社が短兵急の感を禁じ得ない脱天然ガスプランをあえて掲げるのも,ある程度納得がゆく。
ただし,ここで強調すべきは,中欧諸国にとどまらず,LNGという選択肢をとりうる西欧諸国も含めた欧州全体においても,水素への燃料転換が,都市ガス事業のカーボンニュートラル化の主要な方策とみなされている点である。日本の場合は,これとは違う。
日本の都市ガス事業のカーボンニュートラルをめざす施策の柱となるのは,グリーン水素ないしブルー水素と二酸化炭素(CO2)から都市ガスの主成分であるメタンを合成するメタネーションである。合成メタン(eメタン)であっても燃焼時にはCO2を排出するが,製造時にCO2を使用することによって相殺されると考え,カーボンニュートラルとみなすわけである。
メタネーションを行い水素とCO2からメタンを合成して利用することは,水素を直接使用することと比べて,エネルギーロスが大きくなる。にもかかわらず,日本の都市ガス事業がメタネーションを選択するのには理由がある。水素は,メタンに比べて,容積当たりの熱量が小さい。したがって,既存の熱需要を水素供給によって充たすためには,多大な追加投資を行って導管を大幅増設しなければならない。これを避けるため,わが国の都市ガス事業者は,水素よりも合成メタンに力を入れているのである。
一方でメタネーションの技術はいまだに開発途上にあり,eメタンは,アンモニアや水素に比べて技術面でのハードルが高い。したがって社会的実装に時間がかかるが,あまりゆっくりしていると,電化におされて肝心のガス需要そのものが縮小しかねない。ガス需要が大幅に縮小すると,水素を直接供給する方式に切り替えたとしても,大規模な導管の追加投資を行わないですむ。その場合,エネルギーロスの大小を考えれば,熱需要を満たすためにeメタンではなく水素を供給する方が,より合理的となる。これが,欧州の都市ガス業界が,水素の直接利用を志向する理由である。彼らは,カーボンニュートラル化の過程での電化の進展により,ガス需要が大幅に縮小することを見込んで,メタンが水素に切り替わっても追加的な導管投資はしないですむと判断しているのである。
欧州の都市ガス業界は,導管事業者中心に構成されている。たとえガス需要が減少しても導管の中に何かが通っていれば,事業は成り立つ。極言すれば,中身が水素であろうがeメタンであろうがかまわないのである。
対照的に日本の都市ガス業界は,小売事業者主体である。小売事業者にとって「ガス事業者としての矜持」は,電化の攻勢に抗し,ガス需要を守り抜くことにある。日本のガス事業者にとって,電化に敗れガス需要が大幅に縮小することを前提にして水素への転換を志向する欧州のガス事業者の姿勢は,「敗北主義」以外の何ものでもないだろう。
ウィーン・エネルジー社のドナウシュタット・プラントのほかに,同じオーストリアのグラーツから車で1時間ほどの距離の場所で進められているエネルギー・シュタイアーマルク(Energie Steirmark)社の「ガベルスドルフ・プロジェクト」も訪れた。このプロジェクトでは,構内にある太陽光発電装置で得られる電気を使って,水の電気分解を行い,水素を生産している。生産した水素は,メタンガスを主成分とする都市ガスに10%混入し,ガス導管を通じて供給する。2026年には,水素混入率を20%に高める予定である。
このプロジェクトの特徴は,水素の生産・供給だけでなく,メタネーションを行なってeメタンを生産・供給している点にある。近隣で栽培されているトウモロコシから作られたバイオガスを原料にして,バイオガス中のメタンガスをガス導管へ直接導く。そのうえで,バイオガス中の他の成分から二酸化炭素を分離し,構内で得られた水素と合成してeメタンを生成し,それもガス導管に注入するのである。
水素とeメタンの両方を取り扱っているとはいえ,ガベルスドルフ・プロジェクトの主眼は,あくまで水素にある。そのことは,説明にあたった同プロジェクトの関係者が,①既存のガス導管にメタンガスに替えて水素を通しても,重大な脆化の問題は生じない,②メタンガスから水素への転換によって必要となるガス機器の熱量低下への対応は,需要側の責任において遂行される,という2点を強調したことからも明らかである。
これらは,①については脆化の影響を,②については供給側の責任を,それぞれ重視する日本の都市ガス業界の見解と,明らかに異なる。事実認識に関して日欧ガス業界間に大きなギャップが存在するのであり,それがカーボンニュートラル実現策の違い(eメタンか水素か)につながっている。二つの道のどちらが正しいのか。我われは,冷静な目で見極めていかなければならない。
- 筆 者 :橘川武郎
- 地 域 :日本
- 分 野 :国際経済
- 分 野 :国内
- 分 野 :資源・エネルギー・環境
関連記事
橘川武郎
-
[No.4179 2026.01.26 ]
-
[No.4158 2026.01.12 ]
-
[No.4147 2025.12.29 ]
最新のコラム
-
New! [No.4194 2026.02.02 ]
-
New! [No.4193 2026.02.02 ]
-
New! [No.4192 2026.02.02 ]
-
New! [No.4191 2026.02.02 ]
-
New! [No.4190 2026.02.02 ]
世界経済評論IMPACT 記事検索
おすすめの本〈 広告 〉
-
 イノベーション実現の条件
本体価格:3,200円+税 2021年3月
イノベーション実現の条件
本体価格:3,200円+税 2021年3月
文眞堂 -
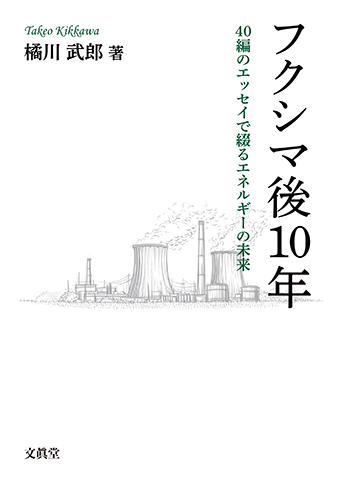 フクシマ後10年:40編のエッセイで綴るエネルギーの未来
本体価格:2,500円+税 2021年3月
フクシマ後10年:40編のエッセイで綴るエネルギーの未来
本体価格:2,500円+税 2021年3月
文眞堂 -
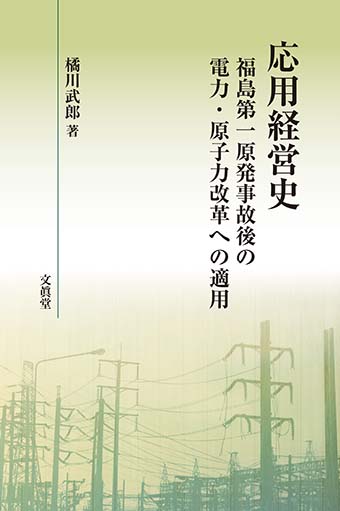 応用経営史:福島第一原発事故後の電力・原子力改革への適用
本体価格:2,750円+税 2016年3月
応用経営史:福島第一原発事故後の電力・原子力改革への適用
本体価格:2,750円+税 2016年3月
文眞堂 -
 ルビーはなぜ赤いのか?:川野教授の宝石学講座
本体価格:2,500円+税
ルビーはなぜ赤いのか?:川野教授の宝石学講座
本体価格:2,500円+税
文眞堂 -
 職場・学校のセクハラ・パワハラ :ハラスメントの法と判例
本体価格:1,300円+税 2026年1月
職場・学校のセクハラ・パワハラ :ハラスメントの法と判例
本体価格:1,300円+税 2026年1月
文眞堂 -
 高収益経営とアントレプレナーシップ:東燃中原延平・伸之の軌跡
本体価格:3,900円+税 2025年11月
高収益経営とアントレプレナーシップ:東燃中原延平・伸之の軌跡
本体価格:3,900円+税 2025年11月
文眞堂 -
 これさえ読めばすべてわかるアセットマネジメントの教科書
本体価格:2,900円+税 2025年9月
これさえ読めばすべてわかるアセットマネジメントの教科書
本体価格:2,900円+税 2025年9月
文眞堂 -
 グローバルサウス入門:「南」の論理で読み解く多極世界
本体価格:2,200円+税 2025年9月
グローバルサウス入門:「南」の論理で読み解く多極世界
本体価格:2,200円+税 2025年9月
文眞堂 -
 サービス産業の国際戦略提携:1976~2022:テキストマイニングと事例で読み解くダイナミズム
本体価格:4,000円+税 2025年8月
サービス産業の国際戦略提携:1976~2022:テキストマイニングと事例で読み解くダイナミズム
本体価格:4,000円+税 2025年8月
文眞堂 -
 ソーシャルマーケティング:行動変容で社会的価値を共創する
本体価格:3,500円+税 2025年12月
ソーシャルマーケティング:行動変容で社会的価値を共創する
本体価格:3,500円+税 2025年12月
文眞堂

