世界経済評論IMPACT(世界経済評論インパクト)
帰ってきた自然状態
(杏林大学総合政策学部 教授)
2025.11.24
私は以前,このコラムで社会契約論を国際関係に応用して論じたことがある(2018年11月19日付,No.1207)。ここでは,また別なテーマに応用してみたい。
ホッブズ(1588-1679)によれば,人は誰しも平等に自然権を与えられている。自然権とは,要するに,自らの安全と命を守るために,持てる力を思いのままに行使する権利である。しかし,各人がその自然権を思うままに行使する結果の“自然状態”は,万人の万人に対する戦争状態である。人はそのような戦争状態を回避するために,自らの自然権を放棄し,それをある特定の個人や機関に委ねる。こうしてできるのが近代主権国家である。後にスピノザ(1632-1677)は,自然権は放棄されるのではなく自制される,と論じた。私もそのほうが適合的であると感じる。
しかし,ホッブズにしてもスピノザにしても,社会契約論における“自然状態”というのは,いわば想像の産物としてのフィクションである。人類の歴史において,近代国家以前の社会がおしなべて自然状態=戦争状態であったとばかりは考えられないのではないだろうか。なるほど,それは法に基づく統治が行き渡っていたとは言えず,安定的・平和的な社会ではなかったであろう。しかし仮に近代国家の本質を社会契約という概念装置にもとめるとして,近代国家成立以前の社会というものは,どのようにして維持されていたのだろうか?私は,それを理解する鍵として「不本意な自然権の自制」という概念を提唱してみたい。
ひとたびヒトが社会的存在として生きていく過程では,すでに組織や力関係の中で一部の人はその自然権を強制的に自制させられてきたのである。小さな集団からより大きな社会組織に至るまで,子ども,女性,部下,家来,奴隷,・・・,有力なものによる支配・統治は,それに従う,ないし従わざるを得ない人々の自然権の自制を強制してきたのである。言い換えれば,万人が平等に自然権を思うままに行使していたような社会は,歴史上一度としてあったことはなく,人類は常に,一部の人々が自然権を暗黙に自制することで維持されてきたのだ。問題は,それらの自然権の自制は,常に何らかの強制に基づく,しばしば不本意なものであり続けてきたということだ。
そしてこのことは,近代国家における法に基づく統治以降の社会においてもそのまま続いている。われわれの社会は,本当に法律だけで維持されているだろうか? いや,そうではない。日常生活や社会組織における細々としたことは,最終的に法に訴えるよりはるか以前に,一部の人々による遠慮,我慢,忖度,服従といった権利の自制によって成り立っているのだ。繰り返すが,それはそれによって戦争状態を回避することに寄与するものである一方,その自然権の自制は,しばしば不本意なものであったということだ。そしてそれは,まさについこないだまでそうだったのだ。
しかし,ついに時代は大きく転換した。これまで不本意に自然権を自制させられてきた人々に,自然権がつぎつぎと帰ってきたのである。黒人,女性,性的マイノリティの人々はもちろん,家庭内における子どもであっても,組織内における部下であっても,教師に対する生徒や学生であっても,医者に対する患者であっても,そして最近ではついにクマまでも,その自然権を侵害することは,何人たりとも許されないことになった。不本意な自然権の自制を強制される人はいなくなろうとしている。
これは望ましいことであるに違いない。しかし,かくしてすべての人々の自然権が復活した社会は,まさに,ホッブズのいう自然状態なのである。そう,今まで歴史上一度も実在したことのなかった,あの自然状態が今実現しようとしているのである。そして,それは万人の万人に対する戦争状態である他はないのである。
ホッブズが指摘したように,戦争状態とは,必ずしも実際の戦闘を伴った状態ばかりではない。いつそのような暴力に巻き込まれるかに常にビクビクしながら,夜もおちおち眠れないような状態もまた戦争状態なのである。かくして今日のわれわれは,これまで聞いたことのなかったようなさまざまなハラスメント,コンプライアンス違反に囲まれ,少しでも手を伸ばせば,他の人の自然権に抵触することをただひたすら恐れて,行動と表現・言論を萎縮させ続けているのである。
自然権を社会の隅々にまで回復することは,それは定義によって良いことであり,異を唱えること自体がタブーである。しかしあえて言おう。隅々にまで権利を回復するだけではダメなのだ。万人の万人に対する戦争状態を回避するためには,なんらかの形で自然権をあらためて各自自制することが求められるのだ。もちろん不本意な強制なしに,である。
さて,どうするか? 残念ながら,答えは風に舞っている。
関連記事
西 孝
-
[No.3963 2025.08.25 ]
-
[No.3842 2025.05.26 ]
-
[No.3736 2025.02.24 ]
最新のコラム
-
[No.4149 2025.12.29 ]
-
[No.4148 2025.12.29 ]
-
[No.4147 2025.12.29 ]
-
[No.4146 2025.12.29 ]
-
[No.4145 2025.12.29 ]
世界経済評論IMPACT 記事検索
おすすめの本〈 広告 〉
-
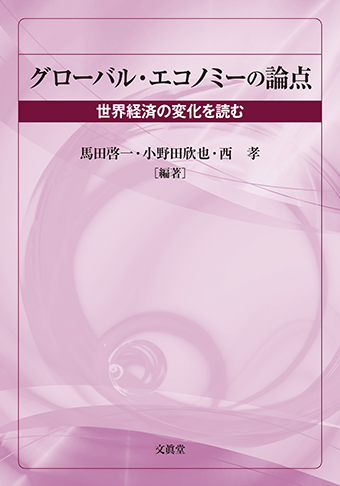 グローバル・エコノミーの論点:世界経済の変化を読む
本体価格:2,800円+税 2017年2月
グローバル・エコノミーの論点:世界経済の変化を読む
本体価格:2,800円+税 2017年2月
文眞堂 -
 国際関係の論点:グローバル・ガバナンスの視点から
本体価格:2,800円+税 2015年2月
国際関係の論点:グローバル・ガバナンスの視点から
本体価格:2,800円+税 2015年2月
文眞堂 -
 揺らぐ世界経済秩序と日本:反グローバリズムと保護主義の深層
本体価格:2,800円+税 2019年11月
揺らぐ世界経済秩序と日本:反グローバリズムと保護主義の深層
本体価格:2,800円+税 2019年11月
文眞堂 -
 ルビーはなぜ赤いのか?:川野教授の宝石学講座
本体価格:2,500円+税
ルビーはなぜ赤いのか?:川野教授の宝石学講座
本体価格:2,500円+税
文眞堂 -
 これさえ読めばすべてわかるアセットマネジメントの教科書
本体価格:2,900円+税 2025年9月
これさえ読めばすべてわかるアセットマネジメントの教科書
本体価格:2,900円+税 2025年9月
文眞堂 -
 DEIBにおける経営倫理とCSRの役割:障害者雇用と女性、LGBT、がん患者の方々に焦点を当てて
本体価格:2,700円+税 2025年10月
DEIBにおける経営倫理とCSRの役割:障害者雇用と女性、LGBT、がん患者の方々に焦点を当てて
本体価格:2,700円+税 2025年10月
文眞堂 -
 サービス産業の国際戦略提携:1976~2022:テキストマイニングと事例で読み解くダイナミズム
本体価格:4,000円+税 2025年8月
サービス産業の国際戦略提携:1976~2022:テキストマイニングと事例で読み解くダイナミズム
本体価格:4,000円+税 2025年8月
文眞堂 -
 揺らぐサムスン共和国:米中対立の狭間で苦悩する巨大財閥
本体価格:2,700円+税 2025年12月
揺らぐサムスン共和国:米中対立の狭間で苦悩する巨大財閥
本体価格:2,700円+税 2025年12月
文眞堂 -
 グローバルサウス入門:「南」の論理で読み解く多極世界
本体価格:2,200円+税 2025年9月
グローバルサウス入門:「南」の論理で読み解く多極世界
本体価格:2,200円+税 2025年9月
文眞堂

