世界経済評論IMPACT(世界経済評論インパクト)
多国籍企業経営の「内部化」現象:MAGAの裏側に生じた米国の没落の背景
(国際貿易投資研究所(ITI)客員 研究員・元帝京大学経済学部大学院 教授)
2025.05.05
「歴史の終り」(F.フクヤマ)の後,資本主義経済に染まった世界市場のグローバル化は,ますます寡占的巨大企業の調整と裁量に大きく依存するようになった。このことは企業論理の市場に対する支配・従属関係の構築,ヒエラルキー上の勝利を意味していた。しかし,市場の内容が変質した。その現象は国境を越えて3つの次元で観察されるようになった。すなわち,国際企業経営の内部化,外部化,アライアンス(提携)である。国家の存在は「異端」であるかのようにも見えてきた。
聖書で「はじめに言葉ありき」と言うが,国際貿易論のはじめとして長い間,所与の条件,前提とみなされていた国家の存在そのものに関する位置付けの問いかけがある。なぜなら国家というのは本来,経済分析の概念ではなく,政治,歴史,文化,習慣,言語などの同一性からなる空間だからである。国家の存在は,経済分析が通常,均質的な空間でなされるという意味において,空間配置の上でまさに「異端」の要素であると言わなければならない。また,国家は国境を通じて人間関係の断絶の源になっている。一般的にビジネスが成立するためには2人以上が違った経済資源の要素条件を持ち合わせていなければならない。古典派経済学では資本家と労働者であり,また新古典派では生産者と消費者である。そして国家はこれらの経済人の集まりの間を引きつなぐ貿易関係を認知するための単位と言える。こうしたことから国家はこれらの資源を手にする企業にもたとえられる。
国際貿易論を最初に唱えたアダム・スミス(Adam Smith)は「安価な製品の生産国はそれを輸出できる」という絶対優位を主張した。しかしこれは絶対優位を有さない国は国際貿易に参加できないという現実とは矛盾した結論になる。デビッド・リカード(David Ricard)が比較優位を通じて貿易上の差別化が可能であることを証明した。労働と資本の自由移動は経営資源の競争優位を構築することが可能になった。多くの国が同一商品や類似商品を互いに輸出入している。グローバル化は企業活動を一挙に多国籍化の経営戦略の方向に加速した世界貿易は次の2つの大きな特徴を持っている。ひとつは北米,欧州,東アジアの3極間貿易が輸出入とも70%以上を占めて,なおかつ3極内の域内貿易統合が進展していること,もうひとつは多国籍企業の直接投資が貿易構造を変化させつつあることであった。この2つの事実は国際貿易論を著しく産業経済論,企業経営論に接近させることとなる。これらの理論的な再構築は,技術革新,規模の経済,差別化,需要補完性,寡占など様々な角度から試みられている。そして,ここ20年余りの間に収穫逓減と完全競争の2つの伝統的な定理は,まさに収穫逓増と不完全競争の概念に取って代わられていた。
収穫逓減の法則は古典派国際貿易理論の前提であった。リカード(Ricard)は,生産性技術格差,HO(Heckscher-Ohlin model)理論において生産要素賦存比率の違いによって国際分業が成立するとしていた。これらの理論では経済空間の規模が国際貿易に影響を与えることはなかった。収穫逓増の概念はすでに1879年にアルフレッド・マーシャル(Alfred Marshal)が『産業経済学』のなかで言及している。マーシャルは企業内部と企業外部の2種類の規模の経済を想定している。労働(L)と資本(K)で構成される生産関数において,例えば5%の投入生産要素の増加があった時に,8%の生産量の増加が実現されるように,規模の増大が収穫逓増につながる関係である。
1960年代以降,米国企業に顕著に見られた海外直接投資は,その後,英国企業にも見られるようになったが,70年代後半には欧州企業,80年代には日本企業,そして90年代には中国,香港,韓国,シンガポール,メキシコ,ブラジルなどの新興工業諸国の企業もこれに加わった。このように企業の多国籍化が世界的な傾向になってくると,従来の生産性格差に代わって世界市場における市場シェアを制覇することが第一義的な課題となった。ここでは企業競争力の概念が鍵を握っており,これまでの貿易収支の均衡に代わって製品の世界市場シェアの拡大が国際経済の重要テーマとなった。さらに多国籍企業の全体の数が増加する中で,いわゆる一国企業というのはどの国でも,どの産業分野でも減少している。このことは,どの製品分野やサービス部門でも少数の企業が世界生産を支配しているということを意味しているのである。自動車,石油,アルミニウム,化学,清涼飲料,大規模小売流通,家電などの事例を見れば歴然としている。言葉を換えて言えば,世界市場における競争とは実は寡占的競争のことであったのである。それぞれの産業セクターの供給はごく少数の企業によって占められており,世界市場は不完全競争である。フランスのパリ大学教授C.Aミシャレ(Charles-Albert Michalet)によればこのような世界的な寡占競争の不完全市場では,次の2つの点が明らかとなってくる。ひとつは企業の生産拠点の海外移転であり,もうひとつは多国籍企業経営のあり方の変化である。寡占競争における企業の海外立地のあり方という点について,ミシャレは次の5点をその理由として挙げた。
第1に輸出に代替する販路開拓として海外直接投資が選択されるが,その重要な基準は進出先の市場が十分に大きく,また市場の成長率が高いことである。この場合,進出先の国の市場規模ということよりも,進出先の近隣諸国を含めた地域全体への市場アクセスが可能であるかどうかが判断基準となる。ポルトガルやアイルランドのような市場規模の小さい国が外国からの投資の誘致に成功しているのは,経済統合した欧州単一市場へのアクセスが可能だからである。また同様にメキシコやカナダに進出することによって旧北米自由貿易協定(NAFTA)全体の経済統合効果にあやかれるからであった。
第2に生産活動を海外に移転することによってコスト上の国際競争力を強化することができる。労働力,原材料,エネルギー,輸送,租税などを自国よりも安いコストで調達すること,いわゆるアウトソーシングを海外のよりコストの安いところに構えることで世界各地の生産工程の最適配置が考えられる。
第3に寡占的競争のあり方が企業の海外投資の決定に重要な影響を及ぼす。寡占企業理論によれば,それぞれの企業は自分の企業の決定に対するライバル企業の反応をあらかじめ予期した上で,自らの決定を下すようになる。市場の均衡を最終的に決めるのは「見えざる手」の結果ではなく,限られた数の企業の間でなされる戦略的な決定のぶつかり合いである。価格水準を決めるのは需給曲線ではなくゲームの理論である。ここではリーダー企業がある国に進出を決めると,ライバル競争関係にある企業も市場シェアの喪失を恐れて海外進出するようになる。
第4に価格競争のみではライバル企業もすぐに追随してくるような寡占競争下では,企業の成長はなかなか望めない。そこでは企業の成長戦略は,新製品開発か既存の製品差別化政策ということになる。しかしこれもすぐにフォロワー・ライバル企業がこれにならって同じような戦略を採択して競争優位は瞬く間になくなってしまう。最後に残る選択肢は,事業の多角化か海外進出して多国籍化するかである。
第5に寡占状態の企業競争では「囚人のジレンマ」と呼ばれるライバル企業間の相互抑止力が作用して,例えば欧米企業の間では双方の市場に相互に同じような業種の直接投資がなされていることが多い。これは互いに企業が相手方と対抗しようとすることによって相手の意図,出鼻を挫くことで市場シェアを確保しようとする行動に出ることを意味している。この分析は,通常ではゼロサム・ゲームで市場がかなり飽和していると言われる先進諸国間,とくに米欧日の3極間の相互直接投資の現象を説明するのに説得力があった。
R.コース(Ronald H. Coase)が1937年に発表した取引コスト論の核心部分である企業の経営業務の内部化という概念は,80年代初期の企業の多国籍化によって脚光を浴びるようになった。取引コスト論は実際,市場が不完全であり,情報が非対称的であり,また不誠実な取引パートナーが存在したりするなど,経済活動が不確実で不安定な状況にあることの認識から出発している。国際取引となってくるとさらに,地理的空間的距離,言語・文化の差異,為替レート,政治制度など危険で不安定なビジネス取引コストを覚悟しなければならない。コースはこれら外部の不安定コスト要因を内部化することを提案するのである。企業活動の上流・下流,国内・海外などを問わず,また海外事業活動の多い企業では経営権買収,子会社設立などによって企業の内側に市場の内部化構造をビルトインすることである。問題は現代の多国籍企業のように5つの大陸にわたり数十カ国で数百の子会社を有するような組織体では,このような要請に応えるのは簡単ではないということである。これまでの伝統的な機能別組織では,国際事業部が結局は他の部の人事,財務,生産,マーケティングなどの部局機能をも統合しようとして本国の本社内での部局間対立を招いたり,海外子会社ではこの国際事業部の軍事主義的でヒエラルキー的なやり方に対する反目が高まっていく。
このような本社内部と海外子会社とにおいて発生する二重の危機に直面して企業の国際的な経営組織は,グローバル・モデルと呼ばれる新たな組織構造を導入することになる。北米,欧州,アジアというような世界の市場別,あるいは製品別の組織編成,さらにはこの両者を合わせた市場と製品の両方を取り入れたマトリックス組織が取り入れられる。このような企業の組織体制では権限が子会社に大幅に移譲されることが多い。一方,本社の中心的な機能は,企画戦略,財務,研究開発など企業の国際競争力の核心にかかわる部分に移行していく。
このような新たなグローバル多国籍企業による商品,サービス,資本,労働力などの企業内部におけるかかえこみ現象は,次の3点で国際貿易を変容させた。
①多国籍企業の海外での売上高全体がその企業の属する国の輸出全体を上回るようになってきたことである。つまり海外子会社の進出先国での売上高とそこからの第3国輸出を合計した額である。1971年以降,慢性的になってきた米国の経常収支の赤字はしばしば,米国経済の衰退,その国際競争力の構造的な喪失と解釈されているが,ジュリウス(D.Jullius)のように,もし米国輸出に現地海外子会社の売上高を加えれば米国の広義の意味での貿易収支は赤字でなく黒字となる。従って貿易収支である国の競争力を論じるのは正鵠を射ていないとする。
②世界貿易の構造と性格が変質したことである。既述のとおり世界貿易の70%以上は北米,欧州,東アジアの3極間貿易で占められているが,今やその内の40%以上は企業内貿易によって成り立っている。このことは,換言すれば多国籍企業の構築する国際的な内部取引の及ぼすグローバルな経済空間の中における「内部化」された財貨・サービスの同一企業内国際移動と言うことができる。
③国際貿易の特化分業のあり方はもう従来のように各国の生産要素の賦存条件によるのではなく,逆に企業の戦略的な必要性に基づいてこれまで国際的な移動はないとされていた生産要素の最適配置が決定される。投資環境の優劣を決めるのは,企業が立地条件を十分に競争優位があると判断した時である。企業の投資がその戦略に基づいて最適立地を決めることは,言わばあたかもアダム・スミスの絶対優位の概念に近づくものと言える。
こういう新たな事態の中で各国の政策当局の対外経済政策の重点は,国際収支の均衡ではなくなった。とくに輸出入の動向は政府にとり第二義的になってしまった。国際投資の流出入のフローの帰趨が最優先の政策課題となったのである。
関連記事
瀬藤澄彦
-
[No.4151 2026.01.12 ]
-
[No.4139 2025.12.22 ]
-
[No.4092 2025.11.24 ]
最新のコラム
-
New! [No.4178 2026.01.19 ]
-
New! [No.4177 2026.01.19 ]
-
New! [No.4176 2026.01.19 ]
-
New! [No.4175 2026.01.19 ]
-
New! [No.4174 2026.01.19 ]
世界経済評論IMPACT 記事検索
おすすめの本〈 広告 〉
-
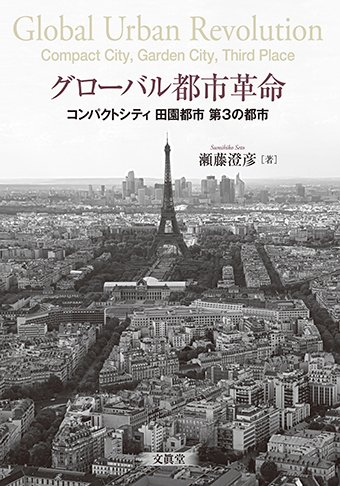 グローバル都市革命:コンパクトシティ 田園都市 第3の都市
本体価格:3,500円+税 2022年11月
グローバル都市革命:コンパクトシティ 田園都市 第3の都市
本体価格:3,500円+税 2022年11月
文眞堂 -
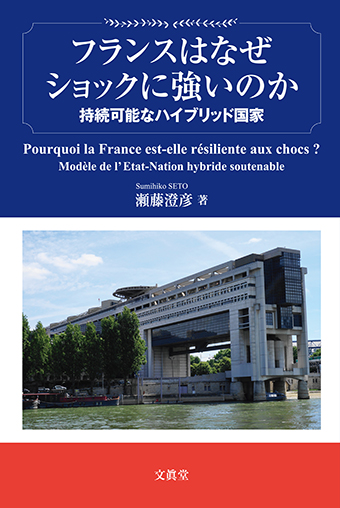 フランスはなぜショックに強いのか:持続可能なハイブリッド国家
本体価格:2,500円+税 2017年6月
フランスはなぜショックに強いのか:持続可能なハイブリッド国家
本体価格:2,500円+税 2017年6月
文眞堂 -
 これさえ読めばすべてわかるアセットマネジメントの教科書
本体価格:2,900円+税 2025年9月
これさえ読めばすべてわかるアセットマネジメントの教科書
本体価格:2,900円+税 2025年9月
文眞堂 -
 サービス産業の国際戦略提携:1976~2022:テキストマイニングと事例で読み解くダイナミズム
本体価格:4,000円+税 2025年8月
サービス産業の国際戦略提携:1976~2022:テキストマイニングと事例で読み解くダイナミズム
本体価格:4,000円+税 2025年8月
文眞堂 -
 ルビーはなぜ赤いのか?:川野教授の宝石学講座
本体価格:2,500円+税
ルビーはなぜ赤いのか?:川野教授の宝石学講座
本体価格:2,500円+税
文眞堂 -
 中国鉄鋼業:生産システム,企業,産業の三層構造と産業政策
本体価格:4,000円+税 2025年8月
中国鉄鋼業:生産システム,企業,産業の三層構造と産業政策
本体価格:4,000円+税 2025年8月
文眞堂 -
 高収益経営とアントレプレナーシップ:東燃中原延平・伸之の軌跡
本体価格:3,900円+税 2025年11月
高収益経営とアントレプレナーシップ:東燃中原延平・伸之の軌跡
本体価格:3,900円+税 2025年11月
文眞堂 -
 グローバルサウス入門:「南」の論理で読み解く多極世界
本体価格:2,200円+税 2025年9月
グローバルサウス入門:「南」の論理で読み解く多極世界
本体価格:2,200円+税 2025年9月
文眞堂 -
 揺らぐサムスン共和国:米中対立の狭間で苦悩する巨大財閥
本体価格:2,700円+税 2025年12月
揺らぐサムスン共和国:米中対立の狭間で苦悩する巨大財閥
本体価格:2,700円+税 2025年12月
文眞堂 -
 職場・学校のセクハラ・パワハラ :ハラスメントの法と判例
本体価格:1,300円+税 2026年1月
職場・学校のセクハラ・パワハラ :ハラスメントの法と判例
本体価格:1,300円+税 2026年1月
文眞堂

