世界経済評論IMPACT(世界経済評論インパクト)
貧困線の設定は政治的地雷原?
(青山学院大学経済学部 教授)
2016.03.07
格差問題と貧困問題はしばしば同次元の問題として語られることが多いが,皆さんはこの2つの問題をどう捉えているだろうか。餓死レベルの貧困をほぼ撲滅し,かつては「1億総中流」などと言われた日本だが,長い不況を経て右肩上がりの経済でなくなってしまったため,多くの人は「隣人との差」に対してより敏感になっているのかもしれない。所得の上昇とともに幸福感や生活満足度が必ずしも上昇しない現象はイースタリン・パラドックスとして知られているが,だからといって,主観要素の大きい生活満足度と,公共政策として撲滅を目指す貧困を混同して議論すべきではないだろう。
日本において絶対基準に基づく貧困測定は存在しない。「ワーキングプア」にも厳密な定義はない。生活保護世帯の支給額を基準にすることもあるだろうが,この基準も中位世帯の消費水準のほぼ6割というような相対的基準のようだ。実際,この生活保護水準を1日・1人あたりにすると,国際貧困線として広く利用されている1日1人当たり1ドル(1985年価格)もしくは1.25ドル(2005年価格)の少なくとも数倍以上に相当しそうだ。
途上国一般に適用されている貧困線は,単純化すると,その国の典型的な貧困家計が生きていくのに最低限必要な食料をぎりぎり購入できる所得水準の家計の,衣・住など生活必需品への支出額を加えた支出総額として「絶対的」貧困線を算出する。世界銀行がこのように定義される世界の貧困国の貧困線を購買力平価でドル換算し,平均的な金額を求めた結果が上記の「国際」貧困線である。
一方,先進国の集まりであるOECD(経済開発協力機構)が定義する貧困線は「その国の中位所得の世帯の半分の金額」という「相対的」貧困線を適用し,国際比較をしている。この指標は貧困指標というよりも不平等指標だと筆者は考える。国民の平均的な生活水準が快適レベルに達した先進国において格差問題が注目を浴びやすいのは仕方ないことかもしれないが,途上国と先進国を区別して,概念が異なる貧困線の定義を併用することに筆者は違和感を覚える。OECDの基準(現在の日本の1人当たり中位所得の半額は年120万円程度で,ちょうど単身の生活保護世帯くらいだろうか)では,日本の貧困者比率は15%程度で,OECD諸国約30カ国のなかで,アメリカに次ぐ貧困大国だということになってしまう。そういう貧困線に日本国民が納得し,それ以下の人々が存在してはいけないという国民的コンセンサスが得られていれば,それでもいいのかもしれないが,そうした議論が正面からなされていないように思う。筆者としては以下の諸点で,相対的貧困線はとても怪しいと思っている。
- ・国全体が豊かになって絶対的貧困を撲滅できたとしても,相対的貧困は永遠に撲滅不可能である。
- ・所得水準が異なる国の間で相対的貧困率を比較して,A国はB国より貧困度が深刻あるいは軽いといった解釈はできないはずである。
- ・不平等指標としてさえもうまく機能しない可能性が高い。例えばA国の所得分布[5,5,5,8,20,40,60]では貧困線は中位所得の半額なので4であるから貧困率は0%であるのに対し,B国の所得分布[10,10,20,30,40,40,60]では貧困線は15であるから貧困率は29%になってしまう。
家計調査や貧困分析の権威で2015年のノーベル経済学賞を受賞したアンガス・ディートンの著作『大脱出:健康,お金,格差の起源』(2013, pp.197−203)には,アメリカの貧困線について以下の興味深い紹介がある。
1960年代前半,社会保障庁の依頼を受けた経済学者モリー・オーシャンスキーがアメリカの貧困線を最初に設定した。成人2人と子供2人から成る4人家族がぎりぎり生きていくために必要な食費を計算し,一般的な家計では所得の約3分の1を食費に充てるという前提に基づいて,その食費を3倍した結果,1963年価格で年間所得3,165米ドルを貧困線として提示した。1969年,この数字が正式にアメリカの貧困線として定められた。その後,物価の上昇に価格調整を除き,この実質貧困線価格が維持されたという。オーシャンスキーが最初に行った計算は農務省の低価格食糧購入計画に基づいて4000ドル強の金額を算出したが,もっと厳しい経済的食糧計画の基準では3000ドルに近かったことと,ギャラップ社の世論調査で貧困線はいくらにすべきかという質問に対し,平均的な回答が3000ドルだったことから,この3,165ドルが採用されたということだ。かなり恣意的なプロセスだが,貧困層に対する所得移転政策を国民に受け入れてもらうためには,世論調査の結果を馬鹿にはできないとディートンは解説する。現代の日本でも,貧困度を議論するなら,せめてこの程度のプロセスを経る必要があろう。
ただし,ディートンの説明に筆者が違和感を覚えるのは以下のくだりである。「人間が生きていくために必要な物品の内訳がきっちり定義されていれば,絶対的貧困は理にかなっている……この手法はアフリカや南アジアなどの貧困国では理にかなっているかもしれないが,……アメリカにおける貧困の現実は,社会に本格的に参画するために必要な財源が十分にないことと,家族とその子供たちが隣人や友人に囲まれて人並みの暮らしを送れる状況にないことが問題だ。人並みに生活するという社会水準を満たせていない状態は絶対的貧困だが,この絶対的貧困を避けるためには,現地の水準に合わせた調整が必要だという点で相対的な金額が必要になる。アメリカのように裕福な国では,相対的な貧困以外は妥当とは考えられない……一般的な生活水準が上がっている世界で絶対的貧困線を採用すると,貧困層が社会の主流からどんどん低い位置へと流れ落ちてしまう」(p.200)
ディートンにしてさえ,貧困の定義に相対基準を持ち込み,先進国の貧困と途上国の貧困に異なる定義を適用してもよいと考えているらしい。さらに自身が世界の貧困について語る個所では「世界の貧困は国際的な概念であって,その測定も国際的基準でおこなわれるべきだ」(p.268)と述べていることと矛盾する。
結局のところ,以下のディートンのくだりに,一貫した科学的根拠に基づいた貧困線を設定するのは困難だという諦観が表れている。「貧困線をどう更新していくかという問題は難しい。これは1つには哲学的・政治的思想の違いがあるためだが,もう1つには貧困線の定義を変えることで,貧困対策の恩恵を受ける対象も変わることになり,そうなると得をするものと損をする者が出てくるためでもある。貧困の計測方法を変えると……政治的な反対運動が起こるのは間違いない。貧困に関する統計は国家が統治するための道具の1つだ……測定がなければ統治が難しいのと同様に,政治がなければ測定は存在しない。Statistics(統計)という単語にStat(国家)という言葉が含まれているのは偶然ではないのだ」(p.203)。
関連記事
藤村 学
-
New! [No.4230 2026.02.23 ]
-
[No.4119 2025.12.08 ]
-
[No.3862 2025.06.09 ]
最新のコラム
-
New! [No.4232 2026.02.23 ]
-
New! [No.4231 2026.02.23 ]
-
New! [No.4230 2026.02.23 ]
-
New! [No.4229 2026.02.23 ]
-
New! [No.4228 2026.02.23 ]
世界経済評論IMPACT 記事検索
おすすめの本〈 広告 〉
-
 ASEAN経済新時代 高まる中国の影響力
本体価格:3,500円+税 2025年1月
ASEAN経済新時代 高まる中国の影響力
本体価格:3,500円+税 2025年1月
文眞堂 -
 アウンサンスーチー政権下のミャンマー経済:最後のフロンティアの成長戦略
本体価格:3,200円+税 2019年12月
アウンサンスーチー政権下のミャンマー経済:最後のフロンティアの成長戦略
本体価格:3,200円+税 2019年12月
文眞堂 -
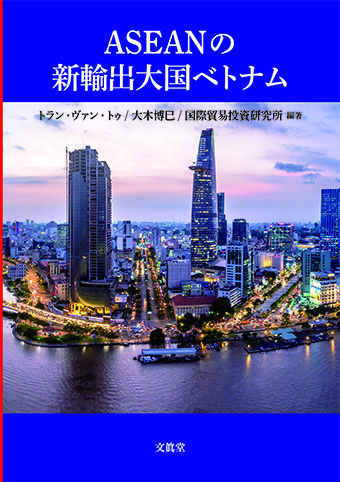 ASEANの新輸出大国ベトナム
本体価格:3,000円+税 2018年12月
ASEANの新輸出大国ベトナム
本体価格:3,000円+税 2018年12月
文眞堂 -
 ルビーはなぜ赤いのか?:川野教授の宝石学講座
本体価格:2,500円+税
ルビーはなぜ赤いのか?:川野教授の宝石学講座
本体価格:2,500円+税
文眞堂 -
 国際マーケティングの補助線
本体価格:2,700円+税 2025年9月
国際マーケティングの補助線
本体価格:2,700円+税 2025年9月
文眞堂 -
 これさえ読めばすべてわかるアセットマネジメントの教科書
本体価格:2,900円+税 2025年9月
これさえ読めばすべてわかるアセットマネジメントの教科書
本体価格:2,900円+税 2025年9月
文眞堂 -
 グローバルミドルリーダー行動の探究:日本的経営の海外移転を担う戦略的役割
本体価格:3,900円+税 2026年1月
グローバルミドルリーダー行動の探究:日本的経営の海外移転を担う戦略的役割
本体価格:3,900円+税 2026年1月
文眞堂 -
 創造力強化経営の実践
本体価格:2,200円+税
創造力強化経営の実践
本体価格:2,200円+税
文眞堂 -
 揺らぐサムスン共和国:米中対立の狭間で苦悩する巨大財閥
本体価格:2,700円+税 2025年12月
揺らぐサムスン共和国:米中対立の狭間で苦悩する巨大財閥
本体価格:2,700円+税 2025年12月
文眞堂 -
 高収益経営とアントレプレナーシップ:東燃中原延平・伸之の軌跡
本体価格:3,900円+税 2025年11月
高収益経営とアントレプレナーシップ:東燃中原延平・伸之の軌跡
本体価格:3,900円+税 2025年11月
文眞堂
