世界経済評論IMPACT(世界経済評論インパクト)
日本ガス協会の「新2050年ビジョン」:天然ガス使用継続へ大胆な方針転換
(国際大学 学長)
2025.11.24
日本ガス協会は,2025年6月3日,新しい長期ビジョンとして,「ガスビジョン2050」(以下,「新ビジョン」と表記)を公表した。同協会は,2020年11月に長期ビジョン「カーボンニュートラルチャレンジ2050」(以下,「旧ビジョン」と表記)を発表しているが,今回の新ビジョンは,旧ビジョンを改訂したものではなく,新たに策定したものという位置づけである。
日本ガス協会は,新ビジョンのなかで,都市ガスの安定供給とカーボンニュートラル化に並行して取り組むとし,「災害に屈しない社会・産業・地域の構築に尽力する」,「お客様に選ばれ続けるソリューションを提供する」,「お客様・地域のカーボンニュートラル化実現に貢献する」という,三つの柱を掲げる。そして,都市ガス事業者は,地域社会や需要家にとって,①信頼されるプロフェッショナル,②お客様・地域に寄り添うパートナー,③発展を支えるイノベーター,になると宣言している。
しかし,今回の新ビジョンで最も注目を集めたのは,これらの定性的な記述ではなく,2050年のカーボンニュートラル実現時点における都市ガス供給の内訳を示した定量的な記述である。そこでは,旧ビジョンではeメタン(水素ないしグリーン電力と二酸化炭素とから生成する合成メタン)90%,水素直接利用5%,バイオガス等5%とされていた内訳が,eメタンとバイオガスで50〜90%,天然ガスとCCUS(二酸化炭素回収・利用,貯留)やクレジット等との組み合わせで10〜50%という内訳へ,大幅に変更された。別言すれば,旧ビジョンではカーボンニュートラル実現後は天然ガスを使わないとしていたものを,新ビジョンではカーボンニュートラル実現後も天然ガスを最大50%まで使い続けると,大胆に方針転換したわけである。
なぜ,日本ガス協会は,このタイミングで大胆な方針転換を打ち出したのか。その背景に,今年2月18日に閣議決定された第7次エネルギー基本計画(以下,「第7次エネ基」と表記)が提示した天然ガス政策の変更が存在することは,容易に想像がつく。
第7次エネ基は,「天然ガスはカーボンニュートラルの実現後も重要なエネルギー源である」と明記した。それまでは,日本ガス協会が発表した旧ビジョンにおいても,経済産業省「『トランジションファイナンス』に関するガス分野における技術ロードマップ」(2022年2月)のような政府の公式文書においても,カーボンニュートラルが実現した暁には,化石燃料である天然ガスは使われなくなるという見通しが示されていた。ところが,第7次エネ基はこの見通しを真っ向から否定し,天然ガスはカーボンニュートラル実現後も使い続けられるとした。それは,天然ガス政策の根本的な変更を意味するものだったのである。
日本ガス協会の新ビジョンは,旧ビジョンに比べて,二つの点で改善されている。
第1は,都市ガス業界のカーボンニュートラルへの道筋が,より現実的になったことである。旧ビジョンは,都市ガス業界のカーボンニュートラル化は,主としてeメタン(合成メタン)によって達成されると考えていた。これと平仄を合わせる形で,2021年10月に閣議決定された第6次エネルギー基本計画では,「2030年には,既存インフラへ合成メタンを1%注入し,その他の手段と合わせてガスの5%をカーボンニュートラル化するとともに,2050年には合成メタンを90%注入し,その他の手段と合わせてガスのカーボンニュートラル化を目指す」,と記されていた。そして,この「2030年までに合成メタン1%混入」について,大手都市ガス会社は,ハードルが高いと盛んに表明してきた。そのような状況のもとでは,「2030年に1%混入することが容易でないeメタンを,本当に2050年までに90%も導入することができるのか」という疑問が,根強く存在した。その疑問は,「旧ビジョン自体が非現実的ではないか」という疑問へとつながっていたのである。
しかし,新ビジョンは,2050年の都市ガス供給内訳においてeメタンの比率が大幅に下がる可能性を示し,さらにはeメタンとともにバイオガスの導入にも力を入れる方針も示した。新ビジョンの現実性は,旧ビジョンのそれより向上したと言える。
第2は,都市ガス業界におけるカーボンニュートラル化の担い手を拡大したことである。
事実上,「eメタンの一本足打法」だった旧ビジョンのもとでは,日本に存在する193の都市ガス事業者のうちカーボンニュートラル化の担い手になりうるのは,東京ガス・大阪ガス・東邦ガスの3社に限定されていた。eメタンの開発には,膨大な資金と人的資源を必要とするからである。残りの事業者は,じっと3社の開発の進展を待つしかなかったのである。
ところが,新ビジョンは,都市ガスのカーボンニュートラル化の過程で,eメタンだけでなくバイオガスやクレジットも重要な役割を果たすことを明らかにした。また,新ビジョンは,地域貢献の大切さも強調した。そうなれば,大手3社以外の他の都市ガス事業者にも出番が生じる。現在,バイオガス活用の点で全国の先頭を走るのは,鹿児島市に本社を置く日本ガスである。スマートコミュニティづくりの中心となり地域貢献に励む都市ガス会社も,神奈川県の小田原ガスなど,少なからず存在する。新ビジョンは,都市ガス業界において自分事としてカーボンニュートラルに取り組む事業者の幅を広げたのである。
一方で,新ビジョンに問題がないわけではない。
一つは,新ビジョンで新たに重要視されたバイオガス,クレジット,CCUS等の社会実装の道筋について,具体的な展望が示されていないことである。この問題点は,日本都市ガス協会の新ビジョンのみならず,政府の第7次エネ基にも,共通するものである。eメタン,バイオガス,クレジット,CCUS等の社会実装の道筋を具体的な形で明示しない限り,都市ガス産業のカーボンニュートラル化に関するロードマップを提示したことにはならないのである。
いま一つは,2050年のカーボンニュートラル実現時点での都市ガス供給においてeメタンとバイオガスが50〜90%を占めるという見通しは,あまりにも幅が広すぎることである。しかも,日本ガス協会は,今後の環境変化に合わせてこの新ビジョンを随時変更するとも言っている。そもそも業界団体が長期ビジョンを策定する目的の一つは,将来の見取り図を明確に示し,関係事業者の投資判断に有用な目安を提供することにある。あまりに幅が広く,可変性が高いビジョンでは,投資判断の目安を提供する役割をはたせないことになる。
- 筆 者 :橘川武郎
- 地 域 :日本
- 分 野 :国際ビジネス
- 分 野 :国内
- 分 野 :資源・エネルギー・環境
関連記事
橘川武郎
-
[No.4147 2025.12.29 ]
-
[No.4122 2025.12.15 ]
-
[No.4103 2025.12.01 ]
最新のコラム
-
[No.4149 2025.12.29 ]
-
[No.4148 2025.12.29 ]
-
[No.4147 2025.12.29 ]
-
[No.4146 2025.12.29 ]
-
[No.4145 2025.12.29 ]
世界経済評論IMPACT 記事検索
おすすめの本〈 広告 〉
-
 イノベーション実現の条件
本体価格:3,200円+税 2021年3月
イノベーション実現の条件
本体価格:3,200円+税 2021年3月
文眞堂 -
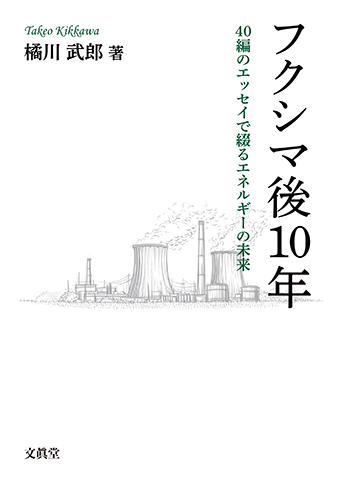 フクシマ後10年:40編のエッセイで綴るエネルギーの未来
本体価格:2,500円+税 2021年3月
フクシマ後10年:40編のエッセイで綴るエネルギーの未来
本体価格:2,500円+税 2021年3月
文眞堂 -
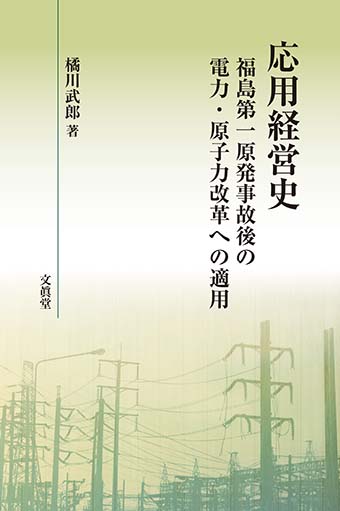 応用経営史:福島第一原発事故後の電力・原子力改革への適用
本体価格:2,750円+税 2016年3月
応用経営史:福島第一原発事故後の電力・原子力改革への適用
本体価格:2,750円+税 2016年3月
文眞堂 -
 中国鉄鋼業:生産システム,企業,産業の三層構造と産業政策
本体価格:4,000円+税 2025年8月
中国鉄鋼業:生産システム,企業,産業の三層構造と産業政策
本体価格:4,000円+税 2025年8月
文眞堂 -
 これさえ読めばすべてわかるアセットマネジメントの教科書
本体価格:2,900円+税 2025年9月
これさえ読めばすべてわかるアセットマネジメントの教科書
本体価格:2,900円+税 2025年9月
文眞堂 -
 グローバルサウス入門:「南」の論理で読み解く多極世界
本体価格:2,200円+税 2025年9月
グローバルサウス入門:「南」の論理で読み解く多極世界
本体価格:2,200円+税 2025年9月
文眞堂 -
 DEIBにおける経営倫理とCSRの役割:障害者雇用と女性、LGBT、がん患者の方々に焦点を当てて
本体価格:2,700円+税 2025年10月
DEIBにおける経営倫理とCSRの役割:障害者雇用と女性、LGBT、がん患者の方々に焦点を当てて
本体価格:2,700円+税 2025年10月
文眞堂 -
 高収益経営とアントレプレナーシップ:東燃中原延平・伸之の軌跡
本体価格:3,900円+税 2025年11月
高収益経営とアントレプレナーシップ:東燃中原延平・伸之の軌跡
本体価格:3,900円+税 2025年11月
文眞堂 -
 揺らぐサムスン共和国:米中対立の狭間で苦悩する巨大財閥
本体価格:2,700円+税 2025年12月
揺らぐサムスン共和国:米中対立の狭間で苦悩する巨大財閥
本体価格:2,700円+税 2025年12月
文眞堂

