世界経済評論IMPACT(世界経済評論インパクト)
日本を追い抜くフィンランドのメタネーション
(国際大学 学長)
2025.10.20
2025年8月,(株)ガスエネルギー新聞が主催した欧州視察ツアーに参加して,フィンランドを訪問した。具体的な訪問先は,ヘルシンキのノルディックレンガス(Nordic Ren Gas,以下「レンガス」と表記)社とエスポーのガスム(Gasum)社,ラホヤのガスム社のバイオガスプラント,およびエスポーのVTTフィンランド技術研究センター(以下「VTT」と表記)である。
レンガスは,水素と二酸化炭素(CO2)からeメタンを製造するメタネーションの準備を着々と進めていた。まずタンペレで,2028年に360GWh/年のeメタンを作るという。続いてラハティで,同じく360GWh/年のeメタンの製造をめざす。このラハティ・プロジェクトは,2024年4月の欧州水素銀行の競争入札の際に,応募した132件のなかから選ばれた7件のうちの一つであり,同行から73.1万ユーロの支援を受けることになった。これをきっかけに,レンガスとガスムの名が一挙に世界に広まったのである。
今回の視察ツアーに参加したガス会社の専門家による稼働率をも考慮に入れた換算によれば,タンペレやラハティでの360GWh/年というeメタン生産量は,約4000㎥/時に相当するそうだ。現時点で世界最大と言われるINPEXと大阪ガスが新潟県長岡で進めるeメタンの試験生産の規模は400㎥/時であるから,レンガスのタンペレやラハティでの生産規模は,各々その約10倍に相当する。タンペレ・プロジェクトが2028年に実現すれば,それは,これまで先行していた日本の取組みを一挙に追い抜いて,世界最初のeメタンの社会実装になるのである。
レンガスは,タンペレやラハティを含め,フィンランド国内で6つの地方自治体と協力して,合計1650GWh/年のeメタン製造計画を進めている。今後,海運業界のeメタンに対する需要が急伸すると見込んでおり,その場合には,自治体とは別に製紙業界と連携して,eメタン製造にあたる構想をもっている。
レンガスは,従業員数わずか30名の小企業である。それが世界初のeメタン実装という大仕事をやってのけようとしているのであるから,その心意気には感嘆を禁じえなかった。
次に訪れたガスムは,レンガスが進めるメタネーションで製造されるオフテーカー(引き取り手)となっている会社である。ただし,ガスムでは,レンガスの見方とはニュアンスが異なる話を聞いた。海運業界を中心にカーボンニュートラルガスの需要が伸びると見通す点ではレンガスの場合と同一であったが,その場合のガスの内容についてガスムは,eメタンよりもバイオガスに力点を置いていたのである。eメタンについては,重要な選択肢の一つであるととらえており,レンガスのプロジェクトのオフテーカーとはなってはいるものの,コスト面で課題があるとの見解であった。なお,ガスムは,従業員数352名の中堅企業である。
ガスムは,フィンランドにおけるバイオガス生産の伸長ぶりを強調する。同社のバイオガス生産量は,2020年に0.8TWhだったものが,2024年は2.1TWhまで急増した。そして,2027年には7TWhを生産することを目標としている。
2025年8月現在,ガスムは,フィンランド国内で9ヵ所,他の北欧各地で18ヵ所のバイオガスプラントを運営している。その一角を担うのが,3ヵ所目に訪れたラホヤのプラントである。
ラホヤのバイオガスプラントは,年間合計6万トンのバイオ廃棄物を処理し,輸送と産業用に約40GWhのバイオガスを生産する。また,年間5万トンの有機肥料も生産している。ラホヤのプラントでは,周辺の住民が持ち込んだ生物由来の家庭用ゴミ,枝葉,食用油,製紙会社から出たスラッジなどをフィードとして使用している。見学をしている最中にも,住民のものと思われる乗用車が台車を牽引し,そこに枝葉を満載してプラントに搬入していた。
ラホヤのバイオガスプラントは,ゴミやスラッジの引取りとバイオガスの外販とを,主要な収入源としている。同プラントの規模は小さくはないが,それでもCO2の排出量が不十分であること,および近隣に需要先があまり存在しないことから,eメタンの併産は行っていない。生分解性廃棄物処理場であればどこでもeメタンを作れるわけではないことが,理解できた。
フィンランドでの最後の訪問先は,VTTであった。VTTは,フィンランド国立の技術研究センターであり,約2400名のスタッフが所属する。
VTTは,日本の産業技術総合研究所(産総研)に近い組織であるが,産総研よりも研究対象が広い。例えばVTTは,原子力にかかわる技術研究も行っている。
VTTの役割は,政府・大学と産業界とのあいだの橋渡しをし,基礎研究・応用研究間に存在するギャップを埋めて,イノベーションを生み出すパートナーとなることである。フィンランド内外の多くの企業と協力関係にあり,日本の三菱電機とも海水からCO2を直接回収する技術(DOC: Direct Ocean Capture)の開発協業を進めている。
今回のツアーでは,VTTから,水素,SAF(持続可能な航空燃料),eフュエル(合成液体燃料)などの研究開発状況についても説明を受けた。それらは,日本での開発状況と重なる部分も多かった。
25年8月のフィンランド訪問の主要な目的は,eメタンの社会実装の進展具合を知ることであった。この点は,レンガスが中心となって,着実に進展していることが確認できた。一方で,ガスムの動きに見られるように,フィンランドではバイオガスの利用にも積極的に取り組んでいる。eメタンとバイオガスによってガスのカーボンニュートラル化をめざしている点で,フィンランドと日本は共通していると言える。
反面,今回のツアーでは,フィンランドと日本とのあいだの違いも判明した。フィンランドでは,eメタン等のカーボンニュートラルガスの需要先として,地域の産業や陸運業界・海運業界を想定している。これに対して,日本では,eメタンの主要な需要先として考えられているのは,都市ガス産業や発電事業である。都市ガス供給や発電でのeメタン利用には,まだまだ時間がかかる。メタネーションの取組みに関してフィンランドが日本を追い抜き,日本よりも早くeメタンの社会実装を実現しそうな背景には,このような想定需要先の違いがあるものと思われる。
- 筆 者 :橘川武郎
- 地 域 :欧州
- 分 野 :国際ビジネス
- 分 野 :資源・エネルギー・環境
関連記事
橘川武郎
-
[No.4158 2026.01.12 ]
-
[No.4147 2025.12.29 ]
-
[No.4122 2025.12.15 ]
最新のコラム
-
New! [No.4178 2026.01.19 ]
-
New! [No.4177 2026.01.19 ]
-
New! [No.4176 2026.01.19 ]
-
New! [No.4175 2026.01.19 ]
-
New! [No.4174 2026.01.19 ]
世界経済評論IMPACT 記事検索
おすすめの本〈 広告 〉
-
 イノベーション実現の条件
本体価格:3,200円+税 2021年3月
イノベーション実現の条件
本体価格:3,200円+税 2021年3月
文眞堂 -
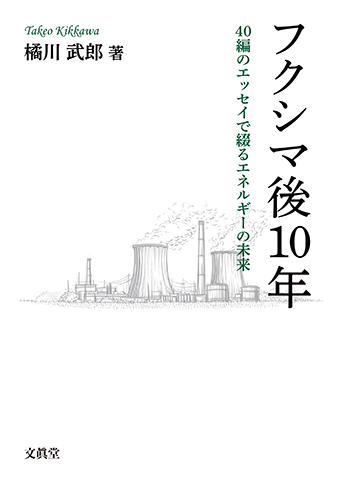 フクシマ後10年:40編のエッセイで綴るエネルギーの未来
本体価格:2,500円+税 2021年3月
フクシマ後10年:40編のエッセイで綴るエネルギーの未来
本体価格:2,500円+税 2021年3月
文眞堂 -
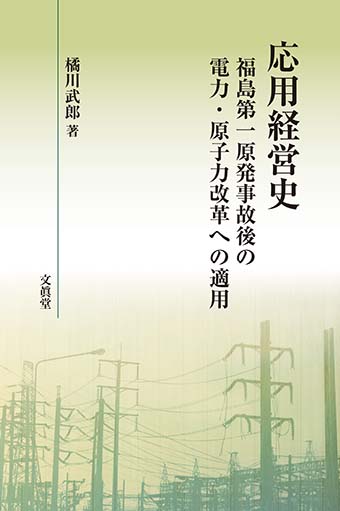 応用経営史:福島第一原発事故後の電力・原子力改革への適用
本体価格:2,750円+税 2016年3月
応用経営史:福島第一原発事故後の電力・原子力改革への適用
本体価格:2,750円+税 2016年3月
文眞堂 -
 中国鉄鋼業:生産システム,企業,産業の三層構造と産業政策
本体価格:4,000円+税 2025年8月
中国鉄鋼業:生産システム,企業,産業の三層構造と産業政策
本体価格:4,000円+税 2025年8月
文眞堂 -
 高収益経営とアントレプレナーシップ:東燃中原延平・伸之の軌跡
本体価格:3,900円+税 2025年11月
高収益経営とアントレプレナーシップ:東燃中原延平・伸之の軌跡
本体価格:3,900円+税 2025年11月
文眞堂 -
 ルビーはなぜ赤いのか?:川野教授の宝石学講座
本体価格:2,500円+税
ルビーはなぜ赤いのか?:川野教授の宝石学講座
本体価格:2,500円+税
文眞堂 -
 職場・学校のセクハラ・パワハラ :ハラスメントの法と判例
本体価格:1,300円+税 2026年1月
職場・学校のセクハラ・パワハラ :ハラスメントの法と判例
本体価格:1,300円+税 2026年1月
文眞堂 -
 国際マーケティングの補助線
本体価格:2,700円+税 2025年9月
国際マーケティングの補助線
本体価格:2,700円+税 2025年9月
文眞堂 -
 揺らぐサムスン共和国:米中対立の狭間で苦悩する巨大財閥
本体価格:2,700円+税 2025年12月
揺らぐサムスン共和国:米中対立の狭間で苦悩する巨大財閥
本体価格:2,700円+税 2025年12月
文眞堂 -
 サービス産業の国際戦略提携:1976~2022:テキストマイニングと事例で読み解くダイナミズム
本体価格:4,000円+税 2025年8月
サービス産業の国際戦略提携:1976~2022:テキストマイニングと事例で読み解くダイナミズム
本体価格:4,000円+税 2025年8月
文眞堂

