世界経済評論IMPACT(世界経済評論インパクト)
「電力の鬼」松永安左エ門の足跡:生誕150年
(国際大学 学長)
2025.08.25
今年(2025年)は,松永安左エ門が生まれてから150年目に当たる。
畏敬の念を込めて「電力の鬼」と呼ばれることが多い松永は,1875(明治8)年に長崎県壱岐島で生まれた。慶應義塾に入学した松永は,そこで,生涯の盟友でありライバルでもあった福澤桃介(福澤諭吉の娘婿)と出会う。桃介の勧誘で電力業界に身を投じた松永は,北九州の九州電灯鉄道や北九州・東海の東邦電力(第二次世界大戦以前の日本における「五大電力」の一つ)などのトップマネジメントとして,辣腕をふるった。
戦前日本を代表する電力業経営者となった松永に対して,当時の論壇は,「科学的経営」の実践者という高い評価を与えた。事実,松永が進めた電力業経営は,①需要家重視の姿勢,②水火併用の電源開発方針,③資金調達面での革新,の3点で出色のものであった。
これらのうち②は,発電コストの切下げに大いに貢献した。松永が電力業経営にいそしむようになった1910年前後の時期には,電力需要のピークは夜の長い冬であった。電力は,おもに照明用や暖房用に使われていたからである。一方,供給サイドは水路式水力発電が中心で,水量と発電量が多いのは夏。多くの電力会社は冬のピークに合わせて水力発電設備に投資したため,夏には電力が余り,コストが上昇することになった。これに対して松永は,コストの最小化をめざして,夏の少ない需要に合わせて水力発電を用意し,冬に足りない分を火力で補おうとしたのである。この優れたビジネスモデルは注目を集め,徐々に業界全体に広がっていった。
松永の電力業経営に関する卓見を象徴した出来事は,1928年に「電力統制私見」を発表したことである。この「私見」は,「電力戦」と称されるほど過熱化していた当時の業界の企業間競争を収束させるために策定されたものであり,民営,地域別9分割,地域独占,発送配電一貫経営の4点を,主要な内容としていた。
これら4点は,ほぼそのままの形で,23年後の1951年に実施に移された。その後長く続く「民営9電力体制」(1988年の沖縄電力の民営化以降は「民営10電力体制」)を生み出した電気事業再編成が,それである。
「電力統制私見」発表から電気事業再編成まで四半世紀近くの歳月を要したのは,日本経済が第二次世界大戦にともなう戦時統制のもとにおかれ,電力国家管理が強行されたからであった。国家管理に徹底抗戦して敗れた松永は,戦時期には電力業経営から離れ隠遁生活を余儀なくされたが,終戦後の1949年に電気事業再編成審議会の会長として社会復帰をはたした。そして,電気事業再編成の立役者となり,「民営9電力体制」の生みの親となったのである。
松永の活躍を可能にした要因としては,日本電力業の発展を牽引した優秀な人材の結集軸となった点をあげることができる。例えば電気事業再編成時には,「三羽烏」と呼ばれた木川田一隆,芦原義重,横山通夫が,サポーターとして松永のもとに参集した。彼ら3名は,のちにそれぞれ,東京電力,関西電力,中部電力の社長となり,日本経済の高度成長に大いに貢献した。
松永自身も,電源の火主水従化や火力燃料の油主炭従化を主導し,高度成長に貢献した。電力業は典型的な公益事業であるが,国際的にもユニークな「民営公益事業」方式を日本に定着させた松永が死去したのは,1971年のことであった。
- 筆 者 :橘川武郎
- 地 域 :日本
- 分 野 :国際ビジネス
- 分 野 :国内
- 分 野 :資源・エネルギー・環境
関連記事
橘川武郎
-
[No.4158 2026.01.12 ]
-
[No.4147 2025.12.29 ]
-
[No.4122 2025.12.15 ]
最新のコラム
-
New! [No.4178 2026.01.19 ]
-
New! [No.4177 2026.01.19 ]
-
New! [No.4176 2026.01.19 ]
-
New! [No.4175 2026.01.19 ]
-
New! [No.4174 2026.01.19 ]
世界経済評論IMPACT 記事検索
おすすめの本〈 広告 〉
-
 イノベーション実現の条件
本体価格:3,200円+税 2021年3月
イノベーション実現の条件
本体価格:3,200円+税 2021年3月
文眞堂 -
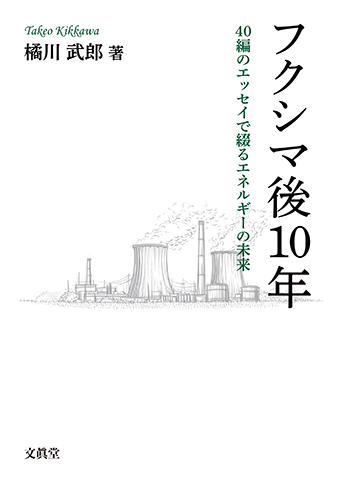 フクシマ後10年:40編のエッセイで綴るエネルギーの未来
本体価格:2,500円+税 2021年3月
フクシマ後10年:40編のエッセイで綴るエネルギーの未来
本体価格:2,500円+税 2021年3月
文眞堂 -
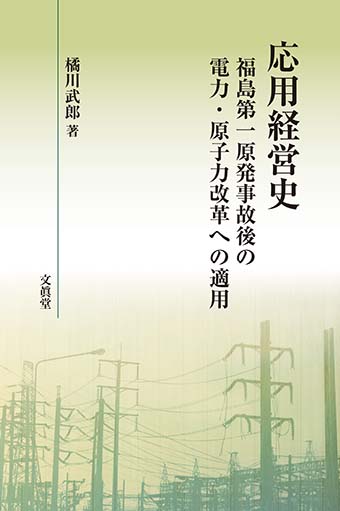 応用経営史:福島第一原発事故後の電力・原子力改革への適用
本体価格:2,750円+税 2016年3月
応用経営史:福島第一原発事故後の電力・原子力改革への適用
本体価格:2,750円+税 2016年3月
文眞堂 -
 高収益経営とアントレプレナーシップ:東燃中原延平・伸之の軌跡
本体価格:3,900円+税 2025年11月
高収益経営とアントレプレナーシップ:東燃中原延平・伸之の軌跡
本体価格:3,900円+税 2025年11月
文眞堂 -
 中国鉄鋼業:生産システム,企業,産業の三層構造と産業政策
本体価格:4,000円+税 2025年8月
中国鉄鋼業:生産システム,企業,産業の三層構造と産業政策
本体価格:4,000円+税 2025年8月
文眞堂 -
 職場・学校のセクハラ・パワハラ :ハラスメントの法と判例
本体価格:1,300円+税 2026年1月
職場・学校のセクハラ・パワハラ :ハラスメントの法と判例
本体価格:1,300円+税 2026年1月
文眞堂 -
 サービス産業の国際戦略提携:1976~2022:テキストマイニングと事例で読み解くダイナミズム
本体価格:4,000円+税 2025年8月
サービス産業の国際戦略提携:1976~2022:テキストマイニングと事例で読み解くダイナミズム
本体価格:4,000円+税 2025年8月
文眞堂 -
 グローバルサウス入門:「南」の論理で読み解く多極世界
本体価格:2,200円+税 2025年9月
グローバルサウス入門:「南」の論理で読み解く多極世界
本体価格:2,200円+税 2025年9月
文眞堂 -
 揺らぐサムスン共和国:米中対立の狭間で苦悩する巨大財閥
本体価格:2,700円+税 2025年12月
揺らぐサムスン共和国:米中対立の狭間で苦悩する巨大財閥
本体価格:2,700円+税 2025年12月
文眞堂 -
 ルビーはなぜ赤いのか?:川野教授の宝石学講座
本体価格:2,500円+税
ルビーはなぜ赤いのか?:川野教授の宝石学講座
本体価格:2,500円+税
文眞堂

