世界経済評論IMPACT(世界経済評論インパクト)
相互関税とASEANの対応
(亜細亜大学アジア研究所 特別研究員)
2025.08.18
4月2日に発表された相互関税は,4月5日から10%のベースライン関税が課され70か国を対象とする上乗せ分に関する交渉が行われてきた。ASEAN各国には高い相互関税が発表され,各国は米国政府と交渉を続け,7月2日にベトナムが20%で合意して以降,順次合意に至っている。相互関税は8月7日に発動されたが,ASEANについては次のようになっている(注1)。最も高いのはラオス(4月2日は48%)とミャンマー(同44%)で40%である。続いてブルネイが25%で4月2日の24%より1%高くなっている。ベトナムは46%から20%に引き下げられた。
一方,カンボジア(同49%),インドネシア(同32%),マレーシア(同24%),タイ(同36%)は19%に引き下げられた。フィリピンも19%だが,4月2日の17%から20%に引き上げられた後19%となった。米国が貿易黒字を計上しているシンガポールはベースライン税率の10%で変更がない。新しい税率の根拠は発表されていない。カンボジアは49%から36%に引き下げられ,タイとカンボジアの国境紛争が停戦に至ると19%に引き下げられた。タイも同様に国境紛争停戦の翌日に19%に引き下げられている。
6か国が対米関税撤廃
相互関税交渉ではASEAN各国は貿易赤字の削減を目的として様々な提案を行い次のような市場開放措置で合意している。まず,米国産品に対する関税の撤廃であり,6か国が対米関税撤廃を行うことで相互関税の引下げに成功した。次に米国産品の購入であり,航空機,農産品,エネルギーの輸入を発表している。3番目に迂回輸出に対する規制の強化であり,フィリピン以外の5か国が約束をしている。他には非関税障壁の撤廃,米国企業を対象とするデジタル分野の規制緩和などが合意されている。合意事項を主要国別にみてみよう(注2)。
- ベトナム:対米関税撤廃,航空機やLNGなどの輸入拡大,中国依存の縮小,第3国からの迂回輸出品に40%課税。
- インドネシア:対米輸入品99%関税撤廃,農産物45億ドル相当,航空機50機輸入,原油等150億ドル輸入,非関税障壁撤廃(電子機器の現地調達義務見直し,米国製自動車米国の安全基準受入れ),第3国からの迂回輸出に高関税。
- タイ:米国製品1万品目以上を無税化,非関税障壁(通関・認証など)削減,インフラ・クリーンエネルギー・ICTなどへの米企業促進措置,米エネルギーや航空機(ボーイング)などの大規模調達公約,原産地規則の強化(中国からの迂回輸入防止策)など。
- マレーシア:98.4%の品目で対米関税撤廃あるいは削減,農産品の販売税免税,自動車・医療機器・医薬品の規格の承認手続きの円滑化,知財権・労働環境などの国際標準の約束と実施強化,デジタルサービス税を課さない,厳密な原産地規則の実施など。
- フィリピン:対米関税撤廃,大豆,小麦,医薬品の輸入拡大,比側は米国との長期の同盟関係を強調,トランプは対中シフト是正を評価した。
- カンボジア:対米関税撤廃,ボーイング737を10機以上購入(引渡し2031年以降),米国向け原産地証明書の発行手続きを厳格化。
相互関税のASEANへの影響
交渉結果については,各国とも一定の評価を行うとともに競合国も高い相互関税(たとえば衣料品でのカンボジアの競合国であるバングラデシュは20%)も課されているなど冷静な見方もある。ただし,対米輸出減少への懸念は強く,経済へのネガティブな影響は避けられないとみられている。たとえば,AMRO(ASEAN+3 Macroeconomic Research Office)がASEANの2025年のGDP成長を4.7%から4.2%に,26年については4.7%から4.2%に下方修正している。今後,半導体に高関税が課されるとマレーシアやシンガポールへの影響が大きくなることが懸念される。
ASEAN側は米国に大きく譲歩したが,これらの措置で米国の対ASEAN輸出が増えるかどうかは判らない。たとえばベトナムの対米輸入上位5品目はすでに無税である。また,航空機や農産品の輸入は一時的なものになる可能性が高い。自動車など製造業製品は米国に競争力があるかどうかが課題である。
第1期トランプ政権で中国に追加関税が課されて以降,中国の対ASEAN投資は拡大を続けてきた。ASEANへの相互関税により中国からASEANへの投資が減少すると報じられているが,中国の対ASEAN投資は今後も続く可能性が強い。ASEAN主要国への相互関税が19%あるいは20%程度となる一方で中国への追加関税は最大55%であり,現在の米国の対中関税率は平均51%と高いためである。また,中国の人件費はASEAN主要国の2倍(カンボジアは3~4倍)程度と高く,中国はASEANに比べ投資コストが高い。
関税による保護政策は中長期的には米国の産業の競争力を損なう可能性が高い。中間財などのコスト増と関税による輸入品に対する保護により米国製造品の輸出競争力,そして輸入品に対する競争力も低下する可能性がある。一方,ASEANの対米関税撤廃はASEANの産業強化に役立つ可能性がある。部分的自由化であるが,コスト削減や国内での競争を促進するためである。明治期日本では不平等な通商条約下で関税自主権がなかったことが工業発展に有利な条件として働いたといわれている(注3)。相互関税を巡るディールは米国の勝利とみられているが,中長期的には米国製造業をさらに衰退させる可能性がある。
輸出先多角化を図るASEAN
相互関税は最恵国待遇(GATT1条)違反であるが,途上国に対し高い関税を課しており,第37条違反(低開発締約国の輸出の障害の軽減・廃止,低開発締約国の輸出について関税及び関税以外の輸入障害の新設・強化をしないなど)でもある。ASEANは相互関税という国際ルールに反する一方的で著しく不平等な措置に対して冷静に対応してきた。4月のASEAN特別経済大臣会議では,ASEANと米国の強固で永続的なパートナーシップを確認し,米国の関税に対して報復措置は課さないことで合意し,5月のASEAN首脳会議でも,一方的な関税に深刻な懸念を表明しつつも建設的関係を維持し,報復措置はとらないと議長声明で表明している。しかし,相互関税に加えASEANで経済社会協力を実施してきた米国国際協力庁(USAID)の廃止は米国への信頼を低下させることは確実である。
こうした状況下で中国はベトナム,マレーシア,カンボジアの3か国で首脳外交を展開した。中国は「米国は信頼できず自国の利益を優先するが,中国は信頼でき相互の利益を重視する国であり,WTOルールに一致しない恣意的な関税引上げを拒否し,ルールに基づく無差別でオープンな多角的貿易システムを支持する」ことを強調し,米国のイメージを引下げ中国のイメージアップに努めた。また,鉄道などインフラ整備やサプライチェーンの強化などを中心にベトナムでは40,マレーシアとは31の協力文書に調印しカンボジアとは37の協力案件を進めることを発表し,ASEANとの経済協力の強化と経済連携の推進を強調した。
しかし,中国のアプローチに対し,ASEANは報復措置を取らないことに早々と合意し中国と一線を画し,特別経済大臣会議や首脳会議で米国との建設的関係を強調し米中均衡戦略の維持を確認している。
ASEANは首脳会議で合意したように経済統合を強化・加速するとともに米国依存の低下を目指して貿易関係の多角化を進めている。2025年に入りインドネシアがBRICSに正式加盟しマレーシア,タイ,ベトナムがパートナー国となった。ASEANのBRICS参加は中国・ロシアの陣営に加わることだという見方があるが,これらの国はIPEF(インド太平洋経済枠組み)に参加し,OECD加盟を進めるなど均衡戦略から外れていない。BRICS参加は国際舞台での発言力の強化に加え,経済的実利によるものである。
5月にはASEAN・GCC(湾岸協力理事会)・中国サミットがマレーシアで開催され,GCCとのFTA交渉が始まった。EUとの2国間FTAはタイ,マレーシア,フィリピンが交渉を行っており,インドネシアは7月に合意に達している。アジア域内貿易の拡大も重要であり,ASEAN+1FTAの改善を着実に進めており,ASEAN豪州NZのFTAが発効し,ASEAN中国FTA3.0が今年調印の見通しである。
トランプ関税の狙いはアメリカン・システムの復活
篠田英朗教授は,40代のトランプ氏が「自分はアメリカン・システムのファンだ」と述べていたことを紹介し,トランプ大統領の「アメリカン・システム」との親和性を指摘している(注4)。これはトランプ大統領の通商政策を理解するための卓見である。米国の初代財務長官アレキサンダー・ハミルトンが提唱した「アメリカン・システム」とは自由貿易に基づく「イギリス・システム」に対抗する通商政策であり,「関税障壁により国内産業を保護し関税収入で道路や運河を建設,国内市場の融合・拡大を図る」ものである(注5)。19世紀の米国は世界で最も高い関税を設定する国となり,フリードリッヒ・リストの幼稚産業保護論のモデルとなっている(注6)。
19世紀初めの「開発途上国」米国で成功したアメリカン・システムが世界の最先進国となりITなどサービス産業で世界をリードする現代の米国で成功し,製造業が復権することはありえない(注7)。ただし,関税収入は大きく増加しており,安定財源になると関税撤廃を行うことが難しくなる。その意味でトランプ関税は長く続く可能性があると考えるべきである。
[注]
- (1)The White House, FURTHER MODIFYING THE RECIPROCAL TARIFF RATES, July 31,2025.
- (2)公式資料がないため各種資料により作成,タイについては助川成也国士館大学教授のご教示による。
- (3)速水佑次郎(1995)『開発経済学』創文社,235頁。
- (4)篠田英朗(2025)『地政学理論で読む多極化する世界 トランプとBRICSの挑戦』かや書房,67-76頁。
- (5)速水佑次郎(1995)『開発経済学』創文社,234-235頁。同著ではアメリカ・システムとなっている。
- (6)同上,234-235頁。
- (7)一般社団法人環太平洋アジア交流協会「トランプ関税で米国製造業は復活するか」を参照
関連記事
石川幸一
-
[No.4120 2025.12.08 ]
-
[No.3856 2025.06.02 ]
-
[No.3838 2025.05.19 ]
最新のコラム
-
New! [No.4162 2026.01.12 ]
-
New! [No.4161 2026.01.12 ]
-
New! [No.4160 2026.01.12 ]
-
New! [No.4159 2026.01.12 ]
-
New! [No.4158 2026.01.12 ]
世界経済評論IMPACT 記事検索
おすすめの本〈 広告 〉
-
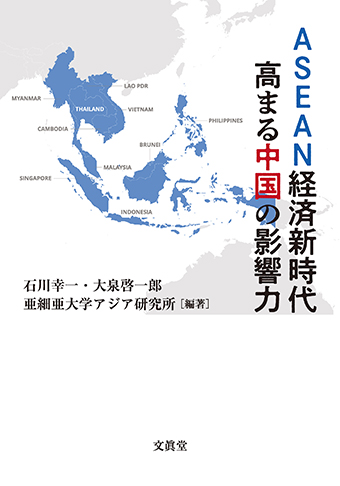 ASEAN経済新時代 高まる中国の影響力
本体価格:3,500円+税 2025年1月
ASEAN経済新時代 高まる中国の影響力
本体価格:3,500円+税 2025年1月
文眞堂 -
 高まる地政学的リスクとアジアの通商秩序:現状と課題、展望
本体価格:2,800円+税 2023年9月
高まる地政学的リスクとアジアの通商秩序:現状と課題、展望
本体価格:2,800円+税 2023年9月
文眞堂 -
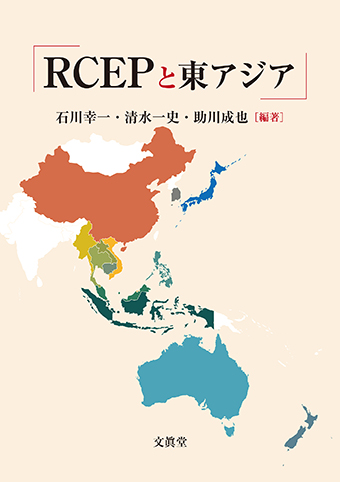 RCEPと東アジア
本体価格:3,200円+税 2022年6月
RCEPと東アジア
本体価格:3,200円+税 2022年6月
文眞堂 -
 グローバルサウス入門:「南」の論理で読み解く多極世界
本体価格:2,200円+税 2025年9月
グローバルサウス入門:「南」の論理で読み解く多極世界
本体価格:2,200円+税 2025年9月
文眞堂 -
 高収益経営とアントレプレナーシップ:東燃中原延平・伸之の軌跡
本体価格:3,900円+税 2025年11月
高収益経営とアントレプレナーシップ:東燃中原延平・伸之の軌跡
本体価格:3,900円+税 2025年11月
文眞堂 -
 中国鉄鋼業:生産システム,企業,産業の三層構造と産業政策
本体価格:4,000円+税 2025年8月
中国鉄鋼業:生産システム,企業,産業の三層構造と産業政策
本体価格:4,000円+税 2025年8月
文眞堂 -
 DEIBにおける経営倫理とCSRの役割:障害者雇用と女性、LGBT、がん患者の方々に焦点を当てて
本体価格:2,700円+税 2025年10月
DEIBにおける経営倫理とCSRの役割:障害者雇用と女性、LGBT、がん患者の方々に焦点を当てて
本体価格:2,700円+税 2025年10月
文眞堂 -
 これさえ読めばすべてわかるアセットマネジメントの教科書
本体価格:2,900円+税 2025年9月
これさえ読めばすべてわかるアセットマネジメントの教科書
本体価格:2,900円+税 2025年9月
文眞堂 -
 揺らぐサムスン共和国:米中対立の狭間で苦悩する巨大財閥
本体価格:2,700円+税 2025年12月
揺らぐサムスン共和国:米中対立の狭間で苦悩する巨大財閥
本体価格:2,700円+税 2025年12月
文眞堂 -
 サービス産業の国際戦略提携:1976~2022:テキストマイニングと事例で読み解くダイナミズム
本体価格:4,000円+税 2025年8月
サービス産業の国際戦略提携:1976~2022:テキストマイニングと事例で読み解くダイナミズム
本体価格:4,000円+税 2025年8月
文眞堂

