世界経済評論IMPACT(世界経済評論インパクト)
エネルギーの未来:2050年の電源ミックスを展望する
(国際大学大学院国際経営学研究科 教授)
2020.07.27
2020年中にも,エネルギー基本計画の改定作業が始まろうとしている。エネルギー基本計画とは,2002年に施行されたエネルギー政策基本法にもとづき策定されるもので,国の中長期的なエネルギー政策の指針を示す役割をもつ。最初のエネルギー基本計画は03年に策定されたが,それ以降,3~4年に1回のペースで改定されてきた。現行の第5次エネルギー基本計画が閣議決定されたのは18年であるから,そろそろ改定の時期を迎えているわけである。
第5次エネルギー基本計画の策定まで効力をもった第4次計画は,11年の東京電力・福島第一原子力発電所事故以降初めての改定を受け,14年に閣議決定された。それを受けて翌15年に決定されたエネルギー長期需給見通しは,30年の電源構成(電源ミックス)を原子力20~22%,再生可能エネルギー22~24%,火力56%とした。第5次エネルギー基本計画においても,この電源構成見通しは維持されることになった。
ここで直視しなければならない点は,エネルギー政策と環境政策にかかわる二つの基本的な閣議決定のあいだに,矛盾が存在することである。第5次エネルギー基本計画が追認した15年策定の電源ミックスでは,2030年に火力発電を56%使うことになっている。一方,16年に閣議決定した地球温暖化対策計画では,2050年までに温室効果ガスを80%削減することにしている。これらの閣議決定は,明らかに矛盾しているのだ。
50年の日本でも,ある程度,製鉄業は石炭を使用しているだろうし,まだガソリン車・ディーゼル車や灯油の暖房,石油化学産業なども残っている可能性が高い。それらを通じて残りの20%分の排出量が生じてしまうので,本当に国内で温室効果ガスを80%削減するのであれば,電源については,ほぼすべてをゼロエミッション電源にしないといけないことになる。
ゼロエミッション電源には,再生可能エネルギー,原子力,CCS(二酸化炭素回収・貯留)付き火力の三つしかない。原発は,リプレース(建て替え)の議論が回避されるなど,きわめて心もとない状況にある。再生エネは,かなり伸長するであろうが,電源のすべてをカバーするのは無理であろう。そうなると,CCSにもきちんと取り組まなくてはいけないことになる。
しかし,CCSのうちのS(貯留)の適地は,日本国内にあまり存在しない。必然的に海外でCCSに取り組まざるをえず,2国間クレジットのような,外国での二酸化炭素排出量削減のうち日本の貢献分をきちんとカウントする仕組みを導入しなければならない。前記の二つの閣議決定について整合性を取るためには,CCSや2国間クレジットの取組みをすぐに始めなければならないわけであるが,現実には,そのような動きはほとんど進展していない。二つの閣議決定が矛盾していると指摘した理由は,ここにある。
経産省は30年を語るが,50年は語らない。環境省は50年を語るが,30年は語らない。こういう「からくり」で,これまで矛盾が糊塗されてきただけである。
ところが,最近では,50年を見据える環境省のカーボンプライシングの主張が,勢いを増してきた。そこで慌てて,経産省も50年のことを語り始めた。このような状況のなかで迎える,今回のエネルギー基本計画の改定である。
第6次エネルギー基本計画の策定に当たっては,今度こそ,「2030年に原子力比率20~22%」などという実現できるはずがない絵空事ではなく,リアリズムに立脚した検討が求められる。その際,有効だと思われるのは,①「原発無し,石炭火力無し」,②「原発無し,石炭火力有り」,③「原発有り,石炭火力無し」,④「原発有り,石炭火力有り」という四つのシナリオを想定し,それぞれのケースで,エネルギー政策の基本となる「S+3E」について,何が問題になるかを直視するアプローチである。「S+3E」とは,Safety(危険性の最小化),Energy Security(エネルギーの安定供給),Economic Efficiency(経済効率性の向上),Environment(地球温暖化対策の推進),のことである。
このような観点から,問題が大いにあると思われる部分に「×」を付してみよう。
再生可能エネルギーの比率が高くなる①と③のシナリオには,「経済効率性」に×をつけざるをえない。再エネのコストは海外では下がっているとはいえ,国内ではまだまだ高いからである。原発を使い続ける③と④のシナリオでは,リプレースが打ち出されていない以上,「危険性の最小化」に×を付すことになる。石炭火力を使う②と④のシナリオには,CCSが進展しない限り「温暖化対策」に×がつくし,逆に石炭火力を使わない①と③のシナリオには,「安定供給」に×が付される。シナリオごとに整理すると,×がつくのは,①では「安定供給」と「経済効率性」,②では「温暖化対策」,③では「危険性の最小化」と「安定供給」と「経済効率性」,④では「危険性の最小化」と「温暖化対策」,ということになる。
これらの×をいかに解消するかが,リアリティあるエネルギー政策のポイントとなる。現時点での筆者の見立てでは,50年時点でも,④のシナリオが最も有力である。ただし,その時点での電源ミックスは,再生可能エネ50%,火力40%,原子力10%となり,「再生可能エネルギー主力電源化」が達成される。もちろんこの見立てがリアリティを持つためには,再生エネのコスト低減,火力発電でのCCSの徹底,原発のリプレースという,三つの課題が達成されていなければならない。
- 筆 者 :橘川武郎
- 地 域 :日本
- 分 野 :国内
- 分 野 :資源・エネルギー・環境
関連記事
橘川武郎
-
New! [No.4210 2026.02.16 ]
-
[No.4179 2026.01.26 ]
-
[No.4158 2026.01.12 ]
最新のコラム
-
New! [No.4219 2026.02.16 ]
-
New! [No.4218 2026.02.16 ]
-
New! [No.4217 2026.02.16 ]
-
New! [No.4216 2026.02.16 ]
-
New! [No.4215 2026.02.16 ]
世界経済評論IMPACT 記事検索
おすすめの本〈 広告 〉
-
 イノベーション実現の条件
本体価格:3,200円+税 2021年3月
イノベーション実現の条件
本体価格:3,200円+税 2021年3月
文眞堂 -
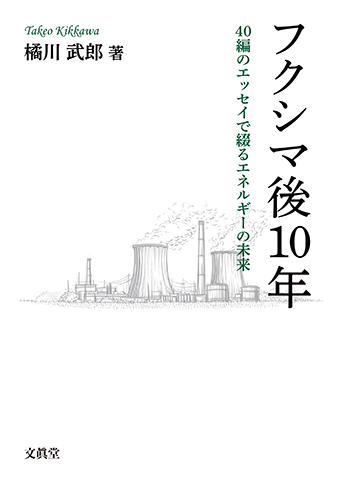 フクシマ後10年:40編のエッセイで綴るエネルギーの未来
本体価格:2,500円+税 2021年3月
フクシマ後10年:40編のエッセイで綴るエネルギーの未来
本体価格:2,500円+税 2021年3月
文眞堂 -
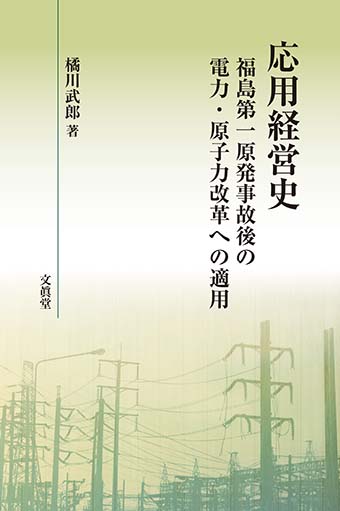 応用経営史:福島第一原発事故後の電力・原子力改革への適用
本体価格:2,750円+税 2016年3月
応用経営史:福島第一原発事故後の電力・原子力改革への適用
本体価格:2,750円+税 2016年3月
文眞堂 -
 中国鉄鋼業:生産システム,企業,産業の三層構造と産業政策
本体価格:4,000円+税 2025年8月
中国鉄鋼業:生産システム,企業,産業の三層構造と産業政策
本体価格:4,000円+税 2025年8月
文眞堂 -
 ルビーはなぜ赤いのか?:川野教授の宝石学講座
本体価格:2,500円+税
ルビーはなぜ赤いのか?:川野教授の宝石学講座
本体価格:2,500円+税
文眞堂 -
 サービス産業の国際戦略提携:1976~2022:テキストマイニングと事例で読み解くダイナミズム
本体価格:4,000円+税 2025年8月
サービス産業の国際戦略提携:1976~2022:テキストマイニングと事例で読み解くダイナミズム
本体価格:4,000円+税 2025年8月
文眞堂 -
 ソーシャルマーケティング:行動変容で社会的価値を共創する
本体価格:3,500円+税 2025年12月
ソーシャルマーケティング:行動変容で社会的価値を共創する
本体価格:3,500円+税 2025年12月
文眞堂 -
 揺らぐサムスン共和国:米中対立の狭間で苦悩する巨大財閥
本体価格:2,700円+税 2025年12月
揺らぐサムスン共和国:米中対立の狭間で苦悩する巨大財閥
本体価格:2,700円+税 2025年12月
文眞堂 -
 DEIBにおける経営倫理とCSRの役割:障害者雇用と女性、LGBT、がん患者の方々に焦点を当てて
本体価格:2,700円+税 2025年10月
DEIBにおける経営倫理とCSRの役割:障害者雇用と女性、LGBT、がん患者の方々に焦点を当てて
本体価格:2,700円+税 2025年10月
文眞堂 -
 グローバルサウス入門:「南」の論理で読み解く多極世界
本体価格:2,200円+税 2025年9月
グローバルサウス入門:「南」の論理で読み解く多極世界
本体価格:2,200円+税 2025年9月
文眞堂
