世界経済評論IMPACT(世界経済評論インパクト)
カーボンニュートラルポートの先頭を走る横浜港:「横浜港港湾脱炭素化推進計画」の特徴
(国際大学 学長)
2025.06.09
2025年3月,横浜市は「横浜港港湾脱炭素化推進計画」(以下,「横浜港計画」と略す)を公表した。筆者は,同計画の策定にあたった横浜港脱炭素化推進臨海部事業所協議会の座長をつとめた。
この横浜港計画は,現在,国が全国各地で進めているカーボンニュートラルポート事業の先頭を走るものである。筆者が当事者であるから,そう言うのではない。それには,きちんとした根拠がある。
第1の根拠は,国が放棄した1.5℃シナリオの実現を,この計画はしっかりと堅持していることである。世界的に気候変動問題は深刻化しており,各国は,地球の平均気温上昇を産業革命以前に比べて1.5℃以内に抑える1.5℃シナリオの実現に取り組んでいる。国は,2023年5月に広島で開催されたG7(先進国首脳会議)に先立ち同年4月に札幌で行われた気候・エネルギー・環境担当大臣会合で,1.5℃シナリオを達成するため,2035年度までに温室効果ガス(GHG)の排出量を2019年度比で60%削減することを,国際公約した。ところが,2025年2月に閣議決定された「地球温暖化対策計画」では,基準年度が2019年度から2013年度にすりかえられ,この国際公約は取り下げられた。2013〜19年度のあいだに日本のGHG排出量は14%低減したから,政府の言う「2035年度2013年度比60%削減」は,2019年度比に換算すれば,50%台半ばの削減にしかならない。このように国が1.5℃シナリオを事実上放棄したのとは対照的に,横浜港計画では,それをきちんと維持している。同計画はGHGの中心である二酸化炭素(CO2)の排出量削減をKPI(重要達成度目標)としたうえで,2035年度に横浜港臨海部から排出されるCO2の量を,2019年度比で60%削減することに言及している。横浜港計画では,1.5℃シナリオが堅持されたのである。
第2の根拠は,他港ではほとんど取り上げらていないコンテナ船燃料の脱炭素化を推進していることである。横浜市が,グリーンメタノールの利用促進に向けて,23年12月に,マースクAS(デンマークに本社を置くコンテナ船世界大手のA.P.モラー・マースクの日本法人)および三菱ガス化学と覚書を締結したのは,それを象徴する出来事である。また,横浜市は,タグボート燃料の脱炭素化をめざして,アンモニアバンカリングにも取り組んでいる。
第3の根拠は,大企業のみならず中小企業をも金融支援対象とする「横浜港CNP(カーボンニュートラルポート)サステナブルファイナンスフレームワーク」を立ち上げることである。このフレームワークの出発点となったのは,2024年4月に,横浜市がみずほ銀行と覚書を締結したことである。
第4の根拠は,横浜港臨海部が,東京湾のはるか沖合に建設される予定である浮体式洋上風力の発生電力の受入拠点となる構想が存在することである。この構想を実現するため,横浜市は,2025年1月に,東京電力パワーグリッド,海上パワーグリッド,戸田建設および三菱UFJ銀行と覚書を締結した。これらのうち海上パワーグリッドは,電気を船で運ぶ電気運搬船の専門会社である。東京都の小池百合子都知事は,2024年11月に,伊豆諸島の海域に合計出力が100万kW規模に達する浮体式洋上風力を建設するプランを発表した。この東京都のプランは,横浜港計画が打ち出した洋上風力発生電力受入拠点構想と連動する可能性がある。
このように,横浜港計画は,他に類例をみない特徴を有している。本稿の冒頭で,「横浜港計画は,国が全国各地で進めているカーボンニュートラルポート事業の先頭を走るものである」と述べた所以である。
- 筆 者 :橘川武郎
- 地 域 :日本
- 分 野 :国際ビジネス
- 分 野 :国内
- 分 野 :資源・エネルギー・環境
関連記事
橘川武郎
-
New! [No.4210 2026.02.16 ]
-
[No.4179 2026.01.26 ]
-
[No.4158 2026.01.12 ]
最新のコラム
-
New! [No.4219 2026.02.16 ]
-
New! [No.4218 2026.02.16 ]
-
New! [No.4217 2026.02.16 ]
-
New! [No.4216 2026.02.16 ]
-
New! [No.4215 2026.02.16 ]
世界経済評論IMPACT 記事検索
おすすめの本〈 広告 〉
-
 イノベーション実現の条件
本体価格:3,200円+税 2021年3月
イノベーション実現の条件
本体価格:3,200円+税 2021年3月
文眞堂 -
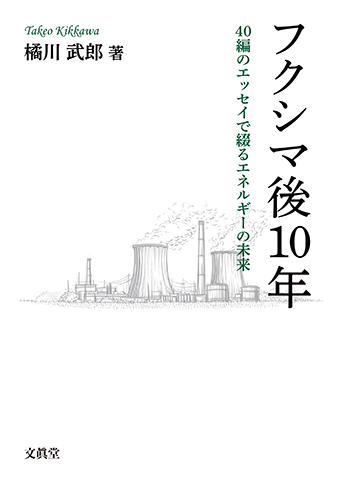 フクシマ後10年:40編のエッセイで綴るエネルギーの未来
本体価格:2,500円+税 2021年3月
フクシマ後10年:40編のエッセイで綴るエネルギーの未来
本体価格:2,500円+税 2021年3月
文眞堂 -
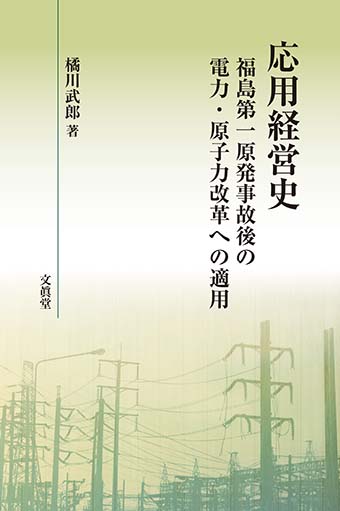 応用経営史:福島第一原発事故後の電力・原子力改革への適用
本体価格:2,750円+税 2016年3月
応用経営史:福島第一原発事故後の電力・原子力改革への適用
本体価格:2,750円+税 2016年3月
文眞堂 -
 高収益経営とアントレプレナーシップ:東燃中原延平・伸之の軌跡
本体価格:3,900円+税 2025年11月
高収益経営とアントレプレナーシップ:東燃中原延平・伸之の軌跡
本体価格:3,900円+税 2025年11月
文眞堂 -
 職場・学校のセクハラ・パワハラ :ハラスメントの法と判例
本体価格:1,300円+税 2026年1月
職場・学校のセクハラ・パワハラ :ハラスメントの法と判例
本体価格:1,300円+税 2026年1月
文眞堂 -
 中国鉄鋼業:生産システム,企業,産業の三層構造と産業政策
本体価格:4,000円+税 2025年8月
中国鉄鋼業:生産システム,企業,産業の三層構造と産業政策
本体価格:4,000円+税 2025年8月
文眞堂 -
 サービス産業の国際戦略提携:1976~2022:テキストマイニングと事例で読み解くダイナミズム
本体価格:4,000円+税 2025年8月
サービス産業の国際戦略提携:1976~2022:テキストマイニングと事例で読み解くダイナミズム
本体価格:4,000円+税 2025年8月
文眞堂 -
 グローバルサウス入門:「南」の論理で読み解く多極世界
本体価格:2,200円+税 2025年9月
グローバルサウス入門:「南」の論理で読み解く多極世界
本体価格:2,200円+税 2025年9月
文眞堂 -
 国際マーケティングの補助線
本体価格:2,700円+税 2025年9月
国際マーケティングの補助線
本体価格:2,700円+税 2025年9月
文眞堂 -
 ルビーはなぜ赤いのか?:川野教授の宝石学講座
本体価格:2,500円+税
ルビーはなぜ赤いのか?:川野教授の宝石学講座
本体価格:2,500円+税
文眞堂
