世界経済評論IMPACT(世界経済評論インパクト)
脱炭素から低炭素への移行:天然ガスに留まらない第7次エネ基「新方針」の影響
(国際大学 学長)
2025.05.19
2025年5月5日に本欄で発信した拙稿「カーボンニュートラル実現後も重要な天然ガス:第7次エネ基『新方針』のインパクト」(「世界経済評論IMPACT」No.3812)では,2025年2月に閣議決定された第7次エネルギー基本計画(エネ基)が天然ガスにきわめて高い位置づけを与え,「天然ガスはカーボンニュートラルの実現後も重要なエネルギー源である」とする「新方針」を打ち出したことを指摘した。本稿では,前稿での議論を敷衍して,この「新方針」がもつ意味について掘り下げる。
まず,強調すべき点は,第7次エネ基が,カーボンニュートラルの旗をけっして降ろしたわけではないことである。「天然ガスはカーボンニュートラルの実現後も重要なエネルギー源である」とした「新方針」は,あくまで「カーボンニュートラルの実現」を前提とするものなのである。
もともと,カーボンニュートラルとは,二酸化炭素等の温室効果ガスの排出量をゼロにするという意味ではない。排出量を吸収・回収量と一致させて,ネットゼロ(プラスマイナスゼロ)にするという意味である。
つまり,天然ガスの使用停止というような厳しい脱炭素施策をとらなくとも,二酸化炭素排出量を低減する低炭素施策を講じたうえでCCUS(二酸化炭素回収・利用,貯留)やDAC(空気からの二酸化炭素の直接回収技術)などの吸収・回収施策を抜本的に強化すれば,カーボンニュートラルは達成されるのである。「天然ガスはカーボンニュートラル実現後も重要なエネルギー源である」とした第7次エネ基の「新方針」は,吸収・回収施策の抜本的強化という条件付きではあるが,「脱炭素から低炭素への移行」と要約することもできる。
天然ガスについて言えば,「二酸化炭素排出量を低減する低炭素施策」としては,バイオガスや水素の混入が有効である。また,「吸収・回収施策」としては,CCUSやDACのほかにも,間接的手法であるが,カーボンクレジットによってオフセットするというやり方もある。
これらのうち,CCUSやDAC,カーボンクレジットによるオフセットという「吸収・回収施策」は,天然ガスのみならず,石油やLP(液化石油)ガスなどの他の化石燃料のカーボンニュートラル化にとっても,有効な手段である。さらには,第7次エネ基が,石油についてはe10(ガソリンへのバイオエタノールの10%混入)やバイオディーゼル,LPガスについてはrDME(バイオ由来のジメチルエーテル)の混入などの,「低炭素施策」を強調している点も見落としてはならない。
もちろん,これらの「低炭素施策」や「吸収・回収施策」を実施する技術的,制度的条件は,現状では十分には整っていない。しかし,カーボンニュートラルが実現する2050年までには,条件整備が進むだろう。そうなれば,カーボンニュートラルの実現と天然ガス・石油・LPガス等の化石燃料の使用継続とが両立することは可能になるわけである。
第7次エネ基の「新方針」のインパクトが及ぶ範囲は,ひとり天然ガスに限られるわけではない。石油・LPガスにも,インパクトが波及することも考えられる。
- 筆 者 :橘川武郎
- 地 域 :日本
- 分 野 :国際経済
- 分 野 :国内
- 分 野 :資源・エネルギー・環境
関連記事
橘川武郎
-
[No.4158 2026.01.12 ]
-
[No.4147 2025.12.29 ]
-
[No.4122 2025.12.15 ]
最新のコラム
-
New! [No.4178 2026.01.19 ]
-
New! [No.4177 2026.01.19 ]
-
New! [No.4176 2026.01.19 ]
-
New! [No.4175 2026.01.19 ]
-
New! [No.4174 2026.01.19 ]
世界経済評論IMPACT 記事検索
おすすめの本〈 広告 〉
-
 イノベーション実現の条件
本体価格:3,200円+税 2021年3月
イノベーション実現の条件
本体価格:3,200円+税 2021年3月
文眞堂 -
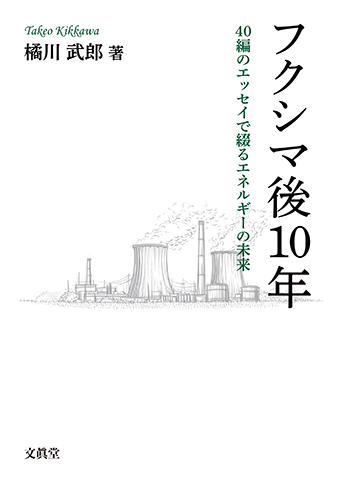 フクシマ後10年:40編のエッセイで綴るエネルギーの未来
本体価格:2,500円+税 2021年3月
フクシマ後10年:40編のエッセイで綴るエネルギーの未来
本体価格:2,500円+税 2021年3月
文眞堂 -
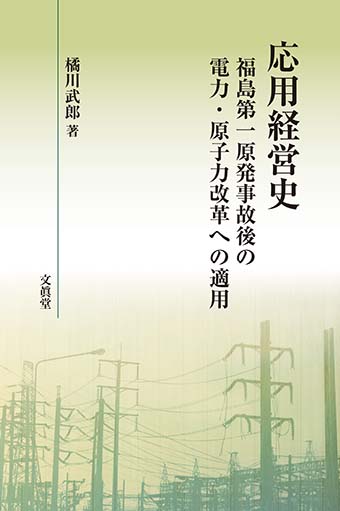 応用経営史:福島第一原発事故後の電力・原子力改革への適用
本体価格:2,750円+税 2016年3月
応用経営史:福島第一原発事故後の電力・原子力改革への適用
本体価格:2,750円+税 2016年3月
文眞堂 -
 サービス産業の国際戦略提携:1976~2022:テキストマイニングと事例で読み解くダイナミズム
本体価格:4,000円+税 2025年8月
サービス産業の国際戦略提携:1976~2022:テキストマイニングと事例で読み解くダイナミズム
本体価格:4,000円+税 2025年8月
文眞堂 -
 DEIBにおける経営倫理とCSRの役割:障害者雇用と女性、LGBT、がん患者の方々に焦点を当てて
本体価格:2,700円+税 2025年10月
DEIBにおける経営倫理とCSRの役割:障害者雇用と女性、LGBT、がん患者の方々に焦点を当てて
本体価格:2,700円+税 2025年10月
文眞堂 -
 グローバルサウス入門:「南」の論理で読み解く多極世界
本体価格:2,200円+税 2025年9月
グローバルサウス入門:「南」の論理で読み解く多極世界
本体価格:2,200円+税 2025年9月
文眞堂 -
 これさえ読めばすべてわかるアセットマネジメントの教科書
本体価格:2,900円+税 2025年9月
これさえ読めばすべてわかるアセットマネジメントの教科書
本体価格:2,900円+税 2025年9月
文眞堂 -
 中国鉄鋼業:生産システム,企業,産業の三層構造と産業政策
本体価格:4,000円+税 2025年8月
中国鉄鋼業:生産システム,企業,産業の三層構造と産業政策
本体価格:4,000円+税 2025年8月
文眞堂 -
 揺らぐサムスン共和国:米中対立の狭間で苦悩する巨大財閥
本体価格:2,700円+税 2025年12月
揺らぐサムスン共和国:米中対立の狭間で苦悩する巨大財閥
本体価格:2,700円+税 2025年12月
文眞堂 -
 高収益経営とアントレプレナーシップ:東燃中原延平・伸之の軌跡
本体価格:3,900円+税 2025年11月
高収益経営とアントレプレナーシップ:東燃中原延平・伸之の軌跡
本体価格:3,900円+税 2025年11月
文眞堂

