世界経済評論IMPACT(世界経済評論インパクト)
大阪・関西万博2025について思う
(元城西国際大学院 特任教授)
2025.10.20
6か月間続いた2025年日本国際博覧会が10月13日に閉幕した。閉会式の中継を見ながら,人や建物で混み合い,暑かった会場や噴水ショーを見た大屋根リンクを思い出しながら,大きな事故もなく,無事に終わったことに安堵した。
会期中,6月に二日,10月に一日,合計三日間,会場の夢洲を訪れた。最初の日はフランス商工会議所がアレンジしたツアーに参加し,その後は一人で会場を回った。時には1時間以上も列に並んだ。会場は広く,夕方には1万5千歩を越し,タクシーで戻った日もある。米,仏,白など合計13のパビリオンに入り,アルジェリア館では政府代表・館長と懇談する機会も得た。ネット予約が取れなかった日本館やシグネチャー館などは外から眺めた。日本館は霞ヶ関の経済産業省にも展示があったようだが,知ったときにはすでに終わっていた。中国館は漢字が竹簡に書かれた建物の正面を写真に収めた。
会場へのアクセス,スマホでのパビリオンの事前予約方法,車椅子来場者などのファースト・レーン,行列の整理,食事やトイレなどについて色々と感じた。AIに「大阪万博の評価は」と聞くと,これらの運営関係の問題点や良かった点が出てくる。雑誌『CASA』の丸ごと特集「万博最終案内」号に目を通し,雑誌『世界』10月号の「万博は実験のためにある」という建築史家の論文も読んだ。万博を訪問した何人かの友人たちとも話したが,このメガイベントについての印象は人それぞれである。論評は建築や技術に関するものが多いようだが,ここでは世界経済や環境に関心を持つ一訪問者としての印象を記したい。
一般入場者は2557万人(関係者を含めると29百万人)と想定の28百万人を下回ったが,ぬいぐるみのミャクミャクなどのグッズの売り上げが順調なため,運営収支は200億円以上の黒字と報じられている。この種のメガイベントの評価は難しいが,財政面では一応成功と言ってもいいのであろう。
全長2キロ,高いところで20メートルの大屋根リングがある。その内を中心に外にも数多くのパヴィリオン(展示館)が立ち,「いのち輝く未来社会のデザイン」という共通のテーマのもとに,158の国と地域そして10の国際機関,それに加えかなりの数の企業がパートナーやパヴィリオン運営の形で参加した。新聞は,来場者が会場のいたる所で,大屋根リングに象徴される「多様でありながら一つ」を身近に感じ,今後もつながりや平和を望むという声を取り上げる。そうした声が多いだろうと私も感じた。
この10年間を振り返ると,コロナ拡大の中で東京オリンピックが無観客開催となり,近年の円安の下で日本人の海外旅行は低調である。一方インバウンド観光はコロナのあと活況を呈し,日本経済を潤している。2019年6月のG20総会で大阪が注目を浴びたが,今回は夢洲という人工島に作られた万博会場に,多い時は一日20万人以上の世界の人々が集まり,パヴィリオンで,そしてパフォーマンス,食事などを通じて,様々な接触・交流があった。名前だけを知っている国や聞いたこともない国があるが,パビリオンに行けばそこの人がいて,その国のことを知れる。子供連れや若い人はそれだけでも嬉しいであろう。ナショナルデイに外国の首脳,ビジネス関係者などが来日し,石破首相は50回以上の会談をした。私の周りにもレセプションに出た人やパヴィリオンでの催しに関わった人がいる。
「多様ながら(にして)一つ」は,E Uのモットー「United in diversity」に通じるが,最近は欧米で移民抑制の動きが広がり,仏,独などでは極右政党の躍進が著しい。国際社会が目指してきた「多様性,公平性,包摂性」についても現トランプ政権は否定的で,関連機関の閉鎖が始まった。こうした状況の中で,「多様でありながら一つにつながって」「対話をし,協働すること」(大阪万博宣言)の意義は大きい。その意味し,目指すところをよく考えて,多様性の重視を経済・社会政策に反映し,個人の行動につなげることが望まれる。
今回の万博への参加を途中で取りやめた国は,ロシアとベラルーシ。G20のメンバーたるメキシコ,アルゼンチン,南アフリカ,そのほかイラン,ギリシャ,エストニア,ボツワナなども不参加であった。G7に経済制裁を受けているロシアとベラルーシはやむを得ないとしても,他の国の不参加は選挙や財政手当の難しさなど主に国内事情のようだが,いささか寂しい気がした。
現在のような万博は,1923年にパリで調印された(最新は1988年に改正)国際博覧会条約に基づき催行されている。「公衆の教育を主たる目的として」「文明の必要とするものに応じるため」「一または二以上の部門において達成された進歩や将来の展望」を対象とする。具体的に何を展覧するかは(科学,技術,文化,自然など),その時々に加盟国の総意で決め,具体的な解釈や展示は参加国にゆだねられているようだ。19世紀半ばからの長い歴史は,植民地を経営し,産業革命が進む時代に始まった。アールヌーボーの芸術が世界に広がった時代もあり,そして二度の世界大戦や冷戦もあった。「文明」「進歩」「未来」というスローガンの下で万博は続いてきている。
今回は「いのち輝く未来のデザイン」のテーマの下に,「いのちを救う」・「いのちに力を与える」・「いのちをつなぐ」の三つのサブテーマがあった。それぞれの国や企業がそれをテーマに展示をし,大きなスペースの展示館は没入型オーデイオヴィジュアルの舞台となった。「いのち」はライフ,つまり生命であり,生活でもある。様々に解釈され,展示に反映された。見たところでは,「命」を水やオリーブの木・葡萄酒が象徴し(仏,白,モナコ),自国のへルスケア産業(ワクチン,人工関節)の展示もあり(白),アンゴラはマラリアとの闘いという健康教育をテーマにした。多数の薬草の標本(バルト)もあった。米国館はITを活用した農業やスタートアップを強調し,宇宙飛行ロケットの下に入れた。最新の医療機械もあった気がする。月の石(米),火星の土(日)なども展示された。
今年は国連SDG(持続開発目標)10年の中間年に当たる。「持続可能性Sustainability」という視点が広く意識され,循環経済(独,マスコットはサーキュラー君)や生態系の循環(日)をテーマにするところが目立ち,第二日本政府館ともいうべき女性館は男女均等をテーマに取り上げた。
建物は大屋根リングや日本館をはじめとして多くのパヴィリオンが木材で建てられ,会場中央に森が造られた。環境に配慮した軽量建物(スイス),空気の循環を良くしたということも何箇所かで聞いた。ただ,半年経ち,閉幕した今,一部は保存・再利用されるとはいうものの,大部分が解体・撤去されていくことを持続性との観点でどう考えるべきであろうか。
万博は,参加国にとって自国の発展ぶりと日本との関係を広く示す数少ない,絶好の機会である。近年ガス関係での日本との関わりが薄くなったが,国として確実に発展しているアルジェリアや経済成長が持続し,カカオ産業が発展するコートジボワール。パヴィリオンを訪れたこの両国に限られないが,日本との経済・文化関係の拡大を望む多くの国が万博をきっかけに具体的な成果をあげることが期待される。もののけ姫や厳島神社が登場し(仏),金継ぎのイメージ(白)や俳句(モナコ)を使うなど,日本文化へのオマージュも見られた。
中南米では,多岐に及ぶ自然とともに先住民族に伝わるデザイン性豊かなマント作りを展示したチリと,「百年の孤独」に登場する黄色い蝶が案内するアマゾンにおける生物多様性を中心に据えたコロンビア。パヴィリオンに入ったこの2カ国はともに数年前に左派の政権が発足し,新しい姿を見せている。アンデス地域にはCAFという地域開発金融機関が昔からあるが,「サウス」の立場に立ち,ブラジルなどを含めたラテンアメリカも対象にし,環境保全,地域統合やそのためのインフラ建設のファイナンスを拡充すると発信をしている。
参加国はデジタルで映像技術を活用した展示をし,来場者は楽しみながら学ぶことになる。ペーパーレスの会場では,その場で知ったことや印象を,スマホでとった写真も見ながら後になって振り返る。フランス館は30分程度の公式ビデオ(virtual版)を用意していたが,他の国では日本館を除き,そうした工夫に気が付かなかった。見過ごした人や会場に行けなかった人のために,今後テレビ番組やビデオが作られるといいと思う。
次回2030年の万博はサウジアラビア・リアドでの開催である。中近東の安定やガザ復興が進むと期待され,アラブ世界の政治経済・文化面での影響力増大が反映されよう。会場の敷地面積は今回の4倍だそうである。でも,そんなに広大な会場をどのように回るのだろうか。
関連記事
久米五郎太
-
[No.3636 2024.11.25 ]
-
[No.2843 2023.02.06 ]
-
[No.1661 2020.03.16 ]
最新のコラム
-
New! [No.4194 2026.02.02 ]
-
New! [No.4193 2026.02.02 ]
-
New! [No.4192 2026.02.02 ]
-
New! [No.4191 2026.02.02 ]
-
New! [No.4190 2026.02.02 ]
世界経済評論IMPACT 記事検索
おすすめの本〈 広告 〉
-
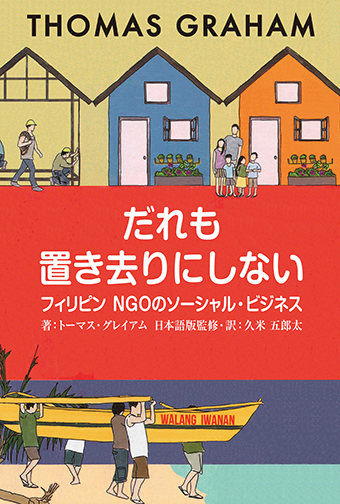 だれも置き去りにしない:フィリピン NGOのソーシャル・ビジネス
本体価格:1,800円+税 2018年9月
だれも置き去りにしない:フィリピン NGOのソーシャル・ビジネス
本体価格:1,800円+税 2018年9月
文眞堂 -
 グローバルサウス入門:「南」の論理で読み解く多極世界
本体価格:2,200円+税 2025年9月
グローバルサウス入門:「南」の論理で読み解く多極世界
本体価格:2,200円+税 2025年9月
文眞堂 -
 DEIBにおける経営倫理とCSRの役割:障害者雇用と女性、LGBT、がん患者の方々に焦点を当てて
本体価格:2,700円+税 2025年10月
DEIBにおける経営倫理とCSRの役割:障害者雇用と女性、LGBT、がん患者の方々に焦点を当てて
本体価格:2,700円+税 2025年10月
文眞堂 -
 国際マーケティングの補助線
本体価格:2,700円+税 2025年9月
国際マーケティングの補助線
本体価格:2,700円+税 2025年9月
文眞堂 -
 創造力強化経営の実践
本体価格:2,200円+税
創造力強化経営の実践
本体価格:2,200円+税
文眞堂 -
 中国鉄鋼業:生産システム,企業,産業の三層構造と産業政策
本体価格:4,000円+税 2025年8月
中国鉄鋼業:生産システム,企業,産業の三層構造と産業政策
本体価格:4,000円+税 2025年8月
文眞堂 -
 高収益経営とアントレプレナーシップ:東燃中原延平・伸之の軌跡
本体価格:3,900円+税 2025年11月
高収益経営とアントレプレナーシップ:東燃中原延平・伸之の軌跡
本体価格:3,900円+税 2025年11月
文眞堂 -
 職場・学校のセクハラ・パワハラ :ハラスメントの法と判例
本体価格:1,300円+税 2026年1月
職場・学校のセクハラ・パワハラ :ハラスメントの法と判例
本体価格:1,300円+税 2026年1月
文眞堂 -
 ルビーはなぜ赤いのか?:川野教授の宝石学講座
本体価格:2,500円+税
ルビーはなぜ赤いのか?:川野教授の宝石学講座
本体価格:2,500円+税
文眞堂 -
 ソーシャルマーケティング:行動変容で社会的価値を共創する
本体価格:3,500円+税 2025年12月
ソーシャルマーケティング:行動変容で社会的価値を共創する
本体価格:3,500円+税 2025年12月
文眞堂

