世界経済評論IMPACT(世界経済評論インパクト)
ビジネスモデルのつくり方:戦略アプローチと取引アプローチ
(常磐大学 教授)
2025.09.08
現在,日本では国と自治体によるスタートアップ支援施策が積極的にとられている。起業の際の重要なものとして,利益を生み出す仕組みを意味するビジネスモデルが挙げられる。既存の企業であっても,ビジネスモデルは現状把握や今後のビジネス活動の展開を考える際に重要となる。
ビジネスモデルは,抽象と具体,そして論理(収束)と閃き(発散)をそれぞれ往復して創造されていくものである(井上達彦『ゼロからつくるビジネスモデル』東洋経済新報社,2019年)。具体的には縦軸を抽象(上)と具体(下),横軸を論理(左)と閃き(右)とすると,ビジネスモデルを創造する際は,抽象・論理の①分析(調査分析を行う),抽象・閃きの②発想(課題を設定し,その解決策のアイデアを創出する),具体・閃きの③試作(ビジネスモデルのプロトタイプを作る),具体・論理の④検証(ビジネスモデルを検証する)の4段階を経ていく(その後さらに①→②→③→④→①…とサイクルを経て,ビジネスモデルを発展させていく)。
本稿では,上記の4段階を基に,総合的なビジネスモデルの構築について説明を行ってみたい。「総合的な」という表現を用いているのは,様々存在し別々に説明されるビジネスモデルの既存議論を,できるだけ総合することを意図しているからである。ビジネスモデル構築のアプローチには,大きくは戦略アプローチと取引アプローチがある。
戦略アプローチは他社との差別化を図る競争戦略に重点を置いている(『世界経済評論IMPACT』No.3343参照)。具体的には,企業の外部環境(競争状況,顧客等)と内部環境(自社)を①分析する。外部環境は業界における位置付けであるポジショニングを分析し,内部環境は人材や技術といった経営資源さらにそれらを状況に合わせて組み合わせるダイナミック・ケイパビリティを分析する。そして「誰に」「何を」「どのように」提供し利益を上げるのかについて②発想する。それをビジネスモデル・キャンバス(アレックス・オスターワルダー&イヴ・ピニュール『ビジネスモデル・ジェネレーション』(小山龍介訳)翔泳社,2012年)として③試作を行う。ビジネスモデル・キャンバスは,外部環境である顧客接点(顧客セグメント・顧客関係・チャネル,主に「誰に」)は主にポジショニングを踏まえて考察し,内部環境である経営基盤(資源・活動・パートナー,主に「どのように」)は主に経営資源とダイナミック・ケイパビリティを踏まえて考察し,顧客価値(価値提案,主に「何を」)がそれらを統合する。そして顧客接点が売上(収益),経営基盤がコスト構造を反映し,それらは売上-コスト=利益を示す財務的側面(売上・コスト構造)を表している。そしてビジネスを実施し,④検証を行い,改善につなげていく。この一連のプロセスの中の①と②の段階で,外部環境である市場における機会(Opportunity:O)と脅威(Threat:T),内部環境である自社の強み(Strength:S)と弱み(Weakness:W)を整理し(①段階),さらに方向性を考える(②段階:強みを活かし機会を活かすSO戦略,弱みを最小化し機会を活かすWO戦略,強みを活かし脅威を最小化するST戦略,弱みを最小化し脅威を最小化するWT戦略)というSWOT分析の利用は効果的となろう。
取引アプローチはビジネスの取引構造に重点を置いている(『世界経済評論IMPACT』No.3730参照)。成功している企業の取引構造の事例を①分析し,それを模倣し自社はどうすればよいか②発想し,ピクト図解(板橋悟『ビジネスモデルを見える化するピクト図解』ダイヤモンド社,2010年)として③試作を行い,そしてビジネスを実施し,④検証を行い,改善につなげていく(井上達彦『ビジュアルビジネスモデルがわかる』日経文庫,2021年)。ピクト図解は,顧客,企業,製品やサービス,価格,販売と支払い,取引の時間経過やまとめを記号によって説明を行うものである。
戦略アプローチと取引アプローチの内容を説明する際に基とした①分析②発想③試作④検証の4段階には,①分析では外部環境と内部環境,事例等調査し,観察やインタビューを行い,それらを基に顧客等の状況を明確にし,②発想では課題を設定し,その解決策のアイデアを生み出し,③試作ではプロトタイプに落とし込み,④検証では実際のテストを行い改善につなげていくというイノベーション手法のデザイン思考という考え方が根底にある。プロトタイプはあくまで仮説であり,顧客等のフィードバックによって改善するというリーン・スタートアップ(エリック・リース『リーン・スタートアップ』(井口耕二訳)日経BP社,2012年)の考え方も含めて,各段階を行き来する試行錯誤の繰り返しが,変化の速い予測困難な状況の中でより良い成果を得ていくことにつながっている。
戦略アプローチと取引アプローチは,観点は異なるが対立するものではない。実際にはこれらはどこに重点を置くのかで使い分け,場合によっては両方を使用し,ビジネスモデルを構築していく必要がある。
関連記事
村中 均
-
[No.4112 2025.12.08 ]
-
[No.3784 2025.04.07 ]
-
[No.3730 2025.02.17 ]
最新のコラム
-
New! [No.4178 2026.01.19 ]
-
New! [No.4177 2026.01.19 ]
-
New! [No.4176 2026.01.19 ]
-
New! [No.4175 2026.01.19 ]
-
New! [No.4174 2026.01.19 ]
世界経済評論IMPACT 記事検索
おすすめの本〈 広告 〉
-
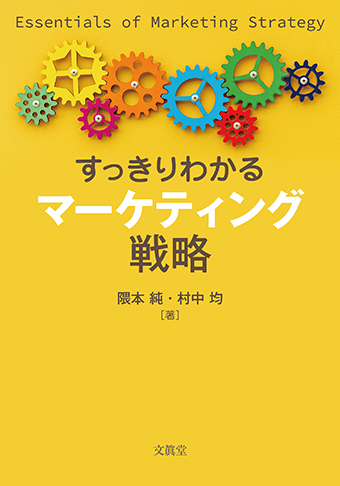 すっきりわかる マーケティング戦略
本体価格:2,000円+税 2023年1月
すっきりわかる マーケティング戦略
本体価格:2,000円+税 2023年1月
文眞堂 -
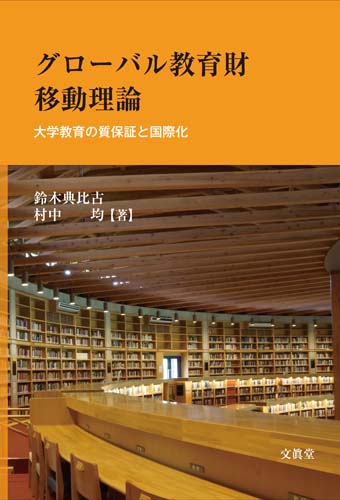 グローバル教育財移動理論:大学教育の質保証と国際化
本体価格:1,950円+税 2014年12月
グローバル教育財移動理論:大学教育の質保証と国際化
本体価格:1,950円+税 2014年12月
文眞堂 -
 サービス産業の国際戦略提携:1976~2022:テキストマイニングと事例で読み解くダイナミズム
本体価格:4,000円+税 2025年8月
サービス産業の国際戦略提携:1976~2022:テキストマイニングと事例で読み解くダイナミズム
本体価格:4,000円+税 2025年8月
文眞堂 -
 中国鉄鋼業:生産システム,企業,産業の三層構造と産業政策
本体価格:4,000円+税 2025年8月
中国鉄鋼業:生産システム,企業,産業の三層構造と産業政策
本体価格:4,000円+税 2025年8月
文眞堂 -
 グローバルサウス入門:「南」の論理で読み解く多極世界
本体価格:2,200円+税 2025年9月
グローバルサウス入門:「南」の論理で読み解く多極世界
本体価格:2,200円+税 2025年9月
文眞堂 -
 職場・学校のセクハラ・パワハラ :ハラスメントの法と判例
本体価格:1,300円+税 2026年1月
職場・学校のセクハラ・パワハラ :ハラスメントの法と判例
本体価格:1,300円+税 2026年1月
文眞堂 -
 高収益経営とアントレプレナーシップ:東燃中原延平・伸之の軌跡
本体価格:3,900円+税 2025年11月
高収益経営とアントレプレナーシップ:東燃中原延平・伸之の軌跡
本体価格:3,900円+税 2025年11月
文眞堂 -
 DEIBにおける経営倫理とCSRの役割:障害者雇用と女性、LGBT、がん患者の方々に焦点を当てて
本体価格:2,700円+税 2025年10月
DEIBにおける経営倫理とCSRの役割:障害者雇用と女性、LGBT、がん患者の方々に焦点を当てて
本体価格:2,700円+税 2025年10月
文眞堂 -
 ルビーはなぜ赤いのか?:川野教授の宝石学講座
本体価格:2,500円+税
ルビーはなぜ赤いのか?:川野教授の宝石学講座
本体価格:2,500円+税
文眞堂 -
 これさえ読めばすべてわかるアセットマネジメントの教科書
本体価格:2,900円+税 2025年9月
これさえ読めばすべてわかるアセットマネジメントの教科書
本体価格:2,900円+税 2025年9月
文眞堂

