世界経済評論IMPACT(世界経済評論インパクト)
問題発見と問題解決を体現するリベラルアーツ
(常磐大学 教授)
2025.04.07
先が読めない時代,Volatility(変動性),Uncertainty(不確実性),Complexity(複雑性),Ambiguity(曖昧性)の英語の頭文字をとってVUCA時代と呼ばれている現在は,変化が速く状況が不安定であり,何が問題であるのか,解決すべき問題は何であるのかの提示が重視されるようになってきている。
よくいわれていることであるが,これまでは問題が設定されている場合が多く,「問題解決」が重視されてきた。しかし上記のように,現在は問題そのものの提示,すなわち「問題発見」が重視されるようになっている。ただし問題を発見できても,それを解決しなくては不十分である。つまり,問題発見そして問題解決という段階のプロセスを経ることが可能でなくてはならない。環境に配慮し先進的な技術を搭載した電気自動車を販売するTESLAや環境に配慮した衣料品を販売するPatagoniaそして環境に配慮したスマートフォンを販売するFairphoneといった「クリティカル・ビジネス」と呼ばれる,これまでとは異なる方向性を示し多くの人が共感する新しい問題を発見し解決していく取り組みが勃興している(山口周『クリティカル・ビジネス・パラダイム』プレジデント社,2024年)。そこで本稿では,問題発見そして問題解決それぞれの段階の内容を精査し,それらをプロセスとして成立させる要因について説明を行ってみたい。
問題発見そして問題解決という段階のプロセスを理解するために,ここで2つの軸,具体的には縦軸を問題(下:ある,上:ない),横軸を解(左:ある,右:ない)としてマトリクスを作成してみると,第1象限は問題ない・解ない,第2象限は問題ない・解ある,第3象限は問題ある・解ある,第4象限は問題ある・解ないとなる。問題ない・解あるの第2象限は状況の可能性が低くここでは考慮せず,問題発見の段階とは,第1象限(問題ない・解ない)から第4象限(問題ある・解ない)に移行させることであり,問題解決の段階とは,第4象限(問題ある・解ない)から第3象限(問題ある・解ある)に移行させることである(同様の見解として,細谷功『問題発見力を鍛える』講談社現代新書,2020年が挙げられる)。
問題発見の段階では,問題そのものを考え新たに物事の枠組みを再定義するため発散させ抽象化していく,批判的に物事を捉えるクリティカルシンキングが肝要となる。問題発見により問題が定義された後は,問題解決の段階であり,この段階では与えられた問題すなわち設定された枠組みで考えるため収束させ具体化していく,根拠に基づき筋道を立てて論理的に分析し説明するロジカルシンキングが肝要となる。
問題発見の段階と問題解決の段階では,必要なものが異なり,クリティカルシンキングとロジカルシンキングの2つを一人の人間として包含するのが,人間そして世界を理解するための専門分野横断的さらにいえば文理融合的な多様性のある知識や経験の総体である「教養」すなわち「リベラルアーツ」である。問題発見と問題解決はそれぞれ異なり,問題発見と問題解決の各段階をつなげ体現するには,リベラルアーツが重要となるのだ。
人間の認知限界から,学問あるいは知識はいわゆる専門分野に枝分かれし(そのことを,タコつぼ化と揶揄されることがある),現在はそれを克服する動きとしてのリベラルアーツの特異性や重要性が指摘されているが,今後のAI(人工知能)の進歩によって,一人の人間として包含する知識の在り方が変化し(例として知識の外部化の容易化),専門分野やリベラルアーツの在り方や考え方が大きく変化していく可能性はあるだろう。
関連記事
村中 均
-
[No.4112 2025.12.08 ]
-
[No.3981 2025.09.08 ]
-
[No.3730 2025.02.17 ]
最新のコラム
-
New! [No.4162 2026.01.12 ]
-
New! [No.4161 2026.01.12 ]
-
New! [No.4160 2026.01.12 ]
-
New! [No.4159 2026.01.12 ]
-
New! [No.4158 2026.01.12 ]
世界経済評論IMPACT 記事検索
おすすめの本〈 広告 〉
-
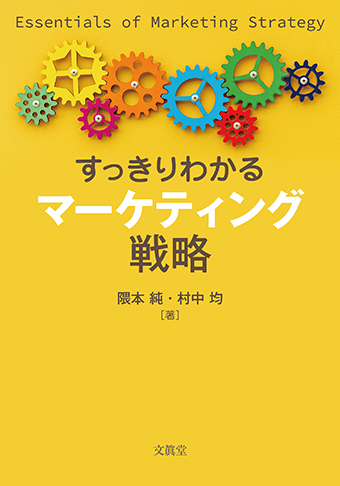 すっきりわかる マーケティング戦略
本体価格:2,000円+税 2023年1月
すっきりわかる マーケティング戦略
本体価格:2,000円+税 2023年1月
文眞堂 -
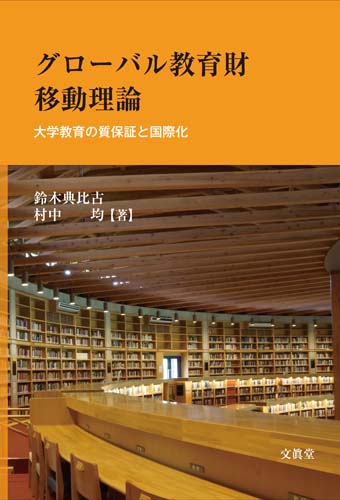 グローバル教育財移動理論:大学教育の質保証と国際化
本体価格:1,950円+税 2014年12月
グローバル教育財移動理論:大学教育の質保証と国際化
本体価格:1,950円+税 2014年12月
文眞堂 -
 国際マーケティングの補助線
本体価格:2,700円+税 2025年9月
国際マーケティングの補助線
本体価格:2,700円+税 2025年9月
文眞堂 -
 職場・学校のセクハラ・パワハラ :ハラスメントの法と判例
本体価格:1,300円+税 2026年1月
職場・学校のセクハラ・パワハラ :ハラスメントの法と判例
本体価格:1,300円+税 2026年1月
文眞堂 -
 これさえ読めばすべてわかるアセットマネジメントの教科書
本体価格:2,900円+税 2025年9月
これさえ読めばすべてわかるアセットマネジメントの教科書
本体価格:2,900円+税 2025年9月
文眞堂 -
 揺らぐサムスン共和国:米中対立の狭間で苦悩する巨大財閥
本体価格:2,700円+税 2025年12月
揺らぐサムスン共和国:米中対立の狭間で苦悩する巨大財閥
本体価格:2,700円+税 2025年12月
文眞堂 -
 高収益経営とアントレプレナーシップ:東燃中原延平・伸之の軌跡
本体価格:3,900円+税 2025年11月
高収益経営とアントレプレナーシップ:東燃中原延平・伸之の軌跡
本体価格:3,900円+税 2025年11月
文眞堂 -
 サービス産業の国際戦略提携:1976~2022:テキストマイニングと事例で読み解くダイナミズム
本体価格:4,000円+税 2025年8月
サービス産業の国際戦略提携:1976~2022:テキストマイニングと事例で読み解くダイナミズム
本体価格:4,000円+税 2025年8月
文眞堂 -
 中国鉄鋼業:生産システム,企業,産業の三層構造と産業政策
本体価格:4,000円+税 2025年8月
中国鉄鋼業:生産システム,企業,産業の三層構造と産業政策
本体価格:4,000円+税 2025年8月
文眞堂 -
 ルビーはなぜ赤いのか?:川野教授の宝石学講座
本体価格:2,500円+税
ルビーはなぜ赤いのか?:川野教授の宝石学講座
本体価格:2,500円+税
文眞堂

