世界経済評論IMPACT(世界経済評論インパクト)
トランプ2.0下の世界とグローバル・サウス:BRICSとIBSAに注目して
(名古屋大学 名誉教授)
2025.07.21
2025年1月に誕生した第2期トランプ政権(トランプ2.0)の打ち出す大統領令は,半年たっても世界に激震をもたらしている。4月2日に貿易相手国に示した一方的な相互関税は,その稚拙さから中国を除いて90日間の延期となったが,その期限が近づくと,この相互関税がトランプによる独善かつ政治優先の「ディール」であることがますます明らかになっている。
こうした中,グローバル・サウス諸国とBRICSの動向が注目されている。これらの国やその集まりはトランプにとって,ヨーロッパの先進国以上に気になる存在と言えそうだ。グローバル・サウスやBRICSは思惑が一致する国の集合体ではなく,しばしばその連携の脆弱性が指摘される。それにも拘わらず彼らはトランプ外交に挑戦し,世界の覇権構造からの多極化で大きな役割を果たしている。
トランプ2.0とBRICS
7月9日に発表された米国の対ブラジル相互関税は4月発表時の10%から50%へと5倍に跳ね上がった。そもそも米国はブラジルに対し貿易黒字を計上しており相互関税の根拠に乏しい。それにも拘らず突出して高い関税率となった。ブラジル大統領に宛てた通告文書には,クーデターを企てた嫌疑で公判中のJ. ボルソナーロ前大統領の裁判を「魔女狩り」裁判として「魔女狩りをやめよ」との要求が記されている。ボルソナーロは「熱帯のトランプ」(‘Trump of the Tropics’)と呼ばれ,2022年の大統領選では敗北を認めずクーデターを企てたとされる人物である。P.クルーグマンは,ブラジルへの高関税には経済的正当性の見せかけすらなく,「もう一人の独裁者を助けるために関税を用いようとする」もので,ブラジルに課される関税は民主主義への制裁措置と捉える(注1)。
この相互関税の通達の3日前の夜,トランプはリオデジャネイロで開催中の第17回BRICSサミットに集まる指導者たちにもソーシャルメディアを通じ警告を発している。「(BRICS)グループの“反米政策”を支持するあらゆる国に対して10%の追加関税をくらわす」との脅しである。サミット開催国ブラジルのルーラ大統領はトランプに対して,「われわれに皇帝はいらない。われわれは主権国家である」と反論し,また「一方的関税引上げに対しては,ブラジルの経済相互主義法に依って対処する」と発表して,相互関税を受入れない立場を表明にしている(日経, 2025.7.8,Financial Times, July 8, 2025,DW, July 8, 2025,ロイター, 2025.7.10)。
今や,トランプの関税政策は経済的な名目を超え,トランプ自身の独裁志向が前面に出るようになった。クルーグマンは,トランプのブラジルへの対応を「独裁者保護プログラム」(Trump’s Dictator Protection Program)と名付けたが,関税はトランプの意に沿わない指導者への制裁手段と化している。そして,その主要な対象国がBRICS諸国である。米中貿易戦争を経て覇権争いの当事国となった中国,さらにはウクライナ侵略戦争を始めたロシア,そしてトランプの世界観に真正面からぶつかる,その他のBRICS加盟国である。
例えば,トランプの南アフリカに対する脅しは見境が無い。トランプは大統領就任後すぐさま南ア援助を停止し,5月21日にホワイトハウスで行われた米・南ア首脳会談では土地政策などで南アが白人を迫害しているとして,証拠とされる動画を見せてラマホーサ大統領に非難を浴びせた。ラマホーサは冷静にその非難に反論したが,迫害の証拠とされる映像は南アのものでなかった。世界の様々な報道機関が,そもそも南アには白人迫害の事実のないことを確認している(BBC, CNN, NHK, 2025, 5, 21- 5. 23)。それでもトランプの南アへの対応は変らない。2025年のG20議長国が南アであるため,本年2月に開催されたG20外相会合にルビオ国務長官は欠席し,7月にダーバンで開催された財務相・中央銀行総裁会議もベッセント財務長官は欠席した。
なお,7月7日に送られた南アへの相互関税書簡では,関税率は30%であった(注2)。
インドもトランプ外交で御し難い国である。インドは米国の対中政策の要となるQuadへの参加国であるが,ロシア制裁には加わらない。中国と共にロシア産資源の輸入国として漁夫の利を得ている。本年4月に米国上院に提出された「2025年ロシア制裁法」はロシアからの石油,ガスなどの資源を輸入する第3国からの輸入に500%の関税を課すというものである。7月に入ってウクライナ停戦に応じないプーチンに不満を募らすトランプは,当初のプーチン寄りから制裁に姿勢を変え始めている。7月14日,トランプは上記法案に沿う形でロシアが50日以内に停戦しなければ,100%の制裁をロシア産資源の輸入国からの輸入品に課すとの発表を行った。ちなみに,2022年2月~25年4月のロシアの原油輸出先国別シェアは中国が47%,インドが38%,トルコが6%である。間違いなく,中国とインドが念頭におかれている(日経, 2025.5.28, 7.15,mint, July 10, 2025,Fox News, July 10, 2025)。
BRICS各国が連携する理由の一つは,米・西側主導の国際秩序に強い不満をもち,その是正を求めることにある。確認すべきは,BRICS諸国が過去半世紀超の経済のグローバル化の中で誕生した,いわば新興国の雄だということである(注3)。それが「グローバル・サウス」の呼称と共に,BRICSを世界に受入れさせたのである。
2024年11月,トランプは,ソーシャルメディアを通じて,ドルの代替通貨を目指すBRICSのあらゆる国からの輸入品に100%の関税を課すと脅したが(Bloomberg News, Dec. 1, 2024)。同様の発言は,大統領に就任すると再びなされた。これに対してロシアは,2024年10月の第16回BRICSサミットで共通通貨の議論はしていない,と正式に発表した(注4)(Reuters, Jan. 31, 2025)。しかし,2023年にはブラジルのルーラ大統領がBRICSの共通通貨を提案しており,BRICSは貿易の振興などを求めて準備通貨としてのドルの代替策を検討してきた。実際,第16回BRICSサミットでは,共通通貨の実現は時機尚早としながらも実態に即した貿易決済制度を追求するとされていた。それ故,ロシアの対応は,腰砕けの印象を与える(注5)。
一方,本年7月の第17回BRICSサミットでは,参加国はドルの国際決済システムであるSWIFTの代替システムの創設に向けて動くことに,正式に合意した(注6)。そして,トランプが「10%の追加関税を近く課す」と発表すると,今度はルーラ大統領がBRICSに新しい貿易通貨の提案で応えた,と直近の報道は伝える(注7)。
中国とロシアを除けば,BRICS原加盟国は決して反米・西側ではない。しかし,国際法や秩序を無視するトランプの一方的な対外政策に,BRICS諸国が米国への不信感を強めたことに変わりはなく,トランプの恣意的ルールに代わる新たな秩序の形成に向けて,その主要な一角にBRICSの国々がいることは間違いない。
グローバル・サウスとBRICS
「グローバル・サウス」の呼称が注目されるようになったのは,今世紀に入ってからであり,とりわけ2010年代以降である。その背景には,移民・難民,人口問題,気候変動,地球温暖化などのグローバルな難題の解決に向けて発展途上諸国の人々が声を上げるようになったことがある。中でも地球温暖化問題は,改めて産業化の過程における先進国の支配と搾取の歴史を思い起こさせる契機となったと言えるだろう。他方で,東アジアの新興国が先頭になって発展し,米国主導の国際秩序のもつ不公平を意識するようにもなった(注8)。2つの潮流が彼らに「グローバル・サウス」の呼称を選ばせたのである。大阪大学のメディア研究機関グローバル・ニュース・ビュー(GNV)のV. ホーキンス博士は,2020~21年の国連気候変動枠組み条約締結国会議(COP26,27)の開催時期にグローバル・サウスの呼称を用いた報道数がピークに達したとしている(注9)。欧米のメディアやアカデミズム,市民運動が受け入れるようになったグローバル・サウスの呼称は,歴史と空間を包み込んだ表記法としてグローバル・サウスの人々に受け入れられたのである(注10)。事実,2023年1月には,インドのモディ首相が「グローバル・サウスの声サミット」を立ち上げている。
ところが,グローバル・サウスの語源は,ゴールドマン・サックスのJ. オニールがブラジル,ロシア,インド,中国の頭文字から作った造語BRICsに求められる。2001年のことである。ただし,ロシア,中国,インドの連携では,当初ロシアのイニシアティブがあった。1998年12月にロシアのY. プリマコフ外相がインド訪問時に,モスクワ,北京,ニューデリーの「戦略的3角形」の構想を提案している(注11)。それから間もなくして,オニールのBRICs論文が登場した。ロシアはブラジルを加えた新興国の対話と協力組織の制度化で,大きな後ろ盾を得たと言えるだろう。
ロシアは,2006年9月の国連総会の折に4カ国の非公式の閣僚会合の設置に動いた。2008年5月にはロシアのエカテリンブルグでの4カ国の外相会合の開催,同年7月の東京でのG8サミットに合わせた外相会合の開催を経て,2009年6月の第1回BRICサミット(注12)の開催につなげた。設立の目的では,「漸進的,積極的,実用的で,開かれた透明性のある方法によって参加国間の対話と協力を促進すること」が謳われた(注13)。BRICは翌年には南アの参加を承認し,2011年からはBRICSサミットとなった。2014年の第6回BRICSサミットでは新開発銀行(NDB)設立のフィージビリティが合意され,翌15年に設立された。通称BRICS銀行である(注14)。サミットは以後,毎年,開催されることになる。2020年代には,BRICSメンバーの拡大に段階を進める。
BRICSとIBSA
ところで,対話・協力組織としてのIBSA(India, Brazil, South Africa Dialogue Forum)の結成と,BRICへの南アの参加ではブラジルのルーラ政権の大きな貢献があった。現在のブラジルのルーラ政権は2023年に始まる第2期の政権である。彼は2003年~2010年に第1期の政権を率いていた。ブラジル政府のBRICS 2025の公式サイトによると,2003年1月のルーラの大統領就任式に参列したインドと南アの高官と会ったブラジルのセルソ・アモリム外相に閃いたのが,IBSAであった。そのアイデアは同年6月初め,フランスのエビアンで開催されたG8サミットにオブザーバーとして参加していたインドのバジパイ首相,ブラジルのルーラ大統領,南アのタボ・ムベキ大統領の3者による会合となり,そこでは農業,環境,WTO,閣僚会合,首脳会議の開催などの様々な課題が話し合われた。かくして,同月のブラジルでのIBSAフォーラムの開催となった(注15)。この時に発せられたIBSAブラジリア宣言は,上記3国がグローバル・サウスに属する多民族,多文化の民主主義国家の共通性を持ち,「多元主義,議会制民主主義,包括的成長と非覇権的世界秩序への決意を共有する国」であるとして,協力を確認している。翌2004年には貧困と飢餓緩和の「IBSA基金」がUNDPと連携して設けられ,2006年には国連南南協力事務所(UNOSSC)によって運営が始まった。IBSA基金は規模が小さいが,開発協力としての「南南協力のパイオニア」となった。2006年9月には第1回IBSAサミットも開かれ,サミットは定例化された。
IBSAは2000年代に精力的に活動を展開した。外相会議は2004年3月に第1回会合を開いて以降,2009年の第6回まで毎年開かれた。その後活動は徐々に低調となるが,第7回が2011年に,第8回と第9回が2017年,2018年に開かれた。サミットも第2回と3回が2007年,2008年,第4回と5回が2010年,2011年に開催された(注16)。
ブラジルは,南アのBRIC参加でも橋渡しをした。ブラジルは2010年のBRICサミット開催国であった。開催月の同年4月,リオデジャネイロ市の主催で第1回IBSA-BRICセミナーを開催し,続いてブラジル政府がブラジリアで第2回BRICサミットと第4回IBSAセミナーを同時開催した(注17)。南アはアフリカの地域大国であり,BRICへの参加を働きかけていた(注18)。ブラジルは南アのBRIC加盟で相互理解の場を提供し,2011年の第3回サミットは南アが加わるBRICSサミットとなったのである。開催国の中国も,南アの加盟に積極的であった。
ただし,IBSAの活動は,BRICSの活発な活動と対照的にその後は低調となる。IBSAは南南協力で先駆的な存在であったが,BRICSと活動が重なる(注19)。改めてIBSAが注目されるようになるのは2020年代に入って,拡大BRICS(BRICS+)に動くことになってからである。
拡大BRICS(BRICS+)と参加国問題
BRICS加盟国の拡大では,中国が2017年にその動きを始める(注20)。ただし,具体的に動き始めるのは2022年である。中国主催の同年6月の第14回BRICSサミット(オンライン)において参加国の拡大が合意され,翌23年8月の南ア・ダーバンでの第15回BRICSサミットには,候補国としてアルゼンチン,エジプト,エチオピア,イラン,サウジアラビア,UAEの6カ国が招待された。翌24年1月にはアルゼンチンが辞退したため,ロシアのカザンで開催された同年8月の第16回サミットは10カ国のBRICS+サミットとなった。なお,サウジアラビアは公式ページでは加盟国扱いになっているが,留保の立場をとり続けている(注21)。また,カザン・サミットでは,パートナー国制度が設けられ,13カ国がパートナーとして正式参加(注22)している。インドネシアは翌25年1月にパートナー国から格上げされ加盟国となった。本年7月のリオデジャネイロの第17回BRICSサミットの加盟国数は11カ国,それにパートナー国が加わる。
BRICS加盟国の拡大,BRICS+では国際情勢が大きく関係している。中国のBRICS+の方針は2017年に出されたが,この年は第1期トランプ政権が誕生している。2022年はロシアがウクライナに軍事侵攻し,西側の経済制裁を受けるロシアは孤立を防ぐ外交が必要となっていた。実際,拡大BRICSの積極派はロシアと中国だった。これに対して,ブラジル,インド,南アの3カ国は慎重派であった。結果的には,中国とロシアの意向が通ったが,23年のダーバン・サミットの準備段階では,3カ国の代表がBRICS拡大のペースと範囲に関して慎重さを要求している(注23)。中国の影響力が増すことによるBRICSの反米・西側化を警戒する見方があり,また確かにそうした国々の参加もあるが,多くの参加国はむしろ多角外交を目指し,トランプ・ヘッジ,また一部は中国ヘッジとしてBRICS+を捉えている(注24)。実際,BRICSへの対応でサウジアラビア,また招待されたベトナムも慎重である。両国とも,貿易関係で中国と米国への依存度が極めて高い。BRICSの中国化がとりわけ注目されているが,BRICSの多数派の期待は米中双方へのヘッジである。だからこそBRICS参加国の多くが,反米・西側以外に南南協力を重視し,グローバル・サウスの雄としてのBRICSへの期待を高め,そして,IBSAが再認識される条件が生まれたのである。
BRICS+とIBSAの再認識
BRICSの政治化で再注目を集めるのがIBSAである。インドの外交雑誌The Diplomatistは,2003年の初のIBSA閣僚会合からの20年を振り返り,南南協力を主目標に据え,アジア,アフリカ,アメリカの3大陸を連結するIBSAの意義に光を当てた。同誌の論文は,BRICSの陰で「なぜIBSAは今日,透明化されているのか」と問い,その歴史を再確認する。最後のIBSA3カ国閣僚会合は2017年であり,また第5回IBSAサミットは2011年で途絶えていた。2022年11月,G20サミットの議長国であったインドはこれを機に第6回IBSAサミットをG20サミットに合わせて開催した。24年9月には第79回国連総会に合わせてIBSAの3カ国外相会合を開き,「貧困と飢餓の闘いが優先課題であり,(それが)IBSA国家間の長期の協力分野である」ことを確認した。その論文の執筆者であるA. N. ロイは,前年に発表されたブラジル・サンパウロのジェトゥリオ・ヴァルガス財団(FGV)のO. ストゥエンケル(注25)によるIBSAの現状とそれを取り巻く環境を振り返る論文に触発されながら「IBSAを復活させるべきだ」との主張を展開している(注26)。
ロイは,IBSAの影響力が落ちているというストゥエンケル論文を要約しながら,(1)過去3年間にBRICSが根本的に変わった。(2)トランプの予測不能な政策への対応が必要となった。(3)民主主義が直面する主要な課題の解決でIBSAの重要性が増した。さらに,(4)IBSAはグローバル・サウスの組織であるが,「BRICSは違う」,「IBSAのメンバーが良いBRICSだ」としてその復権を主張する(注27)。
実際,2024年の拡大BRICSでは,コンセンサスが難しくなった。同年4月の外相会談では共同声明をまとめられなかった。これは同外相会議で初の出来事であった。サミットでロシアはドルの代替政策を強く求めたが,他の参加国の多くは関心が薄かった。設立時には新興勢力(an emerging power)であった中国は今や超大国(a great power)となり,グローバル・サウスを代表してのBRICSのスピーチの能力が複雑化しているなどが挙げられている。国連安全保障理事会改革では,常任理事国のロシアと中国がインド,ブラジル,南アが切望する常任理事国の拡大に反対し続けている(注28)。
2023年8月のBRICSサミットでは,中国が米国バイデン政権による「デカップリング」や「経済的威圧」への反対を表明し,サミットに招待された国の指導者たちと会談を重ねたが,インドで開催された翌月のG20サミットには参加しなかった。ところが,インドは2023年1月に「グローバル・サウスの声」サミット(オンライン)を開催し,125カ国を集めた。同年9月のG20の議長国として,インドはアフリカ連合のG20の正式メンバー化を実現した。同年11月にはCOP28の直前に第2回「グローバル・サウスの声」サミットを開催し,グローバル・サウスの代表を任じて彼らの声を会議に届けた(注29)。米国からの地経学的圧力が強まる中で,中国がロシアとの連携を強め,対抗姿勢を強めるのと対照的に,IBSA諸国はG20を重視し,貧困削減や環境問題などで南南協力を重視する姿勢を強めている。
こうしたIBSAの姿勢は,BRICSの拡大以前の目標と重なる。IBSA基金もその規模は,NDBに遠く及ばないが,IBSAの意義を再確認させるものである。ウクライナ戦争後のロシアと中国の「上限の無い連携」は一方で確かにBRICSの反米・西側の性格を強めているように見える。だが他方で,BRICS参加国の多くは西側との連携を維持するインドやブラジルの立場に近いと言ってよい(注30)。彼らは,G20などの西側諸国との関係を切ろうとはしていない。BRICSの反米・西側の論調は全体像を見ているとは言えない。
おわりに
トランプ2.0は,いよいよ権威主義的な統治の性格を見せつけている。彼のブラジルへの追加関税措置の通告からは,彼のグローバル・ガバナンス観が透けて見える。権威主義国はもちろん権威主義的傾向を見せる国はプーチンのロシアはもちろん,ヨーロッパでもグローバル・サウスでも勢いを増している。IBSAのうちブラジルでは2019年から22年までトランプが擁護したボルソナーロ政権が権力を握っていた。モディ政権が続くインドも,その実像は彼の大国幻想と結びついた権威主義国家だとする見方もある(注31)。
BRICSの原加盟国であるブラジル,インド,南アフリカの3カ国は,3大陸の新興経済の中堅国で制度的には民主主義国家である。トランプ2.0のBRICS制裁は,それらの国を中ロ主導のBRICSへと推し進める傾向を強める。だが,グローバル・サウスの国々が求めているのは,BRICSとの連携を通じた経済的価値の追求である。それに応える点で優位にあるのは一帯一路(BRI)を展開する中国ではあるが,米国に代わる中国ではない。民主主義を維持するIBSAは,公正なグローバル・ガバナンスの要求で優位な立場に立つ。グローバル・サウスの多くの国はIBSAのような国を盛り立てることによって,超大国への対抗軸を得るのである。実際,2023年以降,中国はグローバル・サウスの一員である,との立場を強調するようになった。グローバル・サウスとBRICSの正当性は,IBSAが求めてきた南南協力を強調することによってのみ得られる。世界的な構造変化は,西側諸国との関係を維持するIBSA3カ国の側により大きくグローバル・サウスの正当性を与えているのである。
権威主義を強めるトランプ2.0から目を離せない。だが同時に,BRICSとIBSAなどグローバル・サウスの動向を同様に注視する必要があるだろう。
[注]
- (1)Krugman, P. (2025) Trump’s Dictator Protection Program, July 10.
- (2)JETRO(2025)ビジネス短信「トランプ大統領,南アからの対米輸出品に30%の関税課すと通知」,7月9日
- (3)BRICSへの一般的な関心は,人口,資源,広い国土面積,経済成長率などを持つ国であと説明される。だが共通する経済構造をもってはいない。BRICSの本質は資本活動のグローバル化の中で資本の進出先として,外部から見た優位性に発展の特徴を見るべきだろう。筆者は,そうした経済群を潜在的大市場経済(PoBMEs)と呼んでその特徴を捉えようとした。最も詳しい分析は以下の文献で行った。Hirakawa, H. and Ferdinand C. Maquito (2024) The Dynamics of Asian Economic Development, Springer.
- (4)TASS (2025) BRICS not discussing creation of common currency – Kremlin, Russian News Agency, January 31.
- (5)Demarais, A. (2024) Russia’s Plans to Replace the Dollar are Going Nowhere, Foreign Policy, November 18, 2024.
- (6)Janeiro, Rio De and Rodrigo Chagas (2025) De-Dollarization: BRICS leaders propose creating an alternative payment system to SWIFT, Brasil de Fato, July 7.
- (7)前掲注6 Jeneiro, R.D. and R. Chagas (2025).
- (8)20世紀中ごろから発展途上世界を指して使われるようになった様々な呼称,発展途上諸国,第3世界,「南」,「グローバル・サウス」については,平川均(2024a)「『グローバル・サウス』の背景に何があるか」世界経済評論IMPACT,No.3442,6月3日の他,(2024b)「グローバル・サウスと求められる新たな世界認識」世界経済評論 IMPACT,No.3663,12月16日。平川均(2025a)「拡大BRICSとグローバル・サウスの今日的意義」世界経済評論 IMPACT,No.3746,3月3日,(2025b)「ASEANの進路とBRICSへの参加」世界経済評論,Vol.69, No.4,7/8月号,(2025c)「トランプ2.0とグローバル・サウス」ピープルズ・プラン研究所
- (9)ホーキンス,V.(2023)「『グローバル・サウス』が何故頻出するようになったのか?」Global News View(GNV),8月7日。
- (10)前掲注8(平川2024c)。
- (11)Daniel, R. and K. Virk (2014) BRICS and IBSA (India, Brazil, and South Africa), in South Africa and the BRICS, Center for Conflict Resolution.
- (12)筆者はこれまで同サミットを第1回~2回をBRICsサミット,第3回以降をBRICSサミットと表記してきた。本稿では,第1回と2回をBRIC,第3回以降をBRICSに表記法を改めた。蛇足だが,当初のサミットをBRICsとしたのは,サミット名の語源となったJ. O’NeillのペーパーのBRICsに倣ったためである。Jim O‘Neill (2001) Building better Global Economic BRICs, Goldman Sachs Global Economics Paper, No.66, November 30.
- (13)Joint website of the Ministries of Foreign Affairs of the BRICS member States, History of BRICS.
- (14)前掲注8(平川2025a,b,c)。
- (15)Stuenkel, Oliver (2025) BRICS Democracies Are Losing Leverage, Foreign Policy, May 20.
- (16)India, Brazil, South Africa Forum 公式サイトAbout IBSA.
- (17)Franciéli Barcellos de Moraes (2025) Fifteen years ago, Brasil hosted the BRICS Summit for the first time.
- (18)細井友裕(2025)「南アフリカとBRICSの不安定な関係」世界経済評論,Vol.69, No.4,7/8月号。
- (19)Mukherjee, A. and C. Arkalji (2024) Revitalizing IBSA: India, Brazil, and South Africa, The Observer Research Foundation America (ORF America), November 7.
- (20)中国の王毅外相が,2017年3月9日の第12回全国人民代表大会第5次会議において,「我々は南南協力のための新たなプラットフォームを構築する。・・・BRICS協力を今日の南南協力における世界で最も影響力のあるプラットフォームとする」と報告している。なお,引用は山口信治(2025)「中国とBRICS拡大」世界経済評論,Vol.69, No.4,7/8月号による。
- (21)石油輸出国としての同国の地政学的重要性がBRICSとして曖昧な対応を取らせていると言えるだろう。
- (22)パートナー国となった13カ国は,インドネシア,タイ,ベトナム,マレーシア,ウズベキスタン,カザフスタン,ベラルーシ,トルコ,アルジェリア,ナイジェリア,ウガンダ,ボリビア,キューバである。
- (23)Patrick, S. (2024) BRICS Expansion, the G20, and the Future of World Order, Carnegie Endowment for International Peace, October 9.
- (24)ASEANのBRICS参加については前掲注8(平川 2025b)を参照。
- (25)Stuenkel, Oliver (2025) BRICS Democracies are Losing Leverage, Foreign Policy, May 20.
- (26)Roy, Ash Narain (2025) Treat IBSA as good BRICS, the Diplomatist, June 16.
- (27)前掲注26(Roy 2025)。
- (28)前掲注23(Patrick 2024)。
- (29)前掲注8(平川 2024b)。
- (30)前掲注25(Stuenkel 2025)。
- (31)湊一樹(2024)『「モディ化」するインド-大国幻想が生み出した権威主義-』中央公論新社。
関連記事
平川 均
-
[No.4110 2025.12.01 ]
-
[No.3746 2025.03.03 ]
-
[No.3663 2024.12.16 ]
最新のコラム
-
New! [No.4194 2026.02.02 ]
-
New! [No.4193 2026.02.02 ]
-
New! [No.4192 2026.02.02 ]
-
New! [No.4191 2026.02.02 ]
-
New! [No.4190 2026.02.02 ]
世界経済評論IMPACT 記事検索
おすすめの本〈 広告 〉
-
 一帯一路の政治経済学:中国は新たなフロンティアを創出するか
本体価格:3,400円+税 2019年9月
一帯一路の政治経済学:中国は新たなフロンティアを創出するか
本体価格:3,400円+税 2019年9月
文眞堂 -
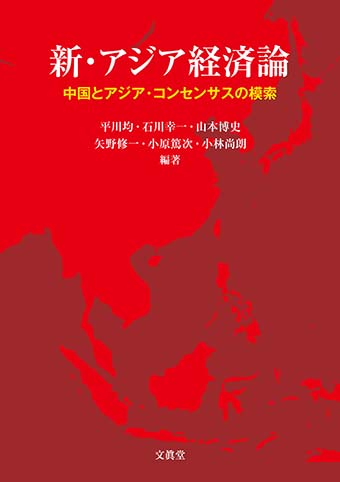 新・アジア経済論:中国とアジア・コンセンサスの模索
本体価格:2,800円+税 2016年2月
新・アジア経済論:中国とアジア・コンセンサスの模索
本体価格:2,800円+税 2016年2月
文眞堂 -
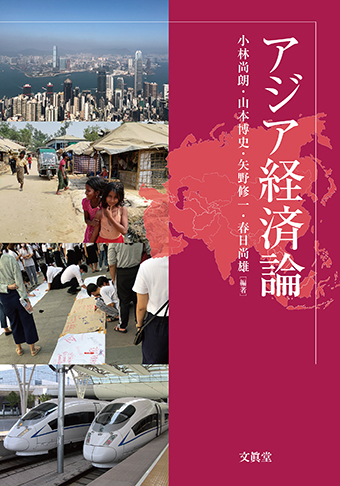 アジア経済論
本体価格:2,600円+税 2022年3月
アジア経済論
本体価格:2,600円+税 2022年3月
文眞堂 -
 創造力強化経営の実践
本体価格:2,200円+税
創造力強化経営の実践
本体価格:2,200円+税
文眞堂 -
 これさえ読めばすべてわかるアセットマネジメントの教科書
本体価格:2,900円+税 2025年9月
これさえ読めばすべてわかるアセットマネジメントの教科書
本体価格:2,900円+税 2025年9月
文眞堂 -
 高収益経営とアントレプレナーシップ:東燃中原延平・伸之の軌跡
本体価格:3,900円+税 2025年11月
高収益経営とアントレプレナーシップ:東燃中原延平・伸之の軌跡
本体価格:3,900円+税 2025年11月
文眞堂 -
 揺らぐサムスン共和国:米中対立の狭間で苦悩する巨大財閥
本体価格:2,700円+税 2025年12月
揺らぐサムスン共和国:米中対立の狭間で苦悩する巨大財閥
本体価格:2,700円+税 2025年12月
文眞堂 -
 中国鉄鋼業:生産システム,企業,産業の三層構造と産業政策
本体価格:4,000円+税 2025年8月
中国鉄鋼業:生産システム,企業,産業の三層構造と産業政策
本体価格:4,000円+税 2025年8月
文眞堂 -
 職場・学校のセクハラ・パワハラ :ハラスメントの法と判例
本体価格:1,300円+税 2026年1月
職場・学校のセクハラ・パワハラ :ハラスメントの法と判例
本体価格:1,300円+税 2026年1月
文眞堂 -
 グローバルサウス入門:「南」の論理で読み解く多極世界
本体価格:2,200円+税 2025年9月
グローバルサウス入門:「南」の論理で読み解く多極世界
本体価格:2,200円+税 2025年9月
文眞堂

