世界経済評論IMPACT(世界経済評論インパクト)
トランプ相互関税交渉,7月末まで延長
(桜美林大学 名誉教授・国際貿易投資研究所 客員研究員)
2025.07.14
トランプ大統領は7月7日,中国を除き(注1),相互関税の適用停止期限を7月9日から7月末日まで延長する大統領令に署名した。同大統領令では,その根拠として「さまざまな政府高官からの追加情報と勧告によった」としているが,90日間の相互関税交渉で合意に達したのは,英国とベトナムの二ヵ国だけでしかなかったことが主因であることは間違いない。なお,英国との交渉合意は5月8日のホワイトハウスのサイトにその協定(EPD)の詳細が掲載されている(世界経済評論インパクト6月2日付拙稿No.3850参照)。しかし,おかしなことに,ベトナムとの合意については,ホワイトハウスにもUSTRにも商務省にも詳細が掲載されていない。
また,ホワイトハウスは7月7日付で掲載した「ファクトシート」(Fact Sheet: President Donald J. Trump Continues Enforcement Tariffs and Announces New Tariff Rates)で,14ヵ国に対して8月1日から適用する各国別の相互関税率を明示し,7月31日までの間にこれら各国が米国との交渉で関税および非関税障壁の削減・撤廃に向けて交渉を促進するよう求めている。8月1日から実施する相互関税率が,4月2日に発表した相互関税率と比べて,高くなった国(2ヵ国),低くなった国(8ヵ国),同じ国(4ヵ国)の内訳は下記の通りだが,なぜこのような差異が出るのか,ファクトシートは全く説明していない。そもそも,4月2日,ホワイトハウスのローズガーデンで,トランプ大統領が聴衆を前に意気揚々と発表した「相互関税率」なるものが,「米国の当該国との貿易赤字額を米国の当該国からの輸入額で割った値(%)をほぼ半分にしたもの」という,実に恣意的かつ杜撰で,根拠に乏しい数値であるから(同拙稿4月7日付No.3790参照),8月1日から実施するという税率も,その根拠を問うだけ野暮ということになる。
- ①8月1日から適用予定の相互関税率が4月2日発表のものより高くなった国〔2ヵ国〕:日本(4月2日の相互関税率24%から8月1日適用予定の相互関税率25%),マレーシア(日本と同じ)。
- ②同じく低くなった国〔8ヵ国〕:カンボジア(49%→36%),バングラデシュ(37%→35%),カザフスタン(27%→25%),チュニジア(28%→25%),セルビア(37%→35%),ラオス(48%→40%),ミャンマー(44%→40%),ボスニア・ヘルツェゴビナ(35%→30%)。
- ③同じく同率の国〔4ヵ国〕:韓国(共に25%),タイ(36%),インドネシア(32%),南ア(30%)(注2)。
上記14ヵ国のうち,8月1日からの相互関税が最も高い国はラオスとミャンマー(共に40%),次いでタイとカンボジア(同36%),バングラデッシュとセルビア(同35%)など東アジア諸国に集中している。なお,ファクトシートは,上記14ヵ国には7月7日付で大統領が書簡を送ったが,今後(the coming days and weeks)にさらに書簡(more letters)を送る可能性があると書いているが,書簡は何カ国に送られるのか,各国に対する相互関税は何%なのかなどについては一切明らかにしていない(注3)。また,この大統領書簡はトランプ大統領のSNS(Truth Social)に,その内容が書かれているというが,なぜ自分のSNSにだけ発表するのか,大統領の書簡は公的文書であるから,なぜホワイトハウス,USTR,商務省のサイトにこの書簡を公表しないのか。これは全く不可解。これは,関税問題に関するトランプ大統領の独裁者ぶりを如実に示している。
日本は妥協せず,トランプ関税の不当性を一貫して主張すべし
トランプ大統領が石破首相に送った書簡を内外のメディアなどが報じたもので読むと,トランプ大統領の対日貿易不均衡に対する強い不満と日本に対する是正の要求の強さが行間から溢れている。トランプ大統領は書簡で,「日米間の貿易は相互的ではない。8月1日から適用する相互関税25%(only 25%と書いている)は,米国の対日貿易不均衡を解消するには低すぎる」,「米国の対日貿易赤字が米国の経済と安全保障に重大な脅威となっている」,「長年にわたる日本の関税,非関税政策および貿易障壁を是正するために相互関税が必要なのだ」,としている。
その一方,「日本の対応次第で25%の相互関税率は高くなることも,低くなることもある」と,交渉による日本側の譲歩を求め,「日本が何らかの理由で輸入関税を引き上げた場合(注:報復関税の実施を意味する),その引き上げ分は25%に上乗せされる」として報復関税を発動しないよう忠告し,されに,「第三国製品が,米国の高関税を回避するため日本で積み替えられた場合は,米国は高関税を課す」といった対抗措置を明言している。
相互関税の対米交渉は,7月末までの僅か1ヵ月弱となった。我が国が筋を曲げずに主張を貫くか,妥協の道を求めるか。石破首相はこれまで7回に亘って,赤澤経済再生相をワシントンに送り,相互関税,自動車,鉄鋼等のセクター別関税など,一連のトランプ関税の全てについて,その不当性を訴え,是正を求めて来た。7月中という残された最後の局面においても,石破政権には,自由貿易主義の旗を降ろさず,主張の一貫性を貫いていただきたいと思う。なお,相互関税は,トランプ大統領の恣意的適用だけでなく,法的脆弱性も問題として挙げられている(注4)。
[注]
- (1)中国は90日間の相互関税適用停止の対象外。5月12日の大統領令14298による個別の関税停止措置を実施中。
- (2)ホワイトハウスに掲載されているファクトシートには,8月1日から各国別に適用する相互関税率しか書かれていないので,この内容は7月7日付ニューヨーク・タイムズの記事(Here Are Trump’s New Tariff Threats)によった。なお,14ヵ国に対する相互関税率は,米国と合意したベトナムに対する相互関税の20%をいずれも大幅に上回っている。
- (3)7月9日にはフィリピン,ブルネイ,モルドバ,アルジェリア,イラクおよびリビアの6ヵ国にトランプ書簡が送付されたという。
- (4)トランプ相互関税の法的脆弱性は,5月28日に米国の国際貿易裁判所が下した相互関税措置は国際緊急経済権限法(IEEPA)に違反するとの判決にある。トランプ政権は即日,連邦巡回区控訴裁判所に控訴し,翌29日,控訴裁は国際貿易裁判所の判決を一時停止し,6月10日,審理終了まで一時停止の継続を認めた。これに関する控訴裁の審理は7月31日の予定(ジェトロビジネス短信「米連邦控訴裁,最終判断出るまでIEEPA関税の継続認める」参照)。
関連記事
滝井光夫
-
[No.4141 2025.12.22 ]
-
[No.4109 2025.12.01 ]
-
[No.4030 2025.10.13 ]
最新のコラム
-
New! [No.4209 2026.02.09 ]
-
New! [No.4208 2026.02.09 ]
-
New! [No.4207 2026.02.09 ]
-
New! [No.4206 2026.02.09 ]
-
New! [No.4205 2026.02.09 ]
世界経済評論IMPACT 記事検索
おすすめの本〈 広告 〉
-
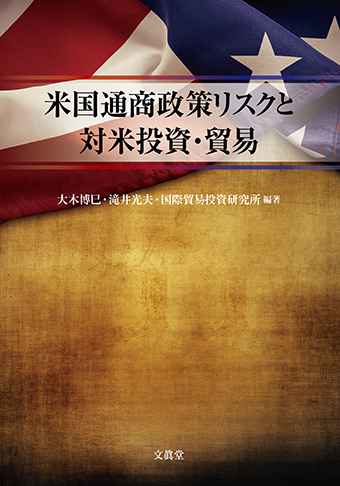 米国通商政策リスクと対米投資・貿易
本体価格:3,000円+税 2018年8月
米国通商政策リスクと対米投資・貿易
本体価格:3,000円+税 2018年8月
文眞堂 -
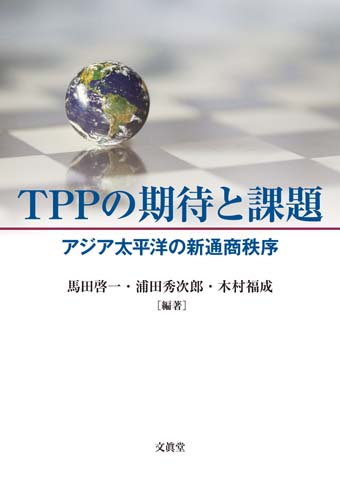 TPPの期待と課題:アジア太平洋の新通商秩序
本体価格:2,750円+税 2016年10月
TPPの期待と課題:アジア太平洋の新通商秩序
本体価格:2,750円+税 2016年10月
文眞堂 -
 ルビーはなぜ赤いのか?:川野教授の宝石学講座
本体価格:2,500円+税
ルビーはなぜ赤いのか?:川野教授の宝石学講座
本体価格:2,500円+税
文眞堂 -
 中国鉄鋼業:生産システム,企業,産業の三層構造と産業政策
本体価格:4,000円+税 2025年8月
中国鉄鋼業:生産システム,企業,産業の三層構造と産業政策
本体価格:4,000円+税 2025年8月
文眞堂 -
 高収益経営とアントレプレナーシップ:東燃中原延平・伸之の軌跡
本体価格:3,900円+税 2025年11月
高収益経営とアントレプレナーシップ:東燃中原延平・伸之の軌跡
本体価格:3,900円+税 2025年11月
文眞堂 -
 サービス産業の国際戦略提携:1976~2022:テキストマイニングと事例で読み解くダイナミズム
本体価格:4,000円+税 2025年8月
サービス産業の国際戦略提携:1976~2022:テキストマイニングと事例で読み解くダイナミズム
本体価格:4,000円+税 2025年8月
文眞堂 -
 DEIBにおける経営倫理とCSRの役割:障害者雇用と女性、LGBT、がん患者の方々に焦点を当てて
本体価格:2,700円+税 2025年10月
DEIBにおける経営倫理とCSRの役割:障害者雇用と女性、LGBT、がん患者の方々に焦点を当てて
本体価格:2,700円+税 2025年10月
文眞堂 -
 揺らぐサムスン共和国:米中対立の狭間で苦悩する巨大財閥
本体価格:2,700円+税 2025年12月
揺らぐサムスン共和国:米中対立の狭間で苦悩する巨大財閥
本体価格:2,700円+税 2025年12月
文眞堂 -
 創造力強化経営の実践
本体価格:2,200円+税
創造力強化経営の実践
本体価格:2,200円+税
文眞堂 -
 グローバルサウス入門:「南」の論理で読み解く多極世界
本体価格:2,200円+税 2025年9月
グローバルサウス入門:「南」の論理で読み解く多極世界
本体価格:2,200円+税 2025年9月
文眞堂
