世界経済評論IMPACT(世界経済評論インパクト)
なぜ日本の米作コストは異常に高いのか:大規模な農地改革に再度取り組むときが来た
(元文京学院大学 客員教授)
2025.05.12
私は国際ビジネスを専門とする者で,農業政策につては全くの素人である。
しかし昨今の日本での米価高騰の騒ぎを聞くにつけ,これは日本の10年先20年先を考えると黙っていられないと考え,一言申し上げたくなり筆をとった。
まず申し上げたいのは,今マスコミで連日取り上げられているのは,政府が貯蔵米を放出したが一向に米の市価が下がらないとか,放出米が末端の小売に届いていないことである。そうしたことを取り上げるのはいいのだが,「なぜ日本の米作コストが世界の標準価格の2倍程度もするのか」という根本的なことに国会もマスコミも問題として取り上げメスを入れようとしていないのはなぜなのか。最近では韓国への旅行者が土産に米を持って帰るのが増えているという。かの地では約半額で買えるからだという。なぜ韓国ではそんな低コストで作れて日本ではできないのか。日本では「米作は聖域」でこの問題に触れるのはタブーになっているのだという話を聞く。
聞くところによるとこの問題は政治家達が保守であれ革新であれ農民が現体制維持を望んでいて,彼らの票田を獲得するために,過去の日米通商交渉でも「米は例外措置」としてかたくなに現在の体制を守ってきたと聞いた。今大問題になっている米国による関税引き上げを発端とする通商交渉においてトランプ大統領もこの米価高の問題を取り上げている。
コメは日本人にとって主食であり国産で賄うという政策は理解できる。
しかし国際相場の約2倍の価格の物を国民におしつけたままでよいのか。又今のコメ作りの体制で今後国内の需要を満たしていけるのか懸念されている。
零細農家の高齢化,後継者不足があるからである。
ではなぜ日本の稲作はかかる状態になったのか,農業には素人であるが,私が理解するところでは,根本的には第二次大戦後の米占領軍による農地解放政策にあったのではないかと考えている。
大地主所有の農地を小作人に一軒当たり3〜5へクタールに細分化して与えたのである。
アメリカ流の平等主義がそこにはあったという説がある。一方日本を弱体化させる施策であったという説もある。問題は稲作も経済活動の一つであって,収益を生めるようにするにはビジネスユニットとして50〜100へクタール程度の「経済規模」というのがあることが無視されていた点にあるように思う。むろん日本が山あり谷ありの山岳地帯であり,平地でそれだけのまとまった農地を造るのは困難な地域があるのは承知している。
ある経済研究所の試算によると50へクタールに集約して米を作ると3〜5へクタールの家族零細農家が作った場合の約半分のコストでできるという。
零細農家も後継者不足から土地を手放す,または第三者に貸したいと考える者も相当数出てきていると聞いている。こうした零細な土地を経済規模にまで集約して会社組織で稲作に取り組む事例もかなり出てきているようだ。
日本はこうした流れを取り込んで,この際思い切って零細農家の土地を集約して,経済規模の生産体制に変革する「大規模な農地改革」を断行する時期に来ているのではないか。もちろん土地の売却や貸すことを促す施策は必要であろう。米作りビジネスの今後の持続性に不安を感じている零細農家にとってはこのような戦略の転換をむしろ歓迎する人もかなりの数いるのではないかと思う。
これによって,休耕地を再び青田にし,コストの下がった日本米を和食ブームに沸く世界に輸出するのである。日本が開かれた多国間貿易の旗手として,これから世界を引っ張って行こうとしたいのであれば,いつまでも「コメは聖域」などと言い続けることは出来なくなると思う。
ところでこうした議論が最近国会の場でなされたということは寡聞にして聞かない。地方再生が議論されているが,本腰を入れてやろうとするのであれば,この問題から避けて通るわけにはいかないと私は考えている。
「国家百年の計」を提唱する政治家,官僚が日本にもそろそろ出てきてもいいのではないか,と思う日々である。
関連記事
小林 元
-
[No.3928 2025.08.04 ]
-
[No.3679 2024.12.30 ]
-
[No.3476 2024.07.01 ]
最新のコラム
-
New! [No.4178 2026.01.19 ]
-
New! [No.4177 2026.01.19 ]
-
New! [No.4176 2026.01.19 ]
-
New! [No.4175 2026.01.19 ]
-
New! [No.4174 2026.01.19 ]
世界経済評論IMPACT 記事検索
おすすめの本〈 広告 〉
-
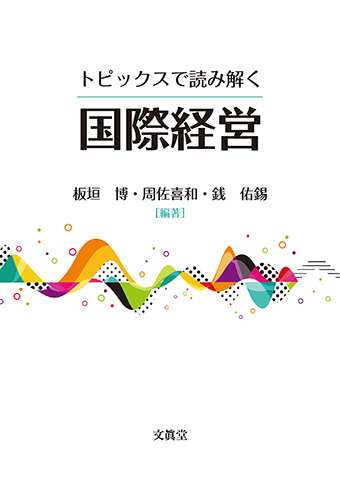 トピックスで読み解く国際経営
本体価格:2,800円+税 2023年9月
トピックスで読み解く国際経営
本体価格:2,800円+税 2023年9月
文眞堂 -
 東日本大震災後の協同組合と公益の課題
本体価格:3,200円+税 2015年10月
東日本大震災後の協同組合と公益の課題
本体価格:3,200円+税 2015年10月
文眞堂 -
 揺らぐサムスン共和国:米中対立の狭間で苦悩する巨大財閥
本体価格:2,700円+税 2025年12月
揺らぐサムスン共和国:米中対立の狭間で苦悩する巨大財閥
本体価格:2,700円+税 2025年12月
文眞堂 -
 中国鉄鋼業:生産システム,企業,産業の三層構造と産業政策
本体価格:4,000円+税 2025年8月
中国鉄鋼業:生産システム,企業,産業の三層構造と産業政策
本体価格:4,000円+税 2025年8月
文眞堂 -
 グローバルサウス入門:「南」の論理で読み解く多極世界
本体価格:2,200円+税 2025年9月
グローバルサウス入門:「南」の論理で読み解く多極世界
本体価格:2,200円+税 2025年9月
文眞堂 -
 国際マーケティングの補助線
本体価格:2,700円+税 2025年9月
国際マーケティングの補助線
本体価格:2,700円+税 2025年9月
文眞堂 -
 DEIBにおける経営倫理とCSRの役割:障害者雇用と女性、LGBT、がん患者の方々に焦点を当てて
本体価格:2,700円+税 2025年10月
DEIBにおける経営倫理とCSRの役割:障害者雇用と女性、LGBT、がん患者の方々に焦点を当てて
本体価格:2,700円+税 2025年10月
文眞堂 -
 ルビーはなぜ赤いのか?:川野教授の宝石学講座
本体価格:2,500円+税
ルビーはなぜ赤いのか?:川野教授の宝石学講座
本体価格:2,500円+税
文眞堂 -
 サービス産業の国際戦略提携:1976~2022:テキストマイニングと事例で読み解くダイナミズム
本体価格:4,000円+税 2025年8月
サービス産業の国際戦略提携:1976~2022:テキストマイニングと事例で読み解くダイナミズム
本体価格:4,000円+税 2025年8月
文眞堂 -
 これさえ読めばすべてわかるアセットマネジメントの教科書
本体価格:2,900円+税 2025年9月
これさえ読めばすべてわかるアセットマネジメントの教科書
本体価格:2,900円+税 2025年9月
文眞堂

