世界経済評論IMPACT(世界経済評論インパクト)
欧州はコストプッシュ型,米国はディマンドプル型のインフレ
(国際貿易投資研究所 客員研究員・元帝京大学 教授)
2022.12.05
「霧のなかでアルプスを山登りするハイカーがその頂上を見極めるのが難しいように欧州の通貨政策担当者もその判断に苦しんでいる」とロンドン・エコノミストは指摘する。フランス中央銀行総裁フランソワ・ビルルワ(François Villeroy)はユーロ・ファイナンス日仏東京会合で日米欧のインフレ・ターゲット目標が一致しているものの,その状況は3者異なり政策内容も違っていると述べた。ECB(欧州中央銀行)チーフ・エコノミストのフィリップ・レイン(Philip Lane)もECBとFRB(米国連邦準備制度理事会)はインフレの内容が米国ではディマンドプル型,欧州ではコストプッシュ型であり,財政政策と金融政策のスウィート・スポット,即ち財政金融のミックスポリシーのどの点がもっとも効率的であるかについての均衡点を見出すのに政策当局者は目を光らせていると指摘。今回の世界的なインフレーションは物価水準と失業率のマイナスの相関関係や,ルールか政策的裁量かという財政金融政策に関するスタンスの違いを浮き彫りにさせつつあるように見える。
2022年10月のユーロ圏の消費者物価指数(CPI)は対前年比10.7%に達した。ECBは再びその政策金利を0.75%引上げてインフレ抑制に動いた。2021~22年を除きコロナ禍の後,米国のような大規模な財政支援策を加盟国によって濃淡はあるものの打ち出せていない。ユーロ圏では景気の過熱ではなく供給ショックとエネルギー価格によってインフレが生じた。最近,欧州で採択された財政支援策は異常なエネルギー価格を抑えるためであって,需要をさらに刺激するためではない。欧州はディマンドプルでなく総供給の引下げに基づく物価上昇である。
欧州ではCPI上昇は7.1%のフランス以外すべての国が10月に2桁のインフレに見舞われた。独11.6%,ベルギー13.1%,オランダ16.8%,北欧バルティック海沿岸諸国ではエストニア22.4%,リトアニア22.0%という高いインフレの波に襲われている。コア・インフレ以外の項目のエネルギーや食糧の輸入依存度が高く,ロシア制裁やウクライナ戦争など地政学的影響を受けやすい国程,高い物価上昇率となっている。換言すれば,エネルギー依存度や戦争に伴う物資の調達における供給不足がロシアやウクライナに近い国ほど高いインフレになっている。地理的にも紛争地から離れているフランスは自前の原子力発電が7割と高く,対露エネルギー依存度が少なく,かつ食料の自給率が欧州で第1位であり,供給ショックに対しその耐久力を発揮している。これらのことは欧州では総供給AS曲線を左にシフトさせて物価下落をさせる必要があることを示唆している。コストプッシュ型インフレの欧州では理論的には金融政策でなく財政政策の出番である。
いち早く巨額のガス高抑制政策の財政支援を発表して,独り勝手の政策だと批判されたドイツは一転,リントナー財務省が緊縮政策に逆戻りすると発言,今度はこれが景気後退を招くと批判されている。2008年のリーマンショックの時のように財政支援を期待したときと異なる。財政政策は足並みがそろわず仏,伊,西などで財政赤字が拡大している。2023年のGDP成長率はフランスが当初2%,現在0~1%で推移,財政赤字は22年度同様5%に達する見込みである。今後はECBの金融政策と歩調を合わせる必要ありとする。各国の経済政策は世帯に対して失業補償でも景気浮揚でもなく,インフレと購買力の危機に向けられる必要がある。EUは2027年までの現行多年度予算の財政均衡を順守していく義務がある。フランスのルメール財務相は年金法案の予算審議に追われており,ECBなどに歩調を合わせていく余裕は少ない。ラガルドECB総裁は現状追認の姿勢が印象強く,遅れてタカ派の金利上昇派に転じてしまった。「家計の購買力を蝕む物価上昇を耐えるのか,あるいは景気後退を受け入れるのか。このジレンマにどう対処するかECBは判断を求められている」とフィガロ紙ド・カぺル論説委員は指摘する(Gaëtan de Capèle. L’éditorial Le Figaro)。実はEUは2008年以降多くの政策ミスを冒した。EU財政緊縮策はいたずらに需要を弱化させたと言われている。
米国のインフレは欧州とは違ってディマンドプル主導,それが労働力の不足が賃金の上昇を招き,サービス価格の高騰として顕在化した。欧州に比べて言うならば「複合インフレ」である。複合とは言え,米国では2020年のトランプ政権以来,5回のコロナ対策費,バイデン政権の21年にはレスキュウ・プランとして約2兆ドル,合計3兆7千億ドルもの巨額給付金が投入され総需要は高水準に達していた。
米国では,CPIコア指数の動きが利上げ継続と景気悪化の思惑を強め,株安の主因となっている。CPIはサービスの構成比率が約57%,サービスのうち住居の構成比率が高く帰属家賃は約24%。持家によって支払わずにすむ家賃を意味する帰属家賃は依然上昇傾向,今後の米インフレをみる上で価格の下落の遅い帰属家賃などいわゆるSticky-price(粘着価格)CPIが気になるところである。スタグフレーションや長期停滞を意味するスラグレーション(slugflation)と呼ぶ可能性が強まる欧州では,インフレ抑制に取り組むのが遅すぎたという批判が出始めている。P. クルーグマンも「日米欧とも低金利時代は多分過ぎ去ってはいない」と長丁場を示唆する(New York Times Nov18, 2022)。引上げた金利をいつ引下げていくのか。金融政策の利子率決定についてはテーラー・ルールに即して言えば需給ギャップとインフレ率が相反するという難しい局面にある(ジェームス・M. バーダマン早大教授)。
徐々に金融政策では対処しきれなくなり再び財政政策に頼ることになるのか。1980年代以降,論争の的となっていた景気対策の有効性を主張するケインズ主義者と裁量を斟酌しない合理的期待形成学者の有名な論争がぶり返している。後者はすでに達成された自然失業率のもとでは対策はインフレ率を上昇させるだけになってしまうと言う。確かにコロナ禍で非自発的失業者が人出不足を招くほど高水準にはなっている。景気の判断を行うきわどい時間が過ぎていく。
関連記事
瀬藤澄彦
-
New! [No.4139 2025.12.22 ]
-
[No.4092 2025.11.24 ]
-
[No.4021 2025.10.06 ]
最新のコラム
-
New! [No.4141 2025.12.22 ]
-
New! [No.4140 2025.12.22 ]
-
New! [No.4139 2025.12.22 ]
-
New! [No.4138 2025.12.22 ]
-
New! [No.4137 2025.12.22 ]
世界経済評論IMPACT 記事検索
おすすめの本〈 広告 〉
-
 グローバル都市革命:コンパクトシティ 田園都市 第3の都市
本体価格:3,500円+税 2022年11月
グローバル都市革命:コンパクトシティ 田園都市 第3の都市
本体価格:3,500円+税 2022年11月
文眞堂 -
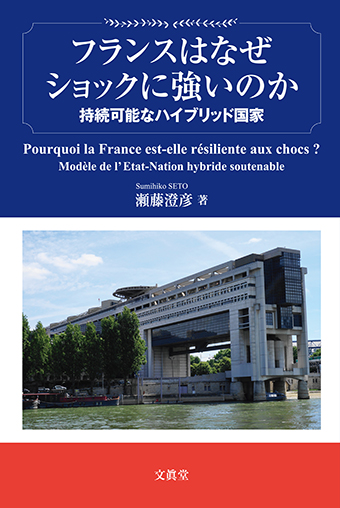 フランスはなぜショックに強いのか:持続可能なハイブリッド国家
本体価格:2,500円+税 2017年6月
フランスはなぜショックに強いのか:持続可能なハイブリッド国家
本体価格:2,500円+税 2017年6月
文眞堂 -
 DEIBにおける経営倫理とCSRの役割:障害者雇用と女性、LGBT、がん患者の方々に焦点を当てて
本体価格:2,700円+税 2025年10月
DEIBにおける経営倫理とCSRの役割:障害者雇用と女性、LGBT、がん患者の方々に焦点を当てて
本体価格:2,700円+税 2025年10月
文眞堂 -
 これさえ読めばすべてわかるアセットマネジメントの教科書
本体価格:2,900円+税 2025年9月
これさえ読めばすべてわかるアセットマネジメントの教科書
本体価格:2,900円+税 2025年9月
文眞堂 -
 グローバルサウス入門:「南」の論理で読み解く多極世界
本体価格:2,200円+税 2025年9月
グローバルサウス入門:「南」の論理で読み解く多極世界
本体価格:2,200円+税 2025年9月
文眞堂 -
 ルビーはなぜ赤いのか?:川野教授の宝石学講座
本体価格:2,500円+税
ルビーはなぜ赤いのか?:川野教授の宝石学講座
本体価格:2,500円+税
文眞堂 -
 サービス産業の国際戦略提携:1976~2022:テキストマイニングと事例で読み解くダイナミズム
本体価格:4,000円+税 2025年8月
サービス産業の国際戦略提携:1976~2022:テキストマイニングと事例で読み解くダイナミズム
本体価格:4,000円+税 2025年8月
文眞堂 -
 中国鉄鋼業:生産システム,企業,産業の三層構造と産業政策
本体価格:4,000円+税 2025年8月
中国鉄鋼業:生産システム,企業,産業の三層構造と産業政策
本体価格:4,000円+税 2025年8月
文眞堂 -
 高収益経営とアントレプレナーシップ:東燃中原延平・伸之の軌跡
本体価格:3,900円+税 2025年11月
高収益経営とアントレプレナーシップ:東燃中原延平・伸之の軌跡
本体価格:3,900円+税 2025年11月
文眞堂

