世界経済評論IMPACT(世界経済評論インパクト)
独・仏のグローバル価値連鎖:競争優位の逆転へ
(国際貿易投資研究所(ITI)客員 研究員・元帝京大学経済学部大学院 教授)
2025.06.16
1990年代から2000年代のグローバリゼーションで,世界の産業内貿易システムは中間財分野の2国間取引は大きな影響を受けた。ドイツは,①中東欧諸国のEU加盟によってこれら地域のドイツ産業のヒンターランド化と,②ユーロ危機の出口戦略としての緊縮政策を通じた産業競争力の強化を図ることができた。欧州経済の牽引役であったドイツと遅れを取ったフランスの間では,どのようにして競争優位の違いが生じ,そして今日,逆転するに至ったのか。
重層的なグローバル生産システムが競争優位を生んだ
フランス国立経済社会統計研究所(INSEE)は“労働コスト”を「労働者一人を雇用するときの経費の総額」と定義している。経費の総額とは,給与総額に配当や自社株配当を加えた直接コストと,事業主負担の社会保険料や各種諸手当などの間接経費を包含するコストの総称である。ドイツとフランスは2011年時点でこの“労働コスト”の比較においては,1時間当たりの35.5ユーロでほぼ拮抗していて,南欧諸国をかなり上回る水準にあった。問題はこの先にある。国際比較をする場合には,国別に違う労働生産性を考慮に入れなければならない。もし労働生産性が高い場合には,労働コストが高いことはハンディキャップにならない。これがいわゆる単位当たりの生産コストであるが,これで国別の比較は変化する。例えば2011年時点のフランスとイタリアの労働コストはそれぞれ時間当たり35ユーロと26ユーロであった。,その差は37%であるが,生産性を考慮すれば18%に縮小する。しかしこれは例えばフランス産業の国際競争力が低下し,企業の海外移転に伴う産業空洞化や貿易赤字の継続を十分に説明するには不十分であった。
ここで本稿のテーマ“中間財”の登場となる。生産性をも考慮に入れた労働コスト比較だけでは今日の国際競争力を計測することは不十分になってしまった。何故か? その理由は多くの多国籍企業の生産システムは大きく生産工程の中間段階における業務のアウトソーシングやオフショアリングに依存するようになったためである。この外部委託コストを正確に反映しないで国際競争力の比較を行っても実態を反映していないことになる。この点でフランスのサービス・コストはドイツに比較してかなり高くなっている。そのドイツはイタリアとほぼ同水準にある。
そして厄介なことに問題はさらなる高次元のところにある。それは企業の業務活動の価値連鎖をいかにして分散して最適な生産工程のネットワークを構築するかである。この点に関しドイツ企業は,内外の下請け企業や関係する中小企業を自社の生産システムの流れのなかにを位置づけるコンピタンスを有している。これらのMittelstandと呼ばれるいわゆる中小企業群は技術革新や最終製品の付加価値を高めることに大きく貢献してきた。そしてドイツ企業はポーランドなど中東欧諸国を筆頭に,英国,オランダ,などにおいてこのような価値連鎖のネットワーク網を張り巡らせてきた。そしてリーマショックやユーロ危機のユーロ安がさらに生産コストの低下を呼び,ドイツ企業にとって有利に働いていたのである。
ドイツ企業がグローバル競争力でフランス企業を凌駕していた理由
独・仏企業のの国際競争力比較を行う場合には,コストとリーダーシップ,差別化戦略,企業間ネットワークという3つのグローバル経営戦略からのアプローチが不可欠となる。広義の労働コスト,アウトソースされるサービスコスト,価値連鎖の分散による生産工程の最適化,業務のオフショアリングなどはすべてこれらの経営戦略の要素を考慮に入れなければならない。このようにして算出されたドイツ企業のグローバル競争力はフランス企業に比べて少なくとも20%以上,コスト面で凌駕していると言われている(注1)。ドイツ企業は高度で差別化された製品をイタリア,スペイン並みのコストで供給できる生産システムを構築していたのである。このドイツ企業の事例は,今後,企業がグローバルな産業競争力を構築するためには,サービスやソフト開発などの請負業務を多角的に活用したネットワークに大きく依存していることを認識する必要がある。しかしながら,これが産業構造の第3次産業化とか産業全体がサービス業種に移行することと混同してはならない。製造企業の生産システムが価値連鎖の分散を通じて錯綜したサービス化の実態のことを示しているのである。
フランス企業は産業間貿易に関わる水平的投資に終始
実際,CEPII(フランス国際経済研究所)の独・仏貿易経済関係の調査報告書(Trade Patterns Inside the Single Market:フォンタネ,フロイデンベルク,ペリディ著)は,ドイツ企業の積極的なアウトソーシングがフランスとの国際競争力の差を広げていると指摘している(注2)。独仏両国の中間財輸入先国は主に先進工業国であり,とりわけ経済産業の独・仏両国間の相互依存度は高く,両国は輸入先国としてそれぞれ第1位であり,その統合度はほかのどこよりも進んでいる。しかし無視しえない格差が存在する。ドイツがフランスに輸入中間財の20%を供給しているのに対し,フランスはその半分の中間財しかドイツに輸出していない。ドイツはさらにチェコ,ポーランドを中心とした中東欧諸国や低い生産コスト国からからの中間財輸入を増大させている。ドイツ企業の行う生産工程にかかわる価値連鎖の分散戦略が競争力強化につながっていたのである。フランスでは輸入取引のみにこのような戦略が観察される。ドイツの海外投資の重要な部分はドイツ企業の価値連鎖における生産工程ネットワークに統合する目的でなされている。フランス企業は産業間貿易に関わる水平的投資に終始して,海外投資先の収益をすべて吸い上げ,価値連鎖の効率的な分散に向かうような垂直的な海外投資に向かっていない。
フランスの海外投資の特徴についてパリ商工会議所(CCIP)は次の3点を指摘する。①大企業グループが海外子会社設置を支配。②投資先がEU諸国の近隣国に地理的に集中。③フランス企業の海外直接投資の売上高の半分は4業種に限定される。このような特徴からフランスの海外直接投資はグローバル化の波に乗れなかった。
第1に企業経営のグローバル化というのは大企業グループの戦略であるという考えから,ドイツ企業に比べてフランスの場合国内の価値連鎖に関連性を持たせる意識が少ない。第2にフランス企業はCEPIIの言うmarket seekingで水平的な海外進出であり,現地のローカルな市場制覇が第一義的であり,収益性やコストの問題は第2義的にされる傾向がある。第3にフランス企業は長期的な海外立地を優先にして生産システム全体を移転させてしまうことが多い。これはマーケティング,戦略的アライアンス,価値連鎖の分散などを重視するドイツ企業と対照をなす。第4に通常,海外直接投資は本国の貿易収支の改善に資することが多い。しかし上述のCEPII報告でもフランス企業が1ドルの海外投資で対投資先国に55セントの代替輸出,24セントの誘発輸入したと報告されているが,ここ10年ではこのような数字は観察されていない。従ってフランスの製造業を支えて「メイド・イン・フランス」としてフランス製品輸出を支援推進するような海外直接投資にはなっていないということができるであろう。
コロナ・パンデミック,ウクライナ戦争,ユーロ為替相場の上昇,地中海沿岸諸国の相対的経済好調などによってドイツとフランスを巡る国際経営戦略のコンテンジャンシー条件は180度変質した。その説明は別の機会に譲る。
[注]
- (1)“ Compétitivité globales déclin industriel : quel coût coupable ? ” par Alexandre Mirlicourtois, directeur des êtudes de Xerf Canal 2012年5月22日
- (2)“ Prospective du couple franco-allemend ” par M Bernard ANGELS 22 juin 2011
関連記事
瀬藤澄彦
-
[No.4139 2025.12.22 ]
-
[No.4092 2025.11.24 ]
-
[No.4021 2025.10.06 ]
最新のコラム
-
[No.4149 2025.12.29 ]
-
[No.4148 2025.12.29 ]
-
[No.4147 2025.12.29 ]
-
[No.4146 2025.12.29 ]
-
[No.4145 2025.12.29 ]
世界経済評論IMPACT 記事検索
おすすめの本〈 広告 〉
-
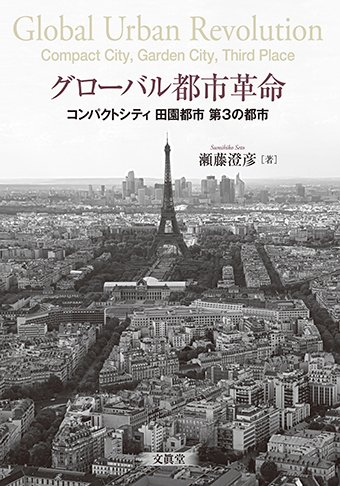 グローバル都市革命:コンパクトシティ 田園都市 第3の都市
本体価格:3,500円+税 2022年11月
グローバル都市革命:コンパクトシティ 田園都市 第3の都市
本体価格:3,500円+税 2022年11月
文眞堂 -
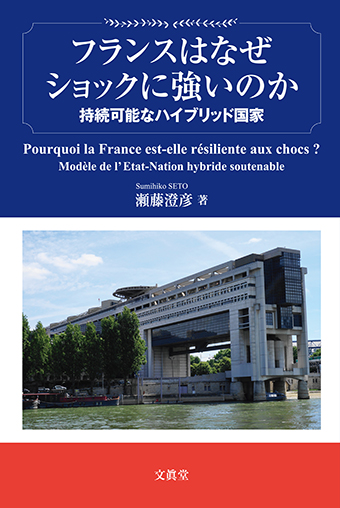 フランスはなぜショックに強いのか:持続可能なハイブリッド国家
本体価格:2,500円+税 2017年6月
フランスはなぜショックに強いのか:持続可能なハイブリッド国家
本体価格:2,500円+税 2017年6月
文眞堂 -
 サービス産業の国際戦略提携:1976~2022:テキストマイニングと事例で読み解くダイナミズム
本体価格:4,000円+税 2025年8月
サービス産業の国際戦略提携:1976~2022:テキストマイニングと事例で読み解くダイナミズム
本体価格:4,000円+税 2025年8月
文眞堂 -
 グローバルサウス入門:「南」の論理で読み解く多極世界
本体価格:2,200円+税 2025年9月
グローバルサウス入門:「南」の論理で読み解く多極世界
本体価格:2,200円+税 2025年9月
文眞堂 -
 高収益経営とアントレプレナーシップ:東燃中原延平・伸之の軌跡
本体価格:3,900円+税 2025年11月
高収益経営とアントレプレナーシップ:東燃中原延平・伸之の軌跡
本体価格:3,900円+税 2025年11月
文眞堂 -
 DEIBにおける経営倫理とCSRの役割:障害者雇用と女性、LGBT、がん患者の方々に焦点を当てて
本体価格:2,700円+税 2025年10月
DEIBにおける経営倫理とCSRの役割:障害者雇用と女性、LGBT、がん患者の方々に焦点を当てて
本体価格:2,700円+税 2025年10月
文眞堂 -
 ルビーはなぜ赤いのか?:川野教授の宝石学講座
本体価格:2,500円+税
ルビーはなぜ赤いのか?:川野教授の宝石学講座
本体価格:2,500円+税
文眞堂 -
 中国鉄鋼業:生産システム,企業,産業の三層構造と産業政策
本体価格:4,000円+税 2025年8月
中国鉄鋼業:生産システム,企業,産業の三層構造と産業政策
本体価格:4,000円+税 2025年8月
文眞堂 -
 国際マーケティングの補助線
本体価格:2,700円+税 2025年9月
国際マーケティングの補助線
本体価格:2,700円+税 2025年9月
文眞堂

