世界経済評論IMPACT(世界経済評論インパクト)
ミクロとマクロの不整合
(杏林大学総合政策学部 教授)
2022.05.30
経済理論に「ミクロ」と「マクロ」があることは周知であるに違いない。経済学部のカリキュラムで,どちらかだけが教えられているということはまずなく,ほぼ必ずと言っていいほど,両方が教えられている。しかもたいていは必修でだ。
両者の間には必ずしも理論的な整合性があるわけではないことも,ほとんどの経済学者は認識している。同時に日々の授業を行うにあたっては,それを都合よく忘れている他はないことも・・・である。
私はマクロ経済学を専門としているが,折りに触れ,両方を教える羽目になることがある。両者を学ぶ意味について,私なりの説明というものはある。とはいえ,両者の間の理論的不整合について,悩ましい点があることは事実だ。そう思いながらも授業は進んでいく。何しろ,両者の不整合について語りだしたら,15回の授業なんて,それだけで終わってしまいかねない。
そう自分に言い聞かせつつ,それでいて,ミクロを教えているときには,需要と供給は両方大事だ,片方だけで考えてはいけないのだ,などと説きながら,銀座のビールがなぜ高いかの話をする。いや,正確にはスキー・ゲレンデの食堂や東京ドームで試合を見ながら飲むビールの値段についてで,銀座の話はしない。しかし,その舌の根も乾かぬうちに,マクロを教えているときは総需要が総生産を決める(有効需要の原理)などと説くことになるのだ。両方聞いている学生に,混乱するなという方が無理というものである。
両者の橋渡しをしようとする,報われることのない努力のもっとも初期のものは,サミュエルソン(Paul Anthony Samuelson,1915 - 2009)による「新古典派総合」である。世界的なベストセラーとなった彼の教科書を通じて知られるようになったものだけに,多くの批判を受けながらも根強い生命力をもっているように思える。
それは,市場メカニズムはしばしば機能不全を起こし,失業を生み出すが,政府のマクロ経済政策を行使して,ひとたび完全雇用が実現すれば,そこから先はミクロ経済学の説く価格調整メカニズムが機能するのだ,と主張している。厄介なことに,実は,この主張は他ならぬケインズ(John Maynard Keynes,1883 - 1946)が彼の『一般理論』の中で述べたこと,ほぼそのままなのである。
ケインズにしては恐ろしく不用意な発言だが,おそらく彼は自分の主張が社会主義を擁護するものだと受けとられることを避けたかったのではないかと推測している。自分は資本主義それ自体を否定するつもりはなく,ましてや革命を支持しているわけではないことを強調したかったのだろう。しかし,不用意であったことには違いないと思う。
アロー(Kenneth Joseph Arrow,1921 - 2017)が批判したように,新古典派総合が説くようなことにはならないのだ。彼の例を用いれば,もし,賃金の硬直性によって失業が起こるようなシステムであれば,それを財政政策で完全雇用にもっていったとしても,そこで価格調整メカニズムが働くとは考えられない。賃金もまた価格だからだ。要するに,両者はシステムとしてそもそも異なっているのである。
また,厚生経済学におけるセカンド・ベスト(次善)の理論によれば,労働市場で需給が均衡しないような経済における最適条件は,それ以外の市場についても,通常の最適条件とは異なってしまう。また,労働市場の需給を回復させるような試みは,他の市場にネガティブな影響をもたらす可能性があるのだ。
他方で,マクロ経済学をミクロ経済学の手法によって再構成しようとする試み―ミクロ的基礎―は,いずれも不毛に終わった。何しろ,ミクロ的に基礎づけようとすればするほど,ケインズの世界からは遠ざかっていくのだから。そして挙句の果てには,そもそも非自発的な失業など存在しないとか,貨幣的要因は無関係だとかいう,突拍子もない市場メカニズム至上主義を生み出してしまった。
解決策? うん,もちろん,諦めるのがいいと思う! 力学だって,ミクロとマクロは別物だ。それでいいではないか。ミクロもマクロも,現実のある特定の側面を切り取って分析するための個別のモデルであるにすぎない。ミクロ経済学における一般均衡理論の普遍性を過信することがそもそもの病原なのだ。
そういえば,私が学生時代,岩波書店から出ていた「現代経済学」シリーズの教科書のタイトルは,『ミクロ経済学』『マクロ経済学』ではなく,『価格理論』『所得分析』だった。今はそうではなくなってしまったが,うん,悪くなかったんじゃないだろうか。
関連記事
西 孝
-
[No.4094 2025.11.24 ]
-
[No.3963 2025.08.25 ]
-
[No.3842 2025.05.26 ]
最新のコラム
-
New! [No.4194 2026.02.02 ]
-
New! [No.4193 2026.02.02 ]
-
New! [No.4192 2026.02.02 ]
-
New! [No.4191 2026.02.02 ]
-
New! [No.4190 2026.02.02 ]
世界経済評論IMPACT 記事検索
おすすめの本〈 広告 〉
-
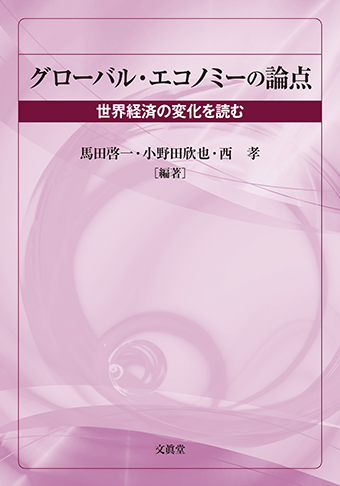 グローバル・エコノミーの論点:世界経済の変化を読む
本体価格:2,800円+税 2017年2月
グローバル・エコノミーの論点:世界経済の変化を読む
本体価格:2,800円+税 2017年2月
文眞堂 -
 国際関係の論点:グローバル・ガバナンスの視点から
本体価格:2,800円+税 2015年2月
国際関係の論点:グローバル・ガバナンスの視点から
本体価格:2,800円+税 2015年2月
文眞堂 -
 揺らぐ世界経済秩序と日本:反グローバリズムと保護主義の深層
本体価格:2,800円+税 2019年11月
揺らぐ世界経済秩序と日本:反グローバリズムと保護主義の深層
本体価格:2,800円+税 2019年11月
文眞堂 -
 創造力強化経営の実践
本体価格:2,200円+税
創造力強化経営の実践
本体価格:2,200円+税
文眞堂 -
 これさえ読めばすべてわかるアセットマネジメントの教科書
本体価格:2,900円+税 2025年9月
これさえ読めばすべてわかるアセットマネジメントの教科書
本体価格:2,900円+税 2025年9月
文眞堂 -
 ルビーはなぜ赤いのか?:川野教授の宝石学講座
本体価格:2,500円+税
ルビーはなぜ赤いのか?:川野教授の宝石学講座
本体価格:2,500円+税
文眞堂 -
 DEIBにおける経営倫理とCSRの役割:障害者雇用と女性、LGBT、がん患者の方々に焦点を当てて
本体価格:2,700円+税 2025年10月
DEIBにおける経営倫理とCSRの役割:障害者雇用と女性、LGBT、がん患者の方々に焦点を当てて
本体価格:2,700円+税 2025年10月
文眞堂 -
 ソーシャルマーケティング:行動変容で社会的価値を共創する
本体価格:3,500円+税 2025年12月
ソーシャルマーケティング:行動変容で社会的価値を共創する
本体価格:3,500円+税 2025年12月
文眞堂 -
 グローバルサウス入門:「南」の論理で読み解く多極世界
本体価格:2,200円+税 2025年9月
グローバルサウス入門:「南」の論理で読み解く多極世界
本体価格:2,200円+税 2025年9月
文眞堂 -
 職場・学校のセクハラ・パワハラ :ハラスメントの法と判例
本体価格:1,300円+税 2026年1月
職場・学校のセクハラ・パワハラ :ハラスメントの法と判例
本体価格:1,300円+税 2026年1月
文眞堂

