世界経済評論IMPACT(世界経済評論インパクト)
米最高裁,IEEPAによるトランプ関税を迅速審理
(桜美林大学 名誉教授・国際貿易投資研究所 客員研究員)
2025.09.22
米最高裁判所は,9月9日,トランプ大統領が国際緊急経済権限法(IEEPA)(注1)に基づく一連の関税措置の合法性を早急に審理すると発表した。トランプ大統領が下級審の判決を不服として,最高裁に上訴したのは9月3日であったから,最高裁の発表はトランプ政権の意向を受けて極めて迅速であった。これに伴い,最高裁は中小企業5社,提訴したテキサス州オースティンのLiberty Justice Centerおよび12の州政府(注2),および被告である連邦政府に対して,9月19日までに弁論書を提出するよう要請した。最高裁で連邦政府の代理人として訴訟事務を担当するジョン・サウアー訟務長官(US Solicitor General) は,審理は11月第1週に開始されるとしている〔9月9日付ワシントン・ポスト(WP,Supreme Court to weigh legality of Trump’s tariffs in key economic case)〕。迅速に審理が進めば年内に判決が出る可能性もあるという。
トランプ大統領の脅威認定とIEEPAによる関税措置
トランプ大統領がIEEPAに基づき実施した関税措置は,①不法移民とフェンタニルの流入,および米国の貿易赤字を理由とする中国原産品に対する10%の関税上乗せ(発動:2月4日),同10%を20%に引き上げ(3月3日),その後追加関税は最大145%となったが,8月11日34%に引き下げられた(期限は11月10まで),②同上の理由により,カナダ・メキシコ原産品に25%の関税上乗せ(カナダ産資源品目は10%)(3月4日),③ベネズエラ産原油を輸入する国・地域の原産品に25%の関税上乗せ(4月2日),④カナダ・メキシコを除く全ての国・地域の全品目に4月5日以降,10%の関税上乗せ,その後4月10日から90日間の課税停止(中国を除く)を経て,8月7日から最高50%の相互関税の上乗せ,の4種類がある(注3)。
トランプ大統領は4月2日付の大統領令で,「大規模かつ持続的な米国の貿易赤字は,米国の国家安全保障と経済に対する異例の脅威を構成する」とし,米国通商政策史上初めて「相互関税」を賦課した。また,同関税を導入した4月2日を,諸外国による「米国略奪」を終わらせる「解放の日」と宣言した。IEEPAによる新たな関税賦課は,IEEPA制定50年の歴史で,トランプ大統領が初めてである。ホワイトハウス内の2人の関係者によると,IEEPAの援用を強く推進したのはトランプ大統領の通商顧問ピーター・ナバロであったという(9月7日付NBC News, The White House is exploring how to keep Trump’s tariffs if the Supreme Court strikes them down)。
最高裁が重視する「主要問題原則」
大統領令が発出された4月,上述の中小企業5社および12州の知事等が,トランプ大統領の関税措置は広範囲にわたり経済的損失をもたらすとして提訴した。その主張は,①IEEPAは大統領に関税を賦課する権限を与えていない,②トランプ大統領が正当化する国家非常事態は存在せず,③米国憲法上,関税賦課の権限は大統領だけでなく議会にもある,として,トランプ大統領の行動は憲法の三権分立原則に違反し,同時に④最高裁の「主要問題原則」(major questions doctrine)(注4)に抵触すると主張した。
ニューヨーク国際貿易裁判所の判決
下級審の判決はまず5月28日,ニューヨークの国際貿易裁判所が下した。3人の判事から成る審判団は,「トランプ関税は異常で法外な脅威(unusual and extraordinary threats)に対処するというIEEPA法の要件を満たしていない」,「大統領が決定した関税の賦課は,大統領が表明した国境を越える移民や麻薬の移動を抑制するものではなく,他の政府にその移動を阻止するための行動をとらせるテコにすることが目的である」,「大統領に輸入を規制する権限を与えているとのIEEPAの文言によって,政府はIEEPAが大統領に関税率に関する完全な権限を与えていると主張しているが,IEEPAは,大統領に大統領が望ましいと考える関税率を賦課する権限を与えていない」とし,「IEEPAを根拠とする関税賦課命令(上記の①~④)はすべて無効であり,課税措置は永久に停止される」と決定した(5月28日付WP,Trump’s ‘Liberation Day’ tariffs halted by Court of International Trade)。
連邦巡回控訴裁判所の判決
国際貿易裁判所の判決を不服として,トランプ大統領は直ちに控訴したが,連邦巡回控訴裁判所(U.S. Court of Appeals for the Federal Circuit)は8月29日,国際貿易裁判所の判決を差し止め,全文127ページの判決(注5)を発表した。7対4の評決による多数派の見解は,「IEEPAは大統領に国家緊急事態に対応していくつかの措置を講じる大きな権限を与えているが,これらの措置のいずれにも,関税,税金,およびその他類似のものを課す権限,あるいは課税権は明示的に含まれていない」,「議会による有効な委任がない限り,大統領には課税権限がない」と明記されている。
トランプ大統領は,冒頭に記したように,控訴裁判所の判決に対して,9月3日,最高裁に控訴したが,トランプ政権の当局者は,「最高裁が来年6月までに大統領の主張を認めなければ,その時までに徴収した関税1兆ドルを返戻しなければならない」と述べた(9月9日付WP, op. cit)。
最高裁は「主要問題原則」をどう判断するか
本裁判の原告団が主張した上述の「主要問題原則」について,連邦巡回控訴裁判所は,もし議会が大統領に関税表を書き換える自由な権限を与える意図を持っていたならば,トランプ政権がその旨を明示していたはずだと論じている。輸入品に対する課税問題などを管轄する特別裁判所である国際貿易裁判所(1890年設置)が,IEEPAとその大統領権限について明確な判断を示している以上,最高裁としてはこれを覆すことは難しい。このため,最高裁の判断には「主要問題原則」が大きく影響するとみられる。ジョン・G・ロバーツ・ジュニア最高裁長官は過去2回の民主党政権の時代に,この「主要問題原則」を積極的に適用して,民主党政権の行政を抑制してきた。
しかし,トランプ大統領が第1期政権で指名したブレット・M・カバノー最高裁判事は,「絶えず変化する国家安全保障上の脅威や外交上の課題に対応する大統領の意思決定の性質上,「主要問題原則」は外交問題には適用されないと示唆している。貿易問題も移民問題も外交政策に密接に関連しているだけに,最高裁の審理で「主要問題原則」が適用されない可能性もある。リベラル派のケタンジ・ブラウン・ジャクソン判事は,「最高裁のゲームには固定したルールはない。二つのルールがあって,トランプ政権は常に勝ち(その結果,大統領の権力は強化される)」と述べている(9月12日付WP,The fate of Trump’s tariffs hinges on this Supreme Court doctrine)。
最高裁判決の行方
最近,最高裁は,トランプ政権が下した3つの決定(①キューバ,ハイチ,ニカラグア,ベネズエラからの移民53万人に対する最大2年間の米国での生活と労働を認める連邦プログラムの停止,②FTC(連邦取引委員会)のアルバロ・べドヤとレベッカ・ケリー・スローターの両民主党委員の解任,③NIH(国立衛生研究所)のマイノリティ等に対する助成金8億ドルの削減,をすべて承認している。こうしたこともあってか,首都ワシントンの通商弁護士は,トランプ政権の関税賦課が「違憲となる可能性は五分五分」としているように(注6),IEEPAを根拠とする関税賦課が,下級審で却下されても,最高裁で生き返る可能性が無いとは言えない。
仮に最高裁でトランプ関税が違憲と判断されても,トランプ政権はIEEPAに代る手段として,第1に1962年通商拡大法232条による国防条項,第2に1974年通商法301条による一方的措置,の発動を準備しているという。これらの代替策はIEEPAによるよりも迅速性に欠け,IEEPAのような一刀両断的な効果には劣るが,トランプ大統領の関税政策が本質的に変わるわけではないとしている(9月7日付NBC News, op, cit)。
[注]
- (1)IEEPA,International Emergency Economic Powers Act, 1977年10月28日施行。
- (2)12州はオレゴン,アリゾナ,コロラド,イリノイ,ニューヨーク等。ネバダ州以外の11州の知事は全て民主党。
- (3)2025年4月16日付ジェトロ調査部米州課,「米国トランプ政権の関税政策の要旨」,本稿①と④の一部は筆者が加筆。
- (4)「主要問題原則」は,バイデン政権下の2022年に最高裁が環境保護庁の温室効果ガスの規制権限を巡る訴訟で確立されたもので,大統領が経済的または政治的に大きな意義を持つ問題を規制するには,議会からの明確な許可を得る必要があるとする。最高裁はこの原則に基づき,バイデン大統領による4000億ドルの奨学金の免除,二酸化炭素排出量抑制,パンデミック中の一部企業へのワクチン接種義務化の試みを阻止した(9月9日付WP, op. cit)。
- (5)連邦巡回控訴裁判所(U.S. Court of Appeals for the Federal Circuit)の判決の全文
- (6)9月17日付ジェトロ・ビジネス短信「米最高裁のIEEPA関税の判断,早ければ年内に,還付手続きの行方に注目」。
関連記事
滝井光夫
-
[No.4141 2025.12.22 ]
-
[No.4109 2025.12.01 ]
-
[No.4030 2025.10.13 ]
最新のコラム
-
[No.4149 2025.12.29 ]
-
[No.4148 2025.12.29 ]
-
[No.4147 2025.12.29 ]
-
[No.4146 2025.12.29 ]
-
[No.4145 2025.12.29 ]
世界経済評論IMPACT 記事検索
おすすめの本〈 広告 〉
-
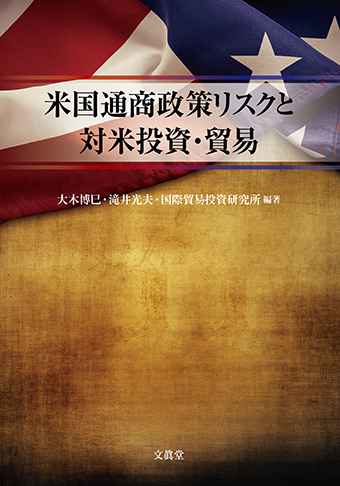 米国通商政策リスクと対米投資・貿易
本体価格:3,000円+税 2018年8月
米国通商政策リスクと対米投資・貿易
本体価格:3,000円+税 2018年8月
文眞堂 -
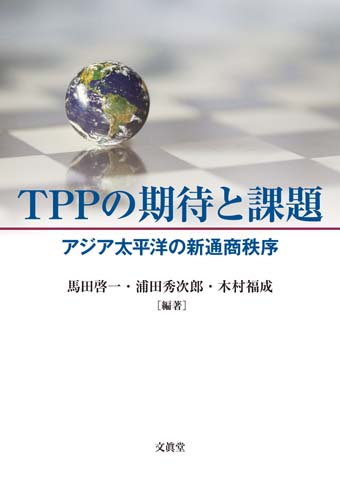 TPPの期待と課題:アジア太平洋の新通商秩序
本体価格:2,750円+税 2016年10月
TPPの期待と課題:アジア太平洋の新通商秩序
本体価格:2,750円+税 2016年10月
文眞堂 -
 国際マーケティングの補助線
本体価格:2,700円+税 2025年9月
国際マーケティングの補助線
本体価格:2,700円+税 2025年9月
文眞堂 -
 揺らぐサムスン共和国:米中対立の狭間で苦悩する巨大財閥
本体価格:2,700円+税 2025年12月
揺らぐサムスン共和国:米中対立の狭間で苦悩する巨大財閥
本体価格:2,700円+税 2025年12月
文眞堂 -
 DEIBにおける経営倫理とCSRの役割:障害者雇用と女性、LGBT、がん患者の方々に焦点を当てて
本体価格:2,700円+税 2025年10月
DEIBにおける経営倫理とCSRの役割:障害者雇用と女性、LGBT、がん患者の方々に焦点を当てて
本体価格:2,700円+税 2025年10月
文眞堂 -
 中国鉄鋼業:生産システム,企業,産業の三層構造と産業政策
本体価格:4,000円+税 2025年8月
中国鉄鋼業:生産システム,企業,産業の三層構造と産業政策
本体価格:4,000円+税 2025年8月
文眞堂 -
 高収益経営とアントレプレナーシップ:東燃中原延平・伸之の軌跡
本体価格:3,900円+税 2025年11月
高収益経営とアントレプレナーシップ:東燃中原延平・伸之の軌跡
本体価格:3,900円+税 2025年11月
文眞堂 -
 グローバルサウス入門:「南」の論理で読み解く多極世界
本体価格:2,200円+税 2025年9月
グローバルサウス入門:「南」の論理で読み解く多極世界
本体価格:2,200円+税 2025年9月
文眞堂 -
 サービス産業の国際戦略提携:1976~2022:テキストマイニングと事例で読み解くダイナミズム
本体価格:4,000円+税 2025年8月
サービス産業の国際戦略提携:1976~2022:テキストマイニングと事例で読み解くダイナミズム
本体価格:4,000円+税 2025年8月
文眞堂

