世界経済評論IMPACT(世界経済評論インパクト)
トランプ氏に「スマホ国内製造業回帰」の意図なし:「メイク・イン・インディア」による証明
(国際貿易投資研究所 客員研究員)
2025.08.11
日米両国政府は2025年7月,日本から自動車「完成品」の対米輸出に掛かる関税率を15%とすることで合意した。しかし,米自動車大手で構成される自動車貿易政策評議会は,メキシコなどから調達する「部品」の関税率が25%であるため,この合意に不満を示した(注1)。これは「逆転関税構造」(inverted duty structure)である。つまり,より高い関税率の「部品」を輸入して車を組み立てて販売することは,より安い関税率の「完成車」を輸入して販売する方が有利だからである。したがって,トランプ氏の意図する,米国内への「製造業回帰」は自動車産業では当てはまらない可能性がある。
一方,インドでは,“メイク・イン・インディア”の名の下,スマートフォンの組立製造における「逆転関税構造」を転換することにより,スマホの国内製造を拡大させることに成功した。
1.メイク・イン・インディア
インドでは,2014年にモディ首相が「メイク・イン・インディア」政策を発表した(注2)。これは,国家主導の製造業振興政策(注3)であり,インドを世界の製造業生産拠点に育成するために,製造業を段階的に現地化する(注4)。「段階的製造プログラム(PMP:Phased Manufacturing Program)」と「生産連動型インセンティブ(PLI:Production Linked Incentive Scheme)」が政策の中心となった。この内,PMPは関税政策を中心に実施された。
メイン・イン・インディアでは,自動車,自動車部品,電子機器,製薬など重点25分野が選定された(注5)。本稿では,特にスマートフォンに焦点を当てて分析する。
2.「「完成品」の関税率が「部品」より低い逆転関税構造」
インドでは,2014年以前は,「逆転関税構造」が存在した。スマホの「完成品」は情報技術協定(ITA)の対象であり,WTOの合意に基づいて無税(0%)で輸入が可能であった。WTO合意は,特に2014年まで中国や韓国からのスマホ完成品に適用された。
「部品」(CKD/SKD部品)はITAの対象外のものが多く,5%,10%,一部で12%の関税が課せられた。ただし,PCBA(プリント基板実装)や「バッテリーパック」などは課税対象外であった。
3.段階的製造プログラム(PMP)による関税率の引き上げ
2015–2019年の間にPMPで,段階的に完成品の関税を部品より高くする政策が導入され(注6),逆転関税構造の転換に成功した(注7)。
(1)最終財の完成品への高率関税化
「完成品」の輸入抑制のため2014年から段階的に最終財の完成品スマホの基本関税(BCD:Basic Customs Duty)が引き上げられ,2014年に6%,2014に12.5%,2017年に15%,2018年には20%となった。
(2)中間財の部品への低率関税化
「部品」については,完成品の関税率の20%より低く設定した。基本関税(BCD)は,2016–17年度に「低コスト部品」の充電器(Charger/Adaptor),バッテリーパック,有線ヘッドセットを各15%とした。2017–18年度に「中間構造部品」のメカニクス部品,ダイカット部品,マイク・受話器,キーパッド,USBケーブルを各15%とした。2018–19年度に「高付加価値部品」PCBA(プリント基板実装)へ拡大し,10%にした。2019–20年度にカメラモジュール,コネクタ,2020-21年度振動モーターを各10%とした。
(3)逆転関税構造の「転換」の成功
以上のように最終財の完成品の関税率が「20%」で,中間財の部品のそれが10%,15%となり,逆転関税構造が転換した。最終財完成品の関税率を中間財部品のそれより高くした結果として,完成品を輸入するよりは部品を輸入してインド国内で組み立てる方が有利である構造へ転換した。
4.トランプ政策によるアメリカに「国内製造業回帰」なし
「製造業国内回帰」を目指すトランプ氏は2025年4月4日にスマホについて「完成品」の関税を免除した(注8)。中間財の「部品」は免除されないので「逆転関税構造」となっている。先に述べたように自動車についても同様である。したがって,米国におけるスマホ製造の国内回帰には不利に働くこととなり,トランプの関税政策は,意図するところとは逆に長期的に国内製造業回帰につながらない。
[注]
- (1)日本経済新聞,2025年7月26日。
- (2)Make in India(2025年6月18日アクセス)。
- (3)Make in India公式ポータル(2025年7月20日アクセス)。インド商工省(DPIIT:Department for Promotion of Industry and Internal Trade,)Annual Report(2025年7月20日アクセス)。Union Budget Speeches(予算教書)財務省が発表。毎年の産業支援策・Make in India関連政策が記載。(2025年7月20日アクセス)。
- (4)インド商工省(DPIIT:Department for Promotion of Industry and Internal Trade),(2025年6月18日アクセス)。
- (5)ギリ・ラム,「インド製造業振興策「Make in India」の行方」,三井物産研究所,2020年1月(2025年6月17日アクセス)。
- (6)Ministry of Electronics and Information Technology, Annual Report 2017-18,(2025年7月20日アクセス)。
- (7)Ministry of Electronics and Information Technology, "Phased Manufacturing Programme (PMP) for mobile handsets and components,"(2025年6月18日アクセス)。
- (8)ジェトロ・ビジネス短信「トランプ米大統領,スマホなど半導体関連製品を相互関税の対象外とする覚書発表」(2025年4月14日付),(2025年7月20日アクセス)
関連記事
朽木昭文
-
[No.4125 2025.12.15 ]
-
[No.4061 2025.11.03 ]
-
[No.3980 2025.09.08 ]
最新のコラム
-
New! [No.4178 2026.01.19 ]
-
New! [No.4177 2026.01.19 ]
-
New! [No.4176 2026.01.19 ]
-
New! [No.4175 2026.01.19 ]
-
New! [No.4174 2026.01.19 ]
世界経済評論IMPACT 記事検索
おすすめの本〈 広告 〉
-
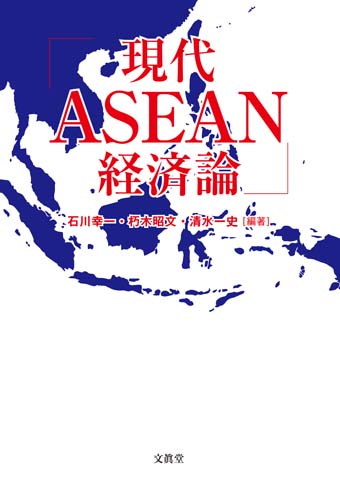 現代ASEAN経済論
本体価格:2,500円+税 2015年9月
現代ASEAN経済論
本体価格:2,500円+税 2015年9月
文眞堂 -
 高まる地政学的リスクとアジアの通商秩序:現状と課題、展望
本体価格:2,800円+税 2023年9月
高まる地政学的リスクとアジアの通商秩序:現状と課題、展望
本体価格:2,800円+税 2023年9月
文眞堂 -
 岐路に立つアジア経済:米中対立とコロナ禍への対応
本体価格:2,800円+税 2021年10月
岐路に立つアジア経済:米中対立とコロナ禍への対応
本体価格:2,800円+税 2021年10月
文眞堂 -
 国際マーケティングの補助線
本体価格:2,700円+税 2025年9月
国際マーケティングの補助線
本体価格:2,700円+税 2025年9月
文眞堂 -
 揺らぐサムスン共和国:米中対立の狭間で苦悩する巨大財閥
本体価格:2,700円+税 2025年12月
揺らぐサムスン共和国:米中対立の狭間で苦悩する巨大財閥
本体価格:2,700円+税 2025年12月
文眞堂 -
 高収益経営とアントレプレナーシップ:東燃中原延平・伸之の軌跡
本体価格:3,900円+税 2025年11月
高収益経営とアントレプレナーシップ:東燃中原延平・伸之の軌跡
本体価格:3,900円+税 2025年11月
文眞堂 -
 職場・学校のセクハラ・パワハラ :ハラスメントの法と判例
本体価格:1,300円+税 2026年1月
職場・学校のセクハラ・パワハラ :ハラスメントの法と判例
本体価格:1,300円+税 2026年1月
文眞堂 -
 これさえ読めばすべてわかるアセットマネジメントの教科書
本体価格:2,900円+税 2025年9月
これさえ読めばすべてわかるアセットマネジメントの教科書
本体価格:2,900円+税 2025年9月
文眞堂 -
 サービス産業の国際戦略提携:1976~2022:テキストマイニングと事例で読み解くダイナミズム
本体価格:4,000円+税 2025年8月
サービス産業の国際戦略提携:1976~2022:テキストマイニングと事例で読み解くダイナミズム
本体価格:4,000円+税 2025年8月
文眞堂 -
 中国鉄鋼業:生産システム,企業,産業の三層構造と産業政策
本体価格:4,000円+税 2025年8月
中国鉄鋼業:生産システム,企業,産業の三層構造と産業政策
本体価格:4,000円+税 2025年8月
文眞堂

