世界経済評論IMPACT(世界経済評論インパクト)
世界的な「アメリカ・ファースト」の危険性
(明治大学 教授)
2025.07.28
2025年4月2日,トランプ米大統領は「相互関税」発動の大統領令に署名した。これを契機に各国・地域は,世界一律10%のベースライン関税に上乗せされる個別の関税率をめぐって,米国政府との間で二国間交渉(ディール!)に乗り出すことになった。執筆時現在(7月20日),上乗せ部分の関税賦課は一時的に停止されている状況にあるが,期限が迫る前に,他国が妥結する前に,交渉を終わらせるべきという声も上がっている。
第一次政権時にトランプ大統領は,アメリカが戦後IMF・GATT体制のもとで構築し,今日のGATT・WTO体制の基本原則でもある「自由・無差別・多国間主義」を悉く否定した。「アメリカ・ファースト」を旗印として,真逆の「保護・差別・二国間主義」の道を突き進んだ。アメリカの雇用および所得の増大のために「保護主義」を掲げ,中国など特定国を狙い撃ちにした「差別的措置」を実施し,各国に要求を飲ませるために「二国間交渉」(注1)を展開したのであった。
第二次トランプ政権においても,「毎日がアメリカ・ファースト」を謳い,「保護・差別・二国間主義」をさらに強化している。「相互関税」が中国など特定国だけでなく世界各国・地域を対象とすること,しかもその税率が高いことなどを踏まえれば,保護主義の度合いは高まったと言える。トランプ大統領の支持層と言われる「忘れられた人々」の立場になれば,「チャイナ・ショック」等への反応として心情的に保護主義が高まることは想像に難くない。それに対する処方箋としての関税引き上げに否定的な研究はすでにあるので(注2),以下では差別主義と二国間主義の問題に注目したい。
今回のアメリカの相互関税は,各国・地域ごとに異なる関税率を課すもので,無差別平等な最恵国待遇を原則とするGATT第1条1項に違反している。ところが,日本を含む多くの国は,アメリカとの二国間交渉においてそのような差別的なやり方の撤回を要求するのではなく,自国に対する関税率の引き下げを要請している。つまり,アメリカだけでなく各国・地域も「自国ファースト」に陥っているのである。
そのうえ,自国が有利な条件(より低い関税率)を得られるように,無垢の第三国に対して譲許しているよりも良い条件をアメリカに提示することになる。アメリカとの二国間交渉のなかで,ベトナムやインドネシアが対米輸入関税をゼロにすると報じられているが(注3),それが事実であればベトナムやインドネシアはアメリカ以外の国・地域を犠牲にして,国際ルール違反のアメリカを優遇する「アメリカ・ファースト」を実践することになる。
また,アメリカは2025年4月3日から自動車に25%の追加関税を課しているが,日本からの対米自動車輸出の1台当たり単価は,前年同月比で4月に14.8%,5月に21.7%,6月に29.1%もそれぞれ減少した(注4)。高関税を受けて低価格帯車の輸出割合が増えたのかもしれないが,追加関税の負担分をメーカー側が負担することで米国内での販売価格の据え置きを狙ったとも推測される。その場合,最終的に株主への配当や従業員の賃金や下請け業者への支払いにつながったかもしれない販売利益を犠牲にして,アメリカ消費者の負担を軽減する「アメリカ・ファースト」を選択したとも言えるのである。
もちろん,それほど単純ではないであろう。短期的利益を圧縮してでも輸出台数を維持することで,中長期的に株主,従業員,下請け業者の利益を維持できるかもしれない。しかし,販売価格を調整することで価格メカニズムの作用を妨げた結果,米国内での値上がり(インフレ)が抑制され,関税収入を増大させることで,アメリカ消費者の相互関税への不満は緩和され,アメリカ政府の満足度=成功体験は増大する。相互関税に対するアメリカ消費者の反発が抑制されれば,トランプ大統領が関税を撤廃あるいは引き下げるインセンティブは低下するであろう。
悪貨は良貨を駆逐する。「アメリカ・ファースト」は無差別平等原則を蝕んで,世界各国・地域までも「アメリカ・ファースト」へと誘っている。そこで必要なことは,われ先にアメリカと二国間交渉をして許しを請うことではなく,無差別平等な多国間主義を維持するために世界各国・地域が対米交渉で協調することであろう。また,アンチ・ダンピング・ルールの従来とは異なる新たな運用方法も含めた,国際協調体制の構築も必要となるであろう。
とはいえ,不遇にあるアメリカの「忘れられた人々」は,「グローバル・サウス(注5)」の一部でもあり,そのまま放置して良いとは思われない。ただし,それに必要な資金は関税で賄うのではなく,グローバル化の恩恵に浴している超富裕層から回収したほうが経済的な合理性,効率性も高いはずである。
[注]
- (1)たとえばアメリカは日本に対して,自動車関税の導入を示唆しながら,離脱したTPPと比べて格段に有利な内容の日米貿易協定を締結した。
- (2)たとえば,遠藤正寛『輸入ショックの経済学-インクルーシブな貿易に向けて-』慶應義塾大学出版会,2023年。
- (3)日本経済新聞 2025年7月3日および7月16日(夕刊)。ただし,どちらもトランプ大統領によるSNSでの発信に基づく内容であって,詳細は不明である。
- (4)日本経済新聞 2025年7月18日。
- (5)ここで「グローバル・サウス」とは,南の国々に限られず,グローバル化のなかで不遇を受けた人々を意味している。
関連記事
小林尚朗
-
[No.1118 2018.07.30 ]
最新のコラム
-
New! [No.4178 2026.01.19 ]
-
New! [No.4177 2026.01.19 ]
-
New! [No.4176 2026.01.19 ]
-
New! [No.4175 2026.01.19 ]
-
New! [No.4174 2026.01.19 ]
世界経済評論IMPACT 記事検索
おすすめの本〈 広告 〉
-
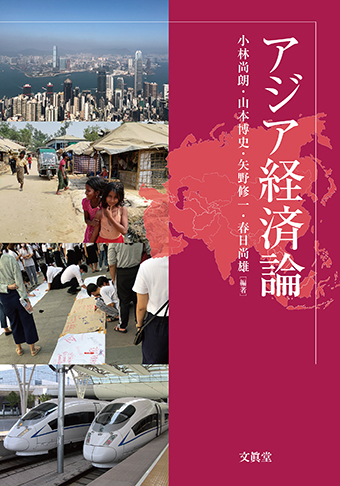 アジア経済論
本体価格:2,600円+税 2022年3月
アジア経済論
本体価格:2,600円+税 2022年3月
文眞堂 -
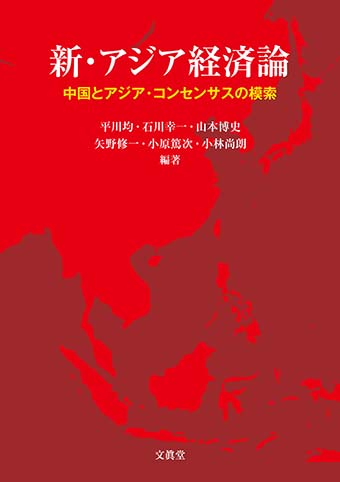 新・アジア経済論:中国とアジア・コンセンサスの模索
本体価格:2,800円+税 2016年2月
新・アジア経済論:中国とアジア・コンセンサスの模索
本体価格:2,800円+税 2016年2月
文眞堂 -
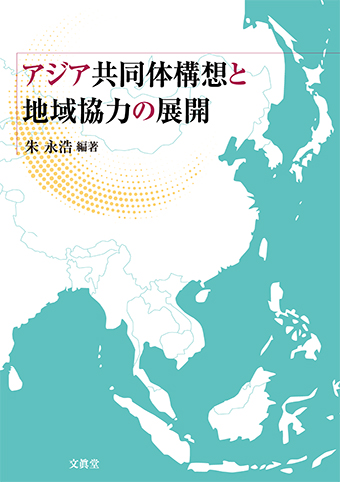 アジア共同体構想と地域協力の展開
本体価格:2,600円+税 2018年3月
アジア共同体構想と地域協力の展開
本体価格:2,600円+税 2018年3月
文眞堂 -
 グローバルサウス入門:「南」の論理で読み解く多極世界
本体価格:2,200円+税 2025年9月
グローバルサウス入門:「南」の論理で読み解く多極世界
本体価格:2,200円+税 2025年9月
文眞堂 -
 揺らぐサムスン共和国:米中対立の狭間で苦悩する巨大財閥
本体価格:2,700円+税 2025年12月
揺らぐサムスン共和国:米中対立の狭間で苦悩する巨大財閥
本体価格:2,700円+税 2025年12月
文眞堂 -
 中国鉄鋼業:生産システム,企業,産業の三層構造と産業政策
本体価格:4,000円+税 2025年8月
中国鉄鋼業:生産システム,企業,産業の三層構造と産業政策
本体価格:4,000円+税 2025年8月
文眞堂 -
 これさえ読めばすべてわかるアセットマネジメントの教科書
本体価格:2,900円+税 2025年9月
これさえ読めばすべてわかるアセットマネジメントの教科書
本体価格:2,900円+税 2025年9月
文眞堂 -
 職場・学校のセクハラ・パワハラ :ハラスメントの法と判例
本体価格:1,300円+税 2026年1月
職場・学校のセクハラ・パワハラ :ハラスメントの法と判例
本体価格:1,300円+税 2026年1月
文眞堂 -
 国際マーケティングの補助線
本体価格:2,700円+税 2025年9月
国際マーケティングの補助線
本体価格:2,700円+税 2025年9月
文眞堂 -
 サービス産業の国際戦略提携:1976~2022:テキストマイニングと事例で読み解くダイナミズム
本体価格:4,000円+税 2025年8月
サービス産業の国際戦略提携:1976~2022:テキストマイニングと事例で読み解くダイナミズム
本体価格:4,000円+税 2025年8月
文眞堂

