世界経済評論IMPACT(世界経済評論インパクト)
中国車シェア拡大下のタイ自動車産業の現状
(神奈川大学 名誉教授)
2025.06.16
世界経済における日本のシェアが低下してきたこの30年,自動車産業は世界的な地歩を維持し,日本経済の屋台骨として多くの雇用を守ってきた重要な産業である。しかしEV化の流れのなか,世界の自動車産業の構図は大きく変化し始めている。その変化の震源は中国である。中国は2010年アメリカを抜き世界最大の自動車市場となった。さらに,政府主導で多くの補助金を投入しBEV(バッテリー電気自動車)を育成した中国は,2023年輸出でも日本を上回り今や世界最大の自動車輸出国になっている。脅威を感じた欧米は中国車の輸入抑制政策に走るなか,東南アジアが中国車の有望な輸出市場となり始めた。筆者の研究分野であるタイは日系のメーカーの独断場で最近まで85%前後のマーケットシェアを占めていたが,日系のシェアの低下が起こってきている。
タイの自動車産業は輸入代替産業育成政策,輸出産業創設の典型的な成功例であった。1960年代初めから本格的に開始された日系を担い手とする輸入代替工業化政策は成功し,タイは東アジアのデトロイトと呼ばれるまでになった。日系自動車メーカーのほぼ独占であったタイ市場は,2022年以降中国メーカーの脅威を受け始めた。タイ政府のBEVへの奨励政策もありICE(内燃機関)車は苦戦を強いられ,日系のいくつかの自動車メーカーは急激な販売台数低下に直面している。BEV奨励政策の背景には,次世代技術への産業構造変化対応とPM2.5に代表される大気汚染問題がある。経営不振から日系メーカーの中にはタイでの生産を断念し撤退するメーカーも出てきた。たとえば,タイ政府のエコカー推進政策の支援下で2011年に工場を建設したスズキは,2010年代後半には6万台にまで生産台数を伸ばしその約半数を輸出するまで順調に生産を拡大していた。しかし,2024年タイ国内販売シェアは1.2%まで落ち,2025年末にタイから撤退を決定した。スズキはインドネシアを東南アジアの生産拠点とする方向のようである。スバルもスズキと同じくタイから撤退を決定している。日産は過去10%以上のシェアがあり,トヨタ,いすゞに次ぐメーカーだったが,今回の中国のシェア拡大の影響を強く受けている。2021年の国内シェアは4.3%,2024年は1.7%にまで低下している。2024年末に年間22万台の生産能力のある第一工場を閉鎖し,従業員1000人を解雇し生産能力が年間15万台の第二工場への集約を発表している。ただ,HEV(ハイブリッド電気自動車)生産拡大へ新たな投資も発表しており,タイから撤退するわけではないようである。マツダは2021年のシェア4.7%から2024年は1.7%へタイ国内販売が低下する中でも,タイでの生産を増強する方向でラヨーン県にSUV車10万台生産体制を確立するとし,2025年2月新規投資を決定している。いすゞも2021年の23.1%から2024年の14.1%へ国内シェアが縮小する中,2025年4月から主にEU向けにBEVピックアップトラックの輸出向け生産を開始し,対抗策を打ち出し始めている。このように,中国BEVのタイ市場への浸透に対する各社の対応は分かれている。
タイ政府のBEV振興策であるEV3.0は2022年5月30日に官報に公示された。EV3.0はBEVの利用促進と市場活性化を目的とし,その期間は2022年から2023年であった。BEV購入に対し電池容量が10kWhのEV車に7万バーツ,30kWh以上のモデルに15万バーツの購入補助金を設定した。この補助金を受けるためには,細かな制限規定があった。主なものとして,2022年から23年までに輸入したEV車が補助金を受け取るには,2024年に生産を開始し輸入車の同数を生産することが義務化されている。生産開始が2025年まで延期されると生産する台数は1.5倍にする必要がある。さらに2026年からタイ産のバッテリーを使用することも義務化,などである。
2024年にBEV推進策はEV3.5に受け継がれた。EV3.5の期間は2024年から2027年とされ,電池容量が50kWh未満のEV車は2024年は5万バーツ,25年は3.5万バーツ,26から27年は2.5万バーツの購入補助金を受け取れる。50kWh以上のモデルには2024年は10万バーツ,25年は7.5万バーツ,26から27年は5万バーツの購入補助金供与を規定している。
現行制度におけるBEVの有利性をみてみよう。タイに完成車を輸出する場合,乗用車関税はWTOの最恵国待遇(MFN)でCIF価格の80%だが,JTEPA協定(64.1%)を利用すると幾分低下する。しかしBEVに関する輸入関税は,アセアン(ATIGA)0%,中国(ACFTA)0%,日本(JTEPA)20%,韓国(AKFTA)40%,欧米80%となっている。中国からのBEV輸入が優遇されていることがわかる。WTOが機能不全となったなかFTA網による貿易自由化の光と影を見ることができる。特筆すべきは,ACFTAでBEVの関税率が0%となっているのは,アセアン主要国ではタイとフィリピンのみであることである。インドネシアはICEと同額の関税50%であり,ベトナムは70%,マレーシアは30%である。タイのACFTAにおけるBEV0%関税設定の説明で,BEVの輸入を想定していなかった,との解説をきくが事実ではないと思われる。
タイ国内の自動車販売価格に大きな影響を与える税に物品税があり,産業育成の手段となっている。ICEの物品税は25~50%課税され,輸入車ではCIF価格に関税をプラスしたうえでの税率となる。物品税に対し10%の地方税,さらに輸入価格,物品税,地方税の合計に7%の付加価値税が課せられるため,輸入車(ICE)の実際の税金は145%前後になる。一方,輸入BEVは関税が0%で物品税はEV3.0では2%,EV3.5で0%に付加価値税の7%のみであり,ICEに比べ大きく軽減された税率となっている。このように,中国からの輸入BEVは大きな税優遇と購入補助金で大きく価格が抑えられたことがシェアの拡大に寄与した。
中国BEVが輸入される前年2021年と2024年のタイ国内販売から,日系メーカーの市場占有率への影響を見てみよう。タイ国内の自動車市場は大きく2つの分野から形成されている。一つは乗用車とSUVの市場で経済発展とともに大きく育ってきた都市の中間層の人々を主な購買層としている。もう一つはタイ農村部の人々をターゲットとする1トンピックアップの市場である。後者の市場のほうが久しく大きくかったが,タイの就業人口に占める農林水産業の比率が低下するなか,最近はほぼ拮抗する販売台数を記録していた。2021年の77.5万台の国内販売のうち44.5%がピックアップで,乗用車とSUVは42.7%であった。2024年には国内販売は63.4万台(タイ工業連盟の数字では57.3万台)まで縮小し,ピックアップは28.6%に急低下し,乗用車とSUVの比率は59.6%まで高まった。ピックアップの昨年度の落ち込みの主因はよく指摘されるように経済不況である。低所得層でローン支払いが滞り差し押さえられる自動車が増大した結果,自動車ローンが厳しくなった。実際押収された車は2023年35万台,2024年には30万台と言われている。農村部の経済沈滞を反映している。
タイで販売されるBEVは2023年までは輸入車のみで,2024年1月から生産統計に表れてくる。2024年のBEVの生産台数は9520台で0.65%,2025年1月から4月までの生産台数は1万4082台で3.1%となり,BEVのタイ生産は3月から急増している。BEVはその機種も多様化し,販売価格もICEに対抗できる水準まで下落している。
タイの市場調査によると,BEVを選択するうえで購入の決め手となったのは維持費,特に電費の安さを挙げる購買層が多い。エコカーのトヨタのヤリスやHEVのカローラ・アルティスの燃費リッター23キロとし,電費燃費を試算した。電費をkW8キロ,電気料金を4バーツ(1バーツ約4.45円)kW,ガソリンをガソホール91の33バーツの条件で計算すると,BEVは1キロの走行に0.5015バーツ,ICEやHEVは1.435バーツとなった。タイではガソリンは日本とほぼ同価格,電気は半額に近いこともありBEVの走行燃費は約三分の一となる。最新のエコカーやHEVでない古いICEではリッター10キロ程度しか走らないので,さらに2倍強のガソリン消費となる。タイの家庭用の電圧は220VでBEVへの充電が各家庭で可能であることもBEVに有利な条件である。
中国BEVの流入で多くの日系自動車メーカーは深刻な打撃を受け,国内販売シェアは2021年の84.7%から2023年には74.3%,2024年には74.7%へ低下した。しかし日系メーカーでも総崩れという事態にはなっておらず,トヨタとホンダは健闘している。トヨタの国内シェアは2021年の31.9%から2024年には38.2%へ上昇している。ホンダも同様に国内シェアを2021年の10.9%から2024年には13.1%へと高めている。タイ政府はHEVやPHEV(プラグインハイブリッド)もBEVへの繋ぎ技術として高く評価し投資恩典を与えている。HEVの国内販売シェアは2022年に7.2%から2024年には20%へと高まっている。PHEVはまだあまり普及しておらず,国内シェアは2022年に1.3%,2024年には1.5%である。2025年の1月から4月のHEVの累計国内販売シェアは,トヨタが50.5%,ホンダは38.4%と高いシェアとなっている。BEVのタイ国内販売は2025年1-4月累計で前年の11%から13.11%へ高まった。同じ時期,HEVのシェアも20%から24.2%へ高まっている。しかし2023年のBEVとHEVのシェアはそれぞれ9.1%と10%であったことを考えると,世界の潮流と同様HEVもタイ市場で確固たる存在感を示している。
タイで急速に日系のシェアを侵食している中国BEVは脅威であるが,日系も今はHEVの販売拡大で踏みとどまっている。生産技術をめぐる大変革期のなかで状況は流動的で予測は困難である。日系メーカーと中国メーカーのタイ市場における置かれた状況を考えると,互いに引くことはできない競争が今後繰り広げられよう。
関連記事
山本博史
-
[No.3991 2025.09.15 ]
-
[No.3661 2024.12.16 ]
-
[No.3452 2024.06.17 ]
最新のコラム
-
New! [No.4178 2026.01.19 ]
-
New! [No.4177 2026.01.19 ]
-
New! [No.4176 2026.01.19 ]
-
New! [No.4175 2026.01.19 ]
-
New! [No.4174 2026.01.19 ]
世界経済評論IMPACT 記事検索
おすすめの本〈 広告 〉
-
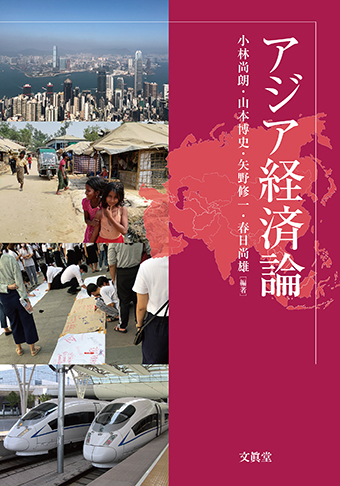 アジア経済論
本体価格:2,600円+税 2022年3月
アジア経済論
本体価格:2,600円+税 2022年3月
文眞堂 -
 アジアにおける民主主義と経済発展
本体価格:4,200円+税 2019年3月
アジアにおける民主主義と経済発展
本体価格:4,200円+税 2019年3月
文眞堂 -
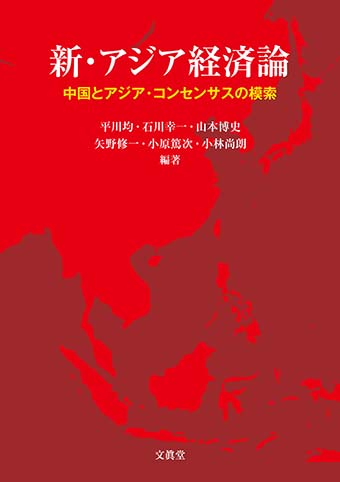 新・アジア経済論:中国とアジア・コンセンサスの模索
本体価格:2,800円+税 2016年2月
新・アジア経済論:中国とアジア・コンセンサスの模索
本体価格:2,800円+税 2016年2月
文眞堂 -
 これさえ読めばすべてわかるアセットマネジメントの教科書
本体価格:2,900円+税 2025年9月
これさえ読めばすべてわかるアセットマネジメントの教科書
本体価格:2,900円+税 2025年9月
文眞堂 -
 サービス産業の国際戦略提携:1976~2022:テキストマイニングと事例で読み解くダイナミズム
本体価格:4,000円+税 2025年8月
サービス産業の国際戦略提携:1976~2022:テキストマイニングと事例で読み解くダイナミズム
本体価格:4,000円+税 2025年8月
文眞堂 -
 中国鉄鋼業:生産システム,企業,産業の三層構造と産業政策
本体価格:4,000円+税 2025年8月
中国鉄鋼業:生産システム,企業,産業の三層構造と産業政策
本体価格:4,000円+税 2025年8月
文眞堂 -
 揺らぐサムスン共和国:米中対立の狭間で苦悩する巨大財閥
本体価格:2,700円+税 2025年12月
揺らぐサムスン共和国:米中対立の狭間で苦悩する巨大財閥
本体価格:2,700円+税 2025年12月
文眞堂 -
 高収益経営とアントレプレナーシップ:東燃中原延平・伸之の軌跡
本体価格:3,900円+税 2025年11月
高収益経営とアントレプレナーシップ:東燃中原延平・伸之の軌跡
本体価格:3,900円+税 2025年11月
文眞堂 -
 DEIBにおける経営倫理とCSRの役割:障害者雇用と女性、LGBT、がん患者の方々に焦点を当てて
本体価格:2,700円+税 2025年10月
DEIBにおける経営倫理とCSRの役割:障害者雇用と女性、LGBT、がん患者の方々に焦点を当てて
本体価格:2,700円+税 2025年10月
文眞堂 -
 国際マーケティングの補助線
本体価格:2,700円+税 2025年9月
国際マーケティングの補助線
本体価格:2,700円+税 2025年9月
文眞堂

