世界経済評論IMPACT(世界経済評論インパクト)
「強いリーダー」と短命内閣:市民社会から読み解く
(立教大学経済研究所・国際貿易投資研究所 客員研究員)
2025.09.22
日本は首相が短命になりやすいといわれるが,これは制度設計と市民社会(注1)の統制によって説明できる。本稿では,フィリピンなど大統領制諸国との比較を通じて,この現象を考察する。
1985年10月,新聞記者として,愛媛県へ赴任する直前,当時,京都大学教授だった「東南アジア研究の師」は,赴任地を「フィールド」と呼び,こう助言された――「(新聞記者なら)政治家・企業人など権力関係を手に取るようにわかるはずだ。東南アジアの首都圏で起こりうることの縮図」(注2)。のちに私がマニラやジャカルタで大統領制の力学を体感していくうえで,この言葉は心に残り続けた。
大統領令――大統領の命令が拘束力ある法規範となること――は,議院内閣制の日本では直感しにくい。私がその重みを痛感したのはフィリピンの大統領制である。マルコス(父)の下で1972年に戒厳令が布かれ,1983年のベニグノ・アキノJr.暗殺を経て(注3),1986年2月の“ピープル・パワー”によって体制は転覆し,コラソン・アキノが大統領に就いた(注4)。現行憲法は「大統領6年・再選禁止」の単任制と定め,再選容認論が浮上しても,市民の集団行動と相まって退けられてきた。さらに同国は,大統領・副大統領・上院議員は6年,下院議員・地方議員(州議会議員,市議会議員,町議会議員など)は3年の任期で多元的に選挙が行われる。
政治権力が長期化すると,取り巻き政治(クローニーキャピタリズム)と呼ばれる。再選不可の制度設計は他地域にも見られる。チリでは大統領4年で即時再選不可,韓国は大統領5年の単任制で再選できない。こうした制度は,権力集中を抑制する半面,政策継続性の確保という課題を抱える。対極にあるのが,プーチンのロシアだろう。
戦後の日本では,首長は内閣よりも「大統領型」に近い強い権限をもつ。将来を期待された国会議員が知事に転出するのが好例だ。静岡県伊東市では市長の学歴詐称疑惑を受けて不信任に続き議会解散へと事態が連鎖した。田久保市長は,与党系(自民・公明)に連合静岡も加わって推した現職が掲げた「新図書館建設」に反対,投票率が高まるなか初当選した。
兵庫県では,5期20年の井戸知事のあと,40代の斎藤知事へ世代交代した。しかし2024年9月,県議会は全会一致で知事不信任を可決し,斎藤氏は失職後の出直し選挙で同年11月に再選を果たした。個人の求心力と制度的統制のせめぎ合いは,地方も例外ではない。
石破首相は戦後35人目の首相である。在任期間は平均2年余りで,知事や市長の任期4年を超えたのは6人(注5)。短命は,「一票の格差」是正や定数配分見直しといった骨の折れる制度改革の実現を難しくしてきた。人口減少が進めば,空き家や耕作放棄地が増える。インフラの一人当たりコストは上昇する。大都市圏への人口集積は一見効率的に見えるが,住民が消えた国土を,財政で保全するとしたら,そのコストは小さくない。
強い指導者が長期政権を築く国では,市民社会の統制を欠き,公共性は持続しない。権力者が報道やSNSをコントロールして,市民社会の統制の眼をふさぐのだ。
実際,Levitsky & Way(2010)は,民主主義の安定には「競争環境の公平性(level playing field)」が不可欠であり,政権交代や短命内閣そのものよりも,制度設計と市民社会の力学こそが重要だと指摘している(Journal of Democracy)。
10月開始の国勢調査で東京圏への人口集中が一段と明らかになれば,定数配分や「1票の格差」論議は避けられない。人口急減局面を前に,各党は,選挙制度改革案を示し,民主主義の根幹「この国のかたち」を争点に据えるべきだ。社会を分断させないために必要なのは,減税や教育無償化といった分配策だけではない。市民社会が政策過程への参加を高めることこそ,リーダーの寿命に左右されない公共性を支える。
官僚機構は継続業務を得意とする一方,国政・自治体を含む立法府改革は政治主導が必須である。短命政権,政権政党が変わることがあっても,公共政策,経済政策,社会保障で,大きな違いはないのだろう。当面,過半数の連立政権が最重要課題である。合計特殊出生率は1970年代には2人を下回っている。経済・社会保障で,先送りされた政策が少なくない。党派を超えた合意形成が,必須だろう。まずは,SNS論争ではなく,同じ席で議論してほしい。
[注]
- (1)本稿の「市民社会」は,メディアやSNSを包摂する上位概念として用いる。ただし,立法府・行政府とは別のセクターとしてとらえている。
- (2)当時,京都大学東南アジア研究センター教授の示唆。1983年頃にはNHK教育テレビ市民講座「東南アジア世界の構図」を担当,1984年頃には京大法学部で「外交史」を聴講,1985年前半は朝日カルチャーセンター中之島教室で「戦争史」を講義。1985年10月,松山支局赴任直前に研究室を訪問して拝聴。
- (3)1972年戒厳令,1983年アキノ暗殺,1986年“ピープル・パワー”。
- (4)筆者は1984年3月に初訪比。『AERA』1993年12月13日号でアキノ前大統領に単独インタビュー。
- (5)安倍晋三,佐藤栄作,吉田茂,小泉純一郎,中曽根康弘,池田勇人。在任期間が長い順番から並べた。
関連記事
小原篤次
-
[No.4100 2025.12.01 ]
-
[No.3881 2025.06.23 ]
-
[No.3783 2025.04.07 ]
最新のコラム
-
[No.4149 2025.12.29 ]
-
[No.4148 2025.12.29 ]
-
[No.4147 2025.12.29 ]
-
[No.4146 2025.12.29 ]
-
[No.4145 2025.12.29 ]
世界経済評論IMPACT 記事検索
おすすめの本〈 広告 〉
-
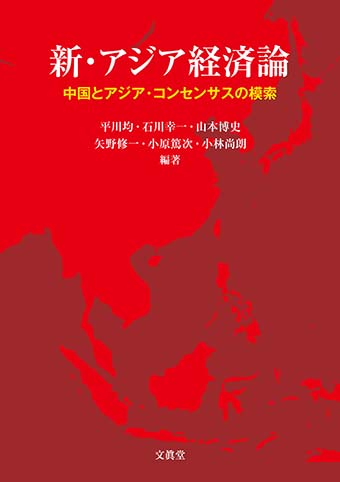 新・アジア経済論:中国とアジア・コンセンサスの模索
本体価格:2,800円+税 2016年2月
新・アジア経済論:中国とアジア・コンセンサスの模索
本体価格:2,800円+税 2016年2月
文眞堂 -
 中国鉄鋼業:生産システム,企業,産業の三層構造と産業政策
本体価格:4,000円+税 2025年8月
中国鉄鋼業:生産システム,企業,産業の三層構造と産業政策
本体価格:4,000円+税 2025年8月
文眞堂 -
 高収益経営とアントレプレナーシップ:東燃中原延平・伸之の軌跡
本体価格:3,900円+税 2025年11月
高収益経営とアントレプレナーシップ:東燃中原延平・伸之の軌跡
本体価格:3,900円+税 2025年11月
文眞堂 -
 揺らぐサムスン共和国:米中対立の狭間で苦悩する巨大財閥
本体価格:2,700円+税 2025年12月
揺らぐサムスン共和国:米中対立の狭間で苦悩する巨大財閥
本体価格:2,700円+税 2025年12月
文眞堂 -
 DEIBにおける経営倫理とCSRの役割:障害者雇用と女性、LGBT、がん患者の方々に焦点を当てて
本体価格:2,700円+税 2025年10月
DEIBにおける経営倫理とCSRの役割:障害者雇用と女性、LGBT、がん患者の方々に焦点を当てて
本体価格:2,700円+税 2025年10月
文眞堂 -
 これさえ読めばすべてわかるアセットマネジメントの教科書
本体価格:2,900円+税 2025年9月
これさえ読めばすべてわかるアセットマネジメントの教科書
本体価格:2,900円+税 2025年9月
文眞堂 -
 グローバルサウス入門:「南」の論理で読み解く多極世界
本体価格:2,200円+税 2025年9月
グローバルサウス入門:「南」の論理で読み解く多極世界
本体価格:2,200円+税 2025年9月
文眞堂 -
 国際マーケティングの補助線
本体価格:2,700円+税 2025年9月
国際マーケティングの補助線
本体価格:2,700円+税 2025年9月
文眞堂 -
 ルビーはなぜ赤いのか?:川野教授の宝石学講座
本体価格:2,500円+税
ルビーはなぜ赤いのか?:川野教授の宝石学講座
本体価格:2,500円+税
文眞堂

