世界経済評論IMPACT(世界経済評論インパクト)
日本製鉄とセブン&アイが関与した国際M&Aの教訓
(早稲田大学・文京学院大学 名誉教授)
2025.08.25
2024年から世間の耳目を集めていた2つの大型買収案件,すなわち日本製鉄(日鉄)によるUSスチール(USS)の買収と,アリマンタシオン・クシュタール(ATC)によるセブン&アイホールディングスの買収提案が決着をみた。
日鉄のUSS買収については,2023年12月に両社が合意したことを発表すると,当時の民主党のバイデン大統領も,翌2024年共和党の大統領候補になったトランプ元大統領も反対意見を述べていた。ところが,トランプ氏が大統領に再び就任するとこの案件を認め,日鉄は2025年6月に念願のUSSの買収を完了した。
もっとも,日鉄は最終的には米国政府と「国家安全保障協定」を結ぶことになった。その内容には,USSの取締役の過半数を米国籍が占めること,2兆円の買収金額に加え,2028年までにUSSに1兆6000億円の追加投資をすること,労働者を解雇しないことなどが盛り込まれた。さらに,日鉄は米国政府に,同政府の同意なしに日鉄側が重要な意思決定をおこなわないことを担保する「黄金株」を提供した。
一方,ATCは,2025年7月に「セブン&アイが誠実な対応をしない」という理由で買収提案を撤回し,セブン&アイの態度を非難した。これに対して,セブン&アイはATCの発言には多くの誤りがあると反論した。
セブン&アイは,今後は独自の成長戦略を取ることとし,コンビニ以外の事業を切り離し,コンビニに専業化することを決定した。そのため,セブン&アイは今後5年間に,ATCの提案を超える財務面の強化と,オペレーションの改革を行うと公表した。日本国内では,1000店の純増や既存店5000店以上への設備投資を実施する。米国市場では,米子会社7-Eleven, Inc.の株式上場,新規出店1300店,レストラン併設店1100店開業,利益率の高いプライベートブランド(PB)商品の拡充,そして宅配サービス「7NOW」の推進をあげている。
これら2つの国際M&Aの経緯と結果をみると,米国をベースに活動する経営者や政治家の国際M&Aに対する考え方と,日本の当事者のそれに対する考え方の相違が浮かび上がる。ATCはこれまで,サークルKなど他社を買収することによって急成長してきた。ATCは当初セブン&アイを6兆円で買収するといっていた。しかし,セブン&アイ側が拒否すると,7兆円に金額を吊り上げた。この頃には,まだ米国を中心とする景気も期待でき,資金調達にも自信があったにみえた。
ところが,トランプ2.0の誕生後,株式市場ではAIや半導体企業を中心に活況を呈しているが,食料品や日用品の物価高騰により消費者マインドは落ち込んでいる。とりわけ中・低所得層を対象としている米国のコンビニ業界の落ち込みは顕著となった。ATCの株価も下落し始め,経済の将来見通しに懸念が持たれるようになった。セブン&アイの中核事業である国内のコンビニ事業も,2016年のカリスマ経営者の退陣以降,かつての1強支配の力は失われ,構造改革には時間がかかるようにみえる。こうした状況をみて,ATCは無理にM&Aを推し進めると財務的なリスクが大きくなると判断し,提案を撤回したと思われる。
他方,日鉄にとって,USSの買収によって成長市場と期待される米国市場でシェアを高め,収益をあげることは世界戦略上,韓国・中国・インドの競合企業に対抗するためにきわめて重要な決定であった。経営陣が現在の経済状況が続けば,資金調達もその負担も「何とかなる」と考えたのも当然といえる。
ただ,日鉄にとって,買収のための巨額の投資は,日本国内市場の発展が望めず,米国経済が停滞してくると,経営上の大きな負担になりかねない。USSの老朽化した工場でこの8月に起こった事故が示すように,今までみえなかった問題が浮上する可能性もある。また,企業文化の異なる企業の買収後の事業統合(PMI:Post Merger Integration)は,きわめて困難が予想される。1980年代には,日本経済のバブルによる収益や円高を背景に,多くの日本企業が米国企業を買収した。三菱地所のロックフェラーセンター,ソニーのコロンビアピクチャーズ,松下電器のMCAの買収などは,今でも記憶に新しい。
三菱地所のロックフェラー買収については,同社が活用していた米国のアドバイザー企業が,米国ではすでに不動産事業のM&Aはマネーゲームになっているので,この買収はきわめてリスクが高いからやめた方がいいと助言した。しかし,当時の三菱地所の経営者はその意味が十分に理解できなかったようだ。買収に突き進んだ結果,経営上の困難に直面し,結局同センターを売却せざるを得なくなった。松下はMCAを売却して大きな損失を出し,後の同社の低迷を招いた。ソニーについてもダメージは大きかった。ただ,ソニーはエンターテイメントに将来性を見出し,忍耐を重ねた結果,現在はこの買収を活かし,収益の大きな柱として育てた。だた,その道のりは遠く険しいものであった。
セブン&アイがまだイトーヨーカドーグループ(IYG)と呼ばれていた1990年に,セブン―イレブン・ジャパン(SEJ)の親会社である米国のサウスランド社が倒産した。他社に買収されると,セブン―イレブンのブランドイメージが傷ついたり消滅したりする恐れがあるとして,当時のSEJ経営者がサウスランド社の買収に乗り出した。
サウスランド社の株主,オーナーの負債,債権者に対する資金的な対応と同時に,再建に向けての資金調達が必要になった。当時,日本経済は長期の停滞期に入ったが,コンビニは新たな小売業態とし成長し続けた。そのため,IYGはこうした資金負担を何とか乗り越えることができた。だが,サウスランド社の再建から成長に向かうまで10年の歳月を要した。
日鉄のUSS買収に関与したトランプ大統領やセブン&アイへの買収提案をおこなったATCの経営陣とっては,投資はマネーゲームへの資金源確保に過ぎないようにみえる。今回の2つ国際M&A案件は,日本企業の経営者にとって,買収する側あるいは買収される側いずれになろうと,その対応に多くの示唆を与えてくれるものといえよう。
関連記事
川邉信雄
-
[No.4105 2025.12.01 ]
-
[No.3786 2025.04.07 ]
-
[No.3620 2024.11.18 ]
最新のコラム
-
New! [No.4178 2026.01.19 ]
-
New! [No.4177 2026.01.19 ]
-
New! [No.4176 2026.01.19 ]
-
New! [No.4175 2026.01.19 ]
-
New! [No.4174 2026.01.19 ]
世界経済評論IMPACT 記事検索
おすすめの本〈 広告 〉
-
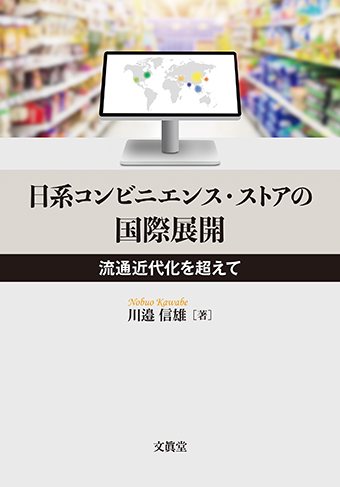 日系コンビニエンス・ストアの国際展開:流通近代化を超えて
本体価格:3,800円+税 2023年5月
日系コンビニエンス・ストアの国際展開:流通近代化を超えて
本体価格:3,800円+税 2023年5月
文眞堂 -
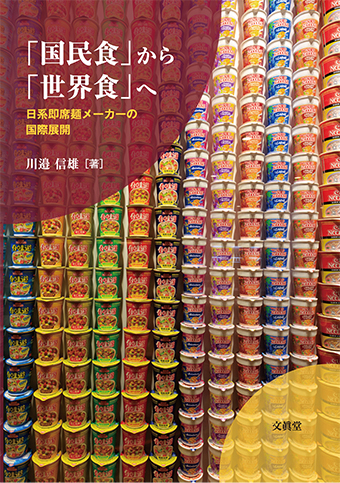 「国民食」から「世界食」へ:日系即席麺メーカーの国際展開
本体価格:2,800円+税 2017年10月
「国民食」から「世界食」へ:日系即席麺メーカーの国際展開
本体価格:2,800円+税 2017年10月
文眞堂 -
 国際マーケティングの補助線
本体価格:2,700円+税 2025年9月
国際マーケティングの補助線
本体価格:2,700円+税 2025年9月
文眞堂 -
 揺らぐサムスン共和国:米中対立の狭間で苦悩する巨大財閥
本体価格:2,700円+税 2025年12月
揺らぐサムスン共和国:米中対立の狭間で苦悩する巨大財閥
本体価格:2,700円+税 2025年12月
文眞堂 -
 DEIBにおける経営倫理とCSRの役割:障害者雇用と女性、LGBT、がん患者の方々に焦点を当てて
本体価格:2,700円+税 2025年10月
DEIBにおける経営倫理とCSRの役割:障害者雇用と女性、LGBT、がん患者の方々に焦点を当てて
本体価格:2,700円+税 2025年10月
文眞堂 -
 ルビーはなぜ赤いのか?:川野教授の宝石学講座
本体価格:2,500円+税
ルビーはなぜ赤いのか?:川野教授の宝石学講座
本体価格:2,500円+税
文眞堂 -
 サービス産業の国際戦略提携:1976~2022:テキストマイニングと事例で読み解くダイナミズム
本体価格:4,000円+税 2025年8月
サービス産業の国際戦略提携:1976~2022:テキストマイニングと事例で読み解くダイナミズム
本体価格:4,000円+税 2025年8月
文眞堂 -
 高収益経営とアントレプレナーシップ:東燃中原延平・伸之の軌跡
本体価格:3,900円+税 2025年11月
高収益経営とアントレプレナーシップ:東燃中原延平・伸之の軌跡
本体価格:3,900円+税 2025年11月
文眞堂 -
 職場・学校のセクハラ・パワハラ :ハラスメントの法と判例
本体価格:1,300円+税 2026年1月
職場・学校のセクハラ・パワハラ :ハラスメントの法と判例
本体価格:1,300円+税 2026年1月
文眞堂 -
 これさえ読めばすべてわかるアセットマネジメントの教科書
本体価格:2,900円+税 2025年9月
これさえ読めばすべてわかるアセットマネジメントの教科書
本体価格:2,900円+税 2025年9月
文眞堂

